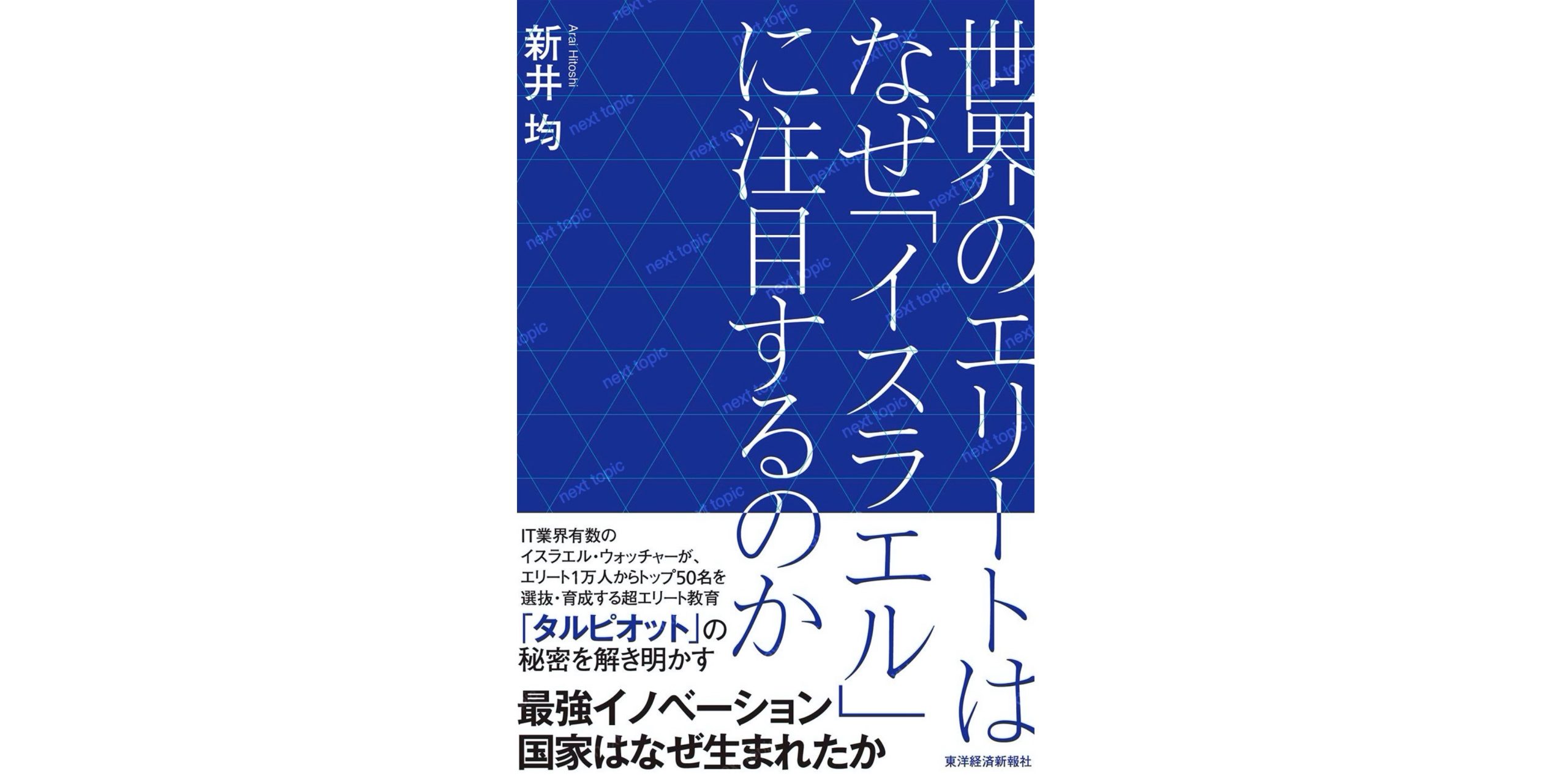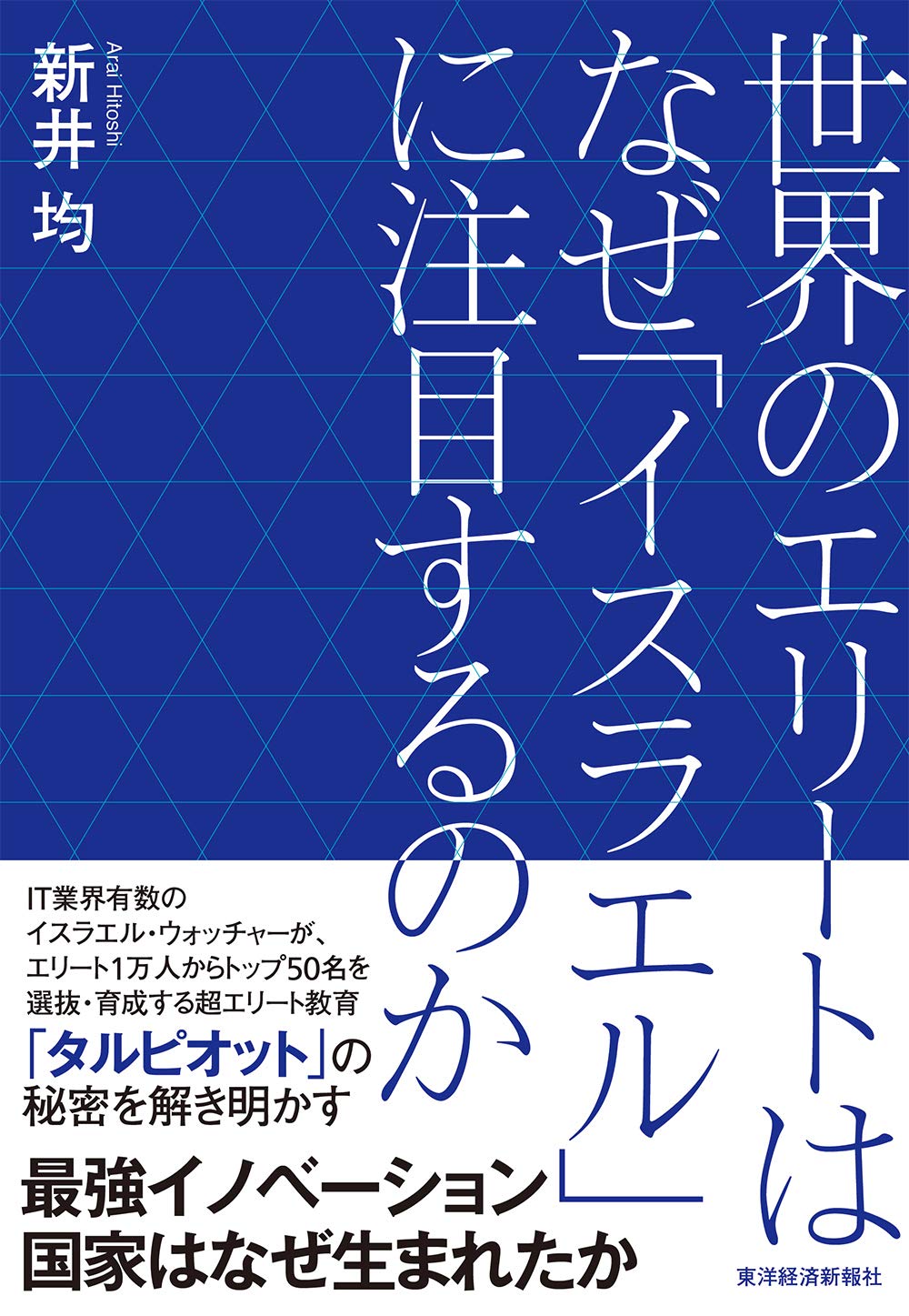【最新 イスラエルについて学ぶためのおすすめ本 – 歴史、経済、政治から最新情勢まで】も確認する
イスラエルの技術をヒントに新たな視点を示す
イスラエルの教育システム「タルピオット」に着目し、エリートを育成するプロセスが解説されています。多様な論点から日本とイスラエルを対比しながら、日本の進むべき針路への示唆されています。教育・人材育成において新たな視点を与えてくれる一冊です。

まえがき
私自身の社会人としてのスタートはNTT(当時日本電信電話公社)の研究者である。電電公社は典型的なドメスティック企業だったが、1985年に民営化してNTTとなってからは国際通信にも関わり、私自身の仕事も海外との接点が増えていった。ただ、そのほとんどがアメリカだった。イスラエルとの接点ができたのは、NTTを辞めて7年後の2007年である。イスラエルという国に特に関心があったわけではなく、単に興味ある技術を持つ提携先企業の国がたまたまイスラエルであった、に過ぎない。もちろん、当該企業とのビジネスをうまく進めるために、“ありがとう”という言葉をヘブライ語ではなんと言うんだろう、といった程度の好奇心はあったが、その後13年間も多くのイスラエルの人々と付き合い、彼らから学ぶだけではなく、彼らの生活・文化にまで興味を持ち、自ら調べることになるとは想像もしていなかった。逆に、新聞やニュースでイスラエルが非難される報道を見聞きすることもあり、正直なところ、当初は“あまり関わらないほうがよい”とも考えていた。
それが、仕事の範囲を超えてイスラエルに興味を持つようになった理由の一つは、出会ったイスラエル人たちの多くが、とてもよく日本のことを知っており、総じて親日家であったということが大きい。それも教科書やガイドブックの知識レベルではない。息子の好きな漫画が『NARUTO(ナルト)』で彼は全巻持っている、と言った企業経営者や、僕は梶芽衣子の歌が好きでCDを持っていると言った若いエンジニアもいた。彼らは日本にこれだけ興味を持ち、色々なことを知っているのに比べ、自分はイスラエルのことを何も知らなかった。私が知っていたことといえば、ホロコースト以外には、1972年に日本赤軍の岡本公三がイスラエルの空港で銃を乱射して大勢の人々を殺害したこと、好きな音楽家の一人であるイツァーク・パールマンがユダヤ人であること、くらいであった。さすがに余りに何も知らないというのはビジネス儀礼上も失礼かと考え、少しずつ調べ始めたところ、学べば学ぶほど、イスラエルという国(及び建国前のユダヤ人)の長い歴史・文化・習慣等が日本のそれとは大きく異なる部分がある一方で、逆にとても似ている側面もある、ということに興味を抱くようになった。それが、以降13年間にわたりイスラエルと付き合うことになったきっかけである。
日本と異なる点がたくさんある中で、彼らを理解する上で重要だと思う事例の一つは、「彼らは早く大人になる」という事実である。ユダヤ教の成人式は、男子がバル・ミツバ(写真)と呼ばれ13歳、女子はバット・ミツバと呼ばれ12歳である。ミツバとはユダヤ教の戒律のことであり、戒律を守ることができる年齢が成人とされる。もちろん、成人といっても結婚できるとか、選挙権が与えられるという意味ではないが、宗教的には戒律を守ることができる、自分の行動に責任を持てる年齢になったと見なされる。この成人式には、外国に住んでいる親類縁者もお祝いのために駆けつけ、男子はトーラーと呼ばれる聖書の律法(人々が守るべきルール)を参加者の前で暗唱せねばならない。この儀式はエルサレムの聖地「嘆きの壁」の前で行われることも多いという。私も嘆きの壁を訪れた際、何度かその場面に出会った。無事に式が終わると、親族だけではなく、その場にいる人々も歓声をあげて祝福する。その後、参加者は家やレストランに移って、大勢でお祝いの宴をする。13歳の少年が、大勢の人々の前でかなり長い聖書の言葉を暗唱するのは、かなりのプレッシャーではないかと想像する。しかし、彼らは皆それを乗り越え、社会から大人として扱われるようになる。戒律を自分で守れる年齢になり、もしその義務を果たせずに過ちを犯した場合には、自分自身で責任を取る、という存在となる。不思議なもので、この日を境に、子供たちはすっかり頼もしくなってゆくようだ。
写真バル・ミツバ

撮影者Yonatan Sindel
Credit attribution requested for the photographer and for the Israel Ministry of Tourism.
それは宗教上の儀式だろう、と思う人もいるかもしれないが、イスラエルでは宗教は日常生活の中に深く組み込まれているので、我々日本人の感覚に照らして言えば、七五三のお宮参りをするのと同じレベルの「生活に根付いた文化・習慣」であると言ってよいだろう。かつ、日本の場合はこのような「文化・習慣」のイベント色が強くなっているが、イスラエルの場合は「それに付随する意義」がなお大変大きな意味を持っており、日常生活の中に影響を与えているのだ。例えて言えば、我々は、大相撲を興行・スポーツとして楽しむが、もとを正せば相撲は「神事」である。この「神事」の部分を頑なに守り、それが日常生活の中で大きな意味を持っているようなものである。さらに、後の章でも触れるが、イスラエルの若者は男女共に18歳で兵役に行く。13歳で社会から大人として迎え入れられ、18歳になると兵役という厳しい経験をすることで、若者たちは、日本の10代よりもずっと早く大人の自覚を持ち逞しくなる。こんなことに言及したのは、これが、年間1000社以上のスタートアップを輩出するというダイナミズムを持つ今のイスラエルを作り上げた、彼らの強みにつながっていると感じているからである。
言うまでもなく、今の日本は変革を求められている。1970年代に高度経済成長が終わり、1990年代にバブルも崩壊して不況期に入って以降、いまだデフレから抜け出せないにもかかわらず、日本社会全体はその状況変化に対応できないまま惰性で生きているようなものである。過去の成功体験からなかなか抜け出せない、ある種の思考停止状態と言ってもよい。2010年以降、過去に経験したことがない人口減少の局面に入り、何も手を打たなければ経済は縮小してゆくことは自明であるにもかかわらず、“問題の先送り”以上のことにはなかなか踏み切れない。状況を打開するために求められるのは、産業構造の変革であることは間違いないだろう。品質の良いモノを大量生産することで、世界第2位の経済大国であった時代ははるか昔に過ぎ去り、グーグルやアマゾンのようなイノベーションを興すことで、成長軌道に回帰することを模索する以外には我々が進むべき道はないはずだ。
そのグーグルやフェイスブックのような多くの世界の先端企業がイスラエルに進出し、投資をし、あるいはイスラエルの技術を取り入れて自らの事業に活かしている。つまり、イスラエルには、これら先端企業の競争力の源泉ともなる魅力的な“資源”があるのだ。我々も先達に倣ってその資源を探し、その資源を生み出しているスタートアップ・ネーション、イスラエルのやりかたを学ぶこと、が必要ではないだろうか。当初、そこまでの問題意識はなかったものの、親日家である彼らの国のことを少しでも知ろうとして13年間付き合ってきた中で、我々日本人にとって参考になることが色々見えてきたのである。本書では、様々な形で日本とイスラエルを比較し、彼我の比較
において、我々が学べることがないか、を模索する。前半では、筆者自身がイスラエルをより良く理解するために、ユダヤ人の歴史や宗教、イスラエルの取った経済政策等を学びながら振り返った。しかし、読者によってはこれらの内容が教科書的で退屈かもしれない。その場合には第2章、第3章は読み飛ばして頂いて構わない。ただ、第4章の「超エリートを育てるタルピオット・プログラム」だけは是非読んで頂きたい。余り知られていないこの独自の「エリート教育」こそが、現在のイスラエルの強さを作り上げた秘密であり、我々が学ぶべき点であると考えるからである。
2020年4月
新井均
世界のエリートはなぜ「イスラエル」に注目するのか――目次
まえがき
プロローグ
第1章 身近にあるイスラエル技術
パソコンの頭脳であるインテルのプロセッサ
世界のエリートはなぜ「イスラエル」に注目するのか
USBメモリー
チェリートマト
インスタントメッセンジャーの元祖はICQ
フェイスブックの顔認証
VoIP通信
ファイアウォール
シスコのハイエンドルータCSR-1
カプセル内視鏡
第2章 生きるために制約を乗り越える:イノベーションを生む土壌
不毛の地で水を確保する
限られた水の有効利用:点滴灌漑
海水から水を作る
産業政策:BIRD
産業政策:ヨズマ
移民社会の持つ多様性
第3章 人を育ててきた歴史とイスラエルが取った戦略
建国の歴史と中東戦争
ユダヤ人の歴史
移民政策
経済成長の実現
第4章 超エリートを育てるタルピオット・プログラム
ジューイッシュ・マザーとは?
技術エリートを育てるタルピオット・プログラム
1万人から50人を選び出すプロセス
3年間のエリート教育の厳しい内容
活躍するタルピオット卒業生たち
第5章 教育を重視するイスラエルの文化的背景
人種の多様性
バラガン、フツパーと言われるイスラエル人の気質
失敗を尊ぶ文化
「学ぶ」宗教
第6章 日本とイスラエルとの違い
静の日本、動のイスラエル
均質な日本、多様性のあるイスラエル
学力をつける日本、子供の好奇心を育てるイスラエル
会社組織中心社会日本、誰とでもつながるソーシャルネットワーク社会イスラエル
品質管理の日本、QA(クオリティ・アシュアランス)のイスラエル
付加価値の作り方が異なる
他国に支配されたことのない日本、他国に支配され続けたユダヤ人
ハーバードの研究結果でも対極に置かれた日本人とイスラエル人
産業革新投資機構(JIC)とヨズマ
第7章 イスラエルから学べること、我々がなすべきこと
規制緩和
学ぶことが楽しい教育
多様性を尊ぶ社会
挑戦することが尊ばれ、失敗を許容する文化
日本が世界から求められる価値を育てる
尖った人材を育てる
あとがき
参考文献
プロローグ
取っ掛かりとして、多少長くなるが、私自身のキャリアとイスラエル企業との関わりから始めることをご容赦願いたい。
「まえがき」で述べたように、私自身はNTT(当時日本電信電話公社)の研究者として社会人をスタートした。今なら優秀な人材が集まるのはGAFAかもしれないが、1980年当時としては、NTTの研究所は日本でもトップクラスの人材を集めた研究機関であり、自分自身がその一員になれたことは正直誇らしかった。新しい部品・装置の技術開発を進める研究所の一員として、約10年間、主にアモルファスシリコンを用いたトランジスタとその応用の研究開発に従事した。残念ながら、大勢の優秀な人材の中に埋もれた私自身は、研究者としては全く能力不足で大した成果を上げることはできなかった。まともな論文は1件しか書いていない。厚顔にも、それを棚に上げて勝手なことを言わせてもらうと、この10年にわたる研究所生活での主な発見は、
・研究者とは総じて保守的であり、自分の得意な研究フィールド、テーマを守り、新たな分野への挑戦をしたがらない人種である
・新たな研究計画を作り予算のための審議をしてもらうときには、必ず「先行事例」「競合他社比較」を求められた
・優れた成果を出している研究者は、必ずしも新たな分野の研究企画をすることが得意であるとは限らない
という三点であった。当時の仲間には不興を買うであろう暴言であることを承知で言えば、当時NTTの研究所で行われていた研究テーマの多くは、特に基礎研究ではなく応用に近い領域では、革新的であるというよりも、既に誰かが取り上げている課題についてアプローチを変えているようなテーマが多かった。また、研究者として多くの論文・研究成果を生み出す問題解決能力に優れた人材は大変多かったが、これらの優れた研究者が必ずしも新たな課題(研究テーマ)を掘り起こし、提起する力があるわけではなかったと思う。
モノ作りをする企業を「メーカー」と呼ぶのに対し、NTTのような通信企業は「ユーザ」と呼ばれる。メーカーの作るシステムを導入する(利用する)ことで、自社のサービスを提供するから、である。NTT研究所で開発した有力な技術はメーカーに技術移転され、そのメーカーが作る通信システムの中に導入されてNTTの通信ネットワークの中で使われる。NTT研究所の使命自体が通信サービス・ネットワークの高度化・経済化に寄与する技術開発、であることは間違いないので、優れた成果が活用されることはもちろん望ましいことである。ただし、NTT自身が毎年兆円単位の投資をしているので、いわばNTT自身が一つの「市場」であることを理解せねばならない。無論、他社よりも劣った自前の技術を無理に採用する、ということは絶対になかったが、オープンな市場の中で競合他社の類似技術と競争し、性能やコストで顧客に選ばれる、という世界とは少し異なっていた。電電ファミリーという言葉がその市場の中でNTTの計画に沿って技術開発に協力してくれるメーカー群を指すように、ある意味ではよくできた仕組みであることは間違いないが、平場で競争にしのぎを削る環境、とは少し異なっていた。
その後、アメリカのビジネススクールに留学したことも契機となり、研究者から方向転換してビジネスの世界に入り、2000年にはNTTも退職して外資系メーカー企業で働くなどいくつかの転職を経験した。そして、2007年にチャンスにめぐりあい、イスラエルのインフォジン社(当時)の技術を利用してモバイルサービスを提供するベンチャーを数名で始めた。そのサービスとは、パソコン向けのホームページを、携帯電話やその後出てきたスマートフォンの画面で最適なサイズ・レイアウトで読めるように自動変換を行う、というものである。現在では当たり前となった手法だが、まだiPhoneが日本市場に登場していない2007年当時では、類似のサービスは他に1、2件しかない目新しいものであった。これが冒頭に述べた、私とイスラエルとの最初の出会いである。その後7年間、大手のクレジットカード会社、銀行、航空会社等、いくつかの日本の大手企業へサービスを提供したが、30件以上の安価な競合サービスが登場し、自身の経営者としての能力不足もあってビジネスを思うように伸ばすことができず、2014年に会社ごとサービスを他社に譲渡して59歳のときに仕事人生に区切りをつけることにした。大企業のサラリーマンから起業まで、更には研究開発から営業や顧客サポートまで、およそ自分がやれそうなことは大体経験したという思いもあり、その後はリタイアの気持ちでいたが、7年間モバイルサービスのために共に働いて仲良くなったイスラエルの友人の求めに応じて、イスラエルのスタートアップ、C社のトレーニングサービスの日本市場開拓支援に携わることとなった。
C社のサービスとは、電力や鉄道など社会インフラとも言われるシステムを運用する事業者へのサイバーセキュリティ・トレーニングである。顧客のチーム(5~15名程度)に、タービン発電機やその制御システム等の実設備の備わったC社のトレーニングアリーナに来てもらい、実際に顧客が日常業務で実施しているようなシステムのオペレーション作業をしてもらう。そこにC社のハッカー(レッドチーム)が“本物のサイバー攻撃”をしかけ、攻撃を受けるとシステムがどうなるか、を顧客に実体験してもらうのだ。当初、私自身がなかなかこのサービスの意義を理解することができなかったが、理解できたときにはその発想の面白さに愕然とした。
当時、日本におけるサイバーセキュリティ対策といえば、ファイアウォールをはじめとして、IDS(不正侵入検知システム)、IPS(不正侵入防止システム)等、社内システムやウエブサイトを外部の攻撃から如何に守るか、という視点での様々な技術・ツールを導入することであった。すなわち、「如何に外部からの攻撃をブロックし、企業ネットワーク内部に侵入されないようにするか」という「入口対策」のソリューションがすべてと言っても過言ではなかった。ところが、このイスラエル企業、C社の発想は全く異なっていた。彼らは、サイバー攻撃を100%防ぐということはあり得ない、という前提に立っている。所詮技術の世界なので、どんな素晴らしい防御技術を導入したところで、早晩それを超える攻撃技術によって破られる、と考えているのである。であれば、攻撃されて被害が発生したときに、如何に迅速に原因を把握し、効果的なリカバリ対策を打てるか、という点に注力したほうが現実的なメリットがある、と彼らは考えているのである。すなわち、入口を守るのではなく、「出口の対策」に注力するのだ。そのために必要なのは、「実際の攻撃とそれにより発生する被害を常日ごろ経験しておくことであり、演習が重要だ」というのが彼らの発想なのである。常日ごろ演習で経験を積んでおけば、万が一本物の被害に遭ったときに、迅速に的確な対策行動がとれるのである。
考えてみれば、これは、日本人が定期的に学校や企業で経験している「地震・火災を想定した避難訓練」の考え方と全く同じである。2020年の現在、この「出口対策」という考え方は日本のサイバーセキュリティ分野の中でも既に市民権を得ている。しかし、私が日本市場開拓を始めた2014年には、「いくら入口のセキュリティ対策をしてもどうせ破られるのだから、出口対策をしましょう」というメッセージを理解した日本企業は一社もなかったと断言できる。
イスラエル人とは、こういう現実的かつ面白い思考・発想ができる人達なんだ、とわかり、それまでもイスラエルとは付き合っていたが、更に興味を持ってイスラエル企業並びにイスラエル人をウォッチし始めた。意識して見始めると、イスラエルのスタートアップが開発している商品には非常にユニークな視点のものが多かった。最近の有名な事例では、自動車の衝突防止システムに利用されるモービルアイ(https://www.mobileye.com/)がある。衝突防止システムとしては、日本でもスバルのアイサイトが有名だが、アイサイトが二眼のカメラで前方障害物・車間距離等を計測するというオーソドックスな手法であるのに対し、モービルアイはカメラが単眼であるにもかかわらず、情報処理技術により前方車間距離や車線、歩行者等を検知することができる。この技術はヘブライ大学のアムノン・シャシュア(Amnon Shashua)教授(当時39歳)により開発された。この独自の画像処理アルゴリズムをもとに、EyeQチップというプロセッサを開発した。2017年8月にインテルが約153億ドル(1.7兆円)という高額でモービルアイを買収したのは記憶に新しい。単眼のカメラで深度を測定するということで、後付けの衝突警報装置として広く普及している。現在(2018年12月)、EyeQチップの搭載されている車両は世界で2400万台あると言われる。日本車では日産のセレナに使われている。モービルアイは更にREMと呼ばれる道路情報収集・解析機能を開発した。道路の情報、存在する障害物等を、数センチの単位で理解し、コネクテッドカーであればそのデータをクラウドに送信し、そのデータをもとに高精細の地図を作成することができる。自動運転のプロジェクトでは、車はカメラやレーダーからの情報とこの地図とをもとに状況認識・判断を行う。GPSを利用する場合の位置精度は約1メートルだが、モービルアイのカメラでは5センチの精度が可能である。また、REMではリアルタイムの地図が作られるため、ゼンリンの地図やグーグルマップには現れない工事現場とか、その標識等も含まれる地図となり、例えば工事のためにある区間が片側車線の相互通行になっているなど、より現実に即した、いわば人間のドライバーが認知するのに近い判断材料を自動運転車に提供することが可能となる。モービルアイが装着された2400万台の車が走るだけでこのような地図がリアルタイムで生成され、それをまたモービルアイが利用しながら車の運転をアシストする世界を想像すると、モービルアイは、単に衝突防止システムだけではなく、自動運転の世界のインフラにもなる可能性があることが理解できるのではないだろうか。
また、モービルアイ共同創業者であるアムノン・シャシュア教授とジブ・アビラム(Ziv Aviram)氏は、2010年に別の企業オーカム社(https://www.orcam/ja/)を創業し、2015年にメガネに取り付けて視覚障害者の生活を支援する小型のデバイスMy Eye(写真0-1)を開発した。視覚障害のある方が付けているMy Eyeのカメラが、捉えている新聞の文字を読みあげる、店で服の色を識別し教えてくれる、目の前の人の顔認証をしその名前を言ってくれる、等のアシストをする。視覚障害のある人々だけではなく、記憶力が悪くて“顔はわかるが名前がなかなか思い出せない”筆者のような人間にとっても大変魅力的なツールである。2017年2月の時点で、企業価値が10億ドル以上と評価されている、いわゆるユニコーン企業となった。
写真0-1MyEye

ORCAM社ホームページより
このような事例は枚挙にいとまがない。イスラエル企業は、独自の視点で、現実に役に立つものを開発し、投資家という第三者の高い評価を得るのである。イスラエルでは年間1000社以上にも及ぶスタートアップが登場するが、そのほとんどに独自のエリート教育を受け、兵役として軍の技術開発に関与した“トップ・オブ・トップ”の人材が何らかの形で関わっているそうだ。かつ、マイクロソフトやグーグルをはじめとする世界中の300社以上にも及ぶ多国籍企業が、彼らの技術力を活用するためにR&Dセンターをイスラエルに開設している。この事実は、技術立国を標榜してきた日本にとっても、イスラエルは見逃すことのできない国であると考えざるを得ないことに気づかせてくれる。人口900万弱の国では国内の市場というものはないに等しい。従って彼らは最初からアメリカ市場、ヨーロッパ市場で勝負することを前提に技術開発を進めている。そして有望な技術・事業には数億ドルという規模の投資も集まる。そこには、自分で開発した技術を自分で使う仕組みのあるNTTの研究開発部門で見た技術開発とは、全く異なるワクワク感があった。
イスラエルのように、魅力的なスタートアップを次々に興してゆくには、我々はどうすればよいのだろうか?我々に足りないものは何なのだろうか?
今一度歴史を振り返ってみると、資本や人材に恵まれた大企業がある種の武器としていた“情報の非対称性”がインターネット関連技術の進化により崩れ、特徴のある中小企業や独自の技術を持つスタートアップが対等以上の競争力を持ち始めた。イスラエルはそのような「競争力の宝庫」であると言える。かつて一世を風靡したiモードというビジネスモデルもスマートフォンとともに市場から退場し、日本メーカーはそのスマートフォン端末市場からもほぼ撤退した。ドコモ向けに数百万台のスマートフォン端末ビジネスをしてきた日本メーカーと、世界市場で数千万台/1シリーズのスマートフォンを売っている中国・韓国メーカーとでは、コスト競争力が桁違いであることは今更比較するまでもない。日本市場向けの仕様がグローバルな市場ニーズと異なることもあるが故に、世界市場を狙おうとすると追加の開発コストもかかることになる。中途半端に大きな日本市場でそれなりのビジネスができるがゆえに垂直統合型を志向した日本企業は、ディスインテグレーション(分業)の流れに乗り遅れていると言える。
高等教育課程で学ぶ学生自身もあまり専門能力を身につけているとは言えないかもしれないが、学生が学んできた力を即戦力として活用するという発想ではなく、新卒学生を一括採用して、企業文化も含めて新人研修で訓練して自社で使える人間として育ててゆくことの多い日本企業では、企業独自の業務プロセスを理解し、内部調整能力の優れた人間が幹部として活躍しがちである。多くの日本人にとって、就職=就社であり、人材の流動性も昔に比べれば多少改善されてきたとはいえ、外国に比べて決して高くはない。一つの会社(及びその子会社、関連会社)で35年から40年間勤め上げることがまだまだ多数派であり、それを前提とした退職金、企業年金という仕組みは、中途採用者や海外から来たエンジニアには不利にできている。このような状況は、50年前の高度経済成長時代も、停滞期にある現在も残念ながらあまり変わらない。
「変わらない」根本原因の一つは我々の社会の「均一性」ではないだろうか?子どもたちは同じ教科書で同じことを一斉に学ぶ。小学校では落ちこぼれを出さないように、低いレベルに合わせた授業内容になりがちだ。確かに、画一的な教育は、それなりに質の高い多数の労働者を生み出し、大量生産のモノ作りによる高度経済成長時代のビジネスを支えた。しかし、それで成功した時代はとうに終わりを告げたにもかかわらず、教育の現場は変わっていない。このような画一的な教育で育った大人たちが、他者と異なる意見と意見を戦わせるような機会も少ない均一な社会で「空気を読みながら」働く。その結果、世界の多様性と向き合い、議論し、変化を捉えながら自らの進むべき方向を見出す力、に乏しくなっているのではないだろうか?
このような素朴な疑問に対して、多様性に溢れた社会の中で、トップ・オブ・トップのエリートたちがイノベーションのダイナミズムを作り出すイスラエルに、我々が参考とすべき答えのヒントがあるのではないか、と感じるようになった。「まえがき」で紹介したように、イスラエルの少年は3歳で責任ある大人として扱われ、18歳で厳しい兵役を経験する。このような経験を通して、養われる胆力も、多くの若者が起業という挑戦に立ち向かうだけのエネルギーにつながるのではないか。また、3年間の兵役(女子は2年)の間、共に暮らし、厳しい訓練を受けた仲間同士の関係は、人間関係が希薄になってきている日本人には想像できないほど深く、濃いもので、その関係は一生続くという。この濃いネットワークが、起業にも大いに役立つらしい。このような、文化・習慣も含め、社会の仕組み、教育のありかた、等で、日本がイスラエルから学べるのではないかと考えられる点、が多々見え始めた。特に、タルピオット・プログラムという技術エリートを育てるプログラムを知ったときに、その思いは更に強くなった。