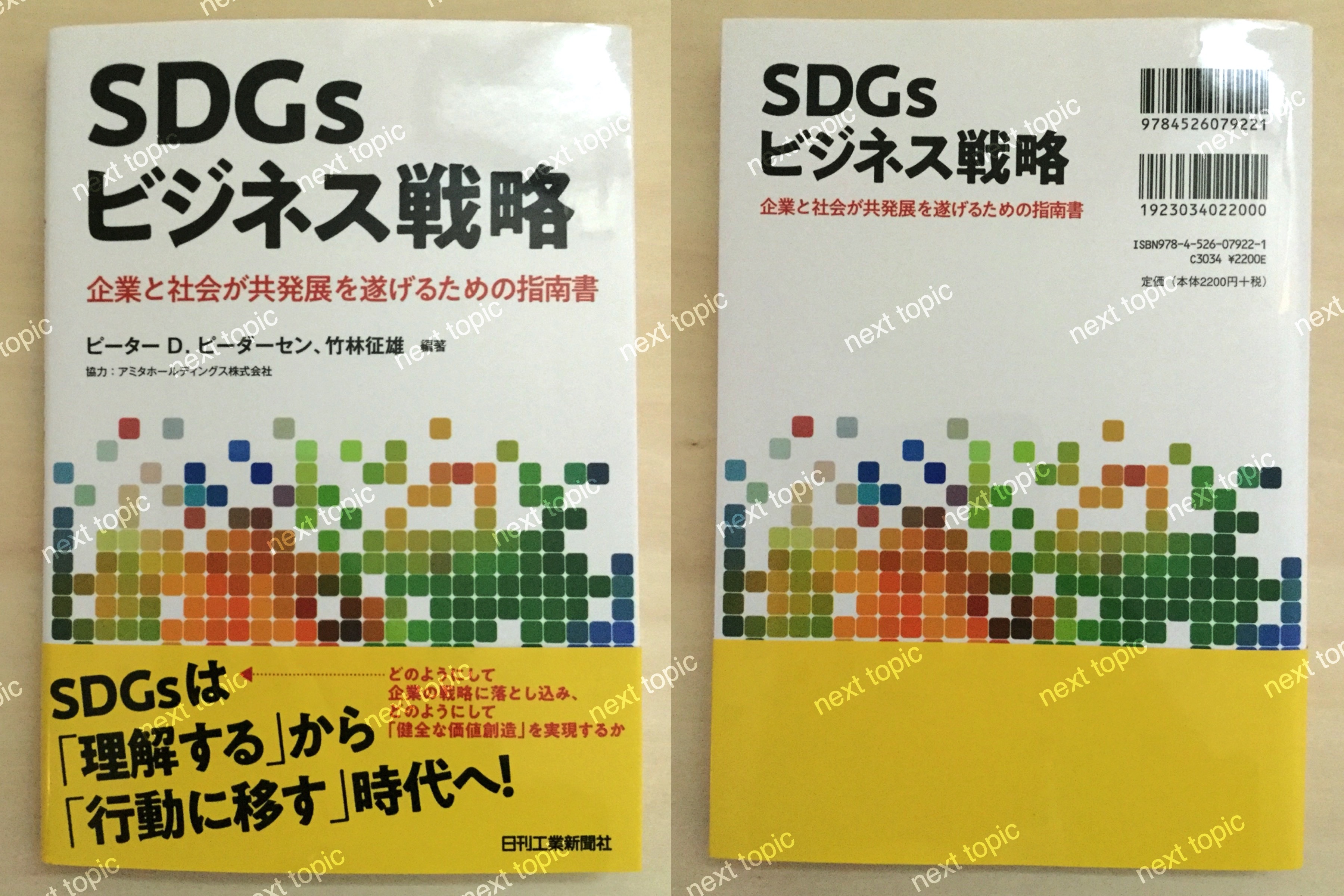ページコンテンツ
【最新 – SDGsを知る・学ぶおすすめ本 – ビジネスマン、学生にも最適!】も確認する
SDGsビジネスがよくわかる
最後まで読むことでSDGsの全体的な理解を深めることができます。読み終わった後は、コラムや対談記事の有識者の鋭い視点を参考に、自分の考えを深めることができます。会社の取り組みがどこまでSDGsなのかチェックできるページもあり、これがとても便利です。

まえがき:本書の使い方
「人間は、自然との闘いに勝ったと思うその瞬間に、自らが負けた側に立っていることに気付くだろう」。このように指摘したのは、異端の経済学者で「スモール・イズ・ビューティフル」を著した、英国のE.F.シューマッハーである。
20世紀後半は、この事実に人類が気づかされたのと同時に、社会面においても貧困を撲滅し、公平で公正な社会を実現しない限り、未来が危うくなることを、強く感じるようになった。
そのため、人類の大きな共同作業として、国際連合を中心に、2000年にMDGs(ミレニアム開発目標—目標年度:2015年)、2015年に、その後継となったSDGs(持続可能な開発目標一目標年度:2030年)が打ち出され、共通の目標と共通言語として、世界を突き動かしている。
本書は、SDGsをどのようにして企業の戦略に落とし込み、「健全な価値創造」を実現できるかに関する多面的かつ実用的な内容を提供すべく、発刊する運びとなった。
2016年いっぱいまで、日本におけるSDGsの認知度はまだ低かったが、2017年から2018年にかけて、理解が急速に広まった。そして2019年以降は、いよいよ行動に移るべき時期が訪れている。その行動において、基礎となる着眼点や哲学と、企業の現場で具体的なアクションを起こすためのヒントとツールが、本書に多数含まれている。
本書は、例えば次のようにご活用いただける。
・最初から最後まで読み、全体的な理解を得る
・SDGsの背景(序章、第1章)、関心の強い個別目標(第3章)、SDGs戦略への落とし込みについて(第2章)、ニーズに合わせて読む
・コラムや対談記事などで、有識者の鋭い視点を参考に、自分の考えを深める。
・戦略に落とし込むための各種フレームワークやツール(第2章)を、社内外の必要な場面で活用する
・具体的な企業事例(第4章)からインスピレーションを得て、次の一手を考える
第2章で紹介する「7つの経営ツール」は、いずれも下記URLから、無料にてダウンロードすることができる。ぜひ、現場を刺激し、企業価値と社会価値が同軸に乗る経営の実現に向け、本書をご活用いただきたい。
「スモール・イズ・ビューティフル」、E.F.シューマッハー、講談社(2010)。原書は、1973年発刊
目次
まえがき:本書の使い方
序章 企業と社会—共存と共発展を模索するその歴史的変遷
株式会社の進化を俯瞰する
株式会社の進化における第一幕:重商主義の時代
株式会社の進化における第二幕:産業資本主義の時代
株式会社の進化における第三幕:持続可能経済の時代
1980年代以降の企業と社会の関係性―3つのステージ
2015年以降にさらに鮮明になった「社会の変革ドライバー」
環境・社会イノベーションは「第5の競争軸」
いまこそ「リフレーミング」が必要
第1章 世界共通言語SDGsとは
はじめに
SDGsに到る系譜
具体的にSDGsとは何か
日本におけるSDGs活動
SDGsの世界的な2つの動向
SDGsとビジネス・企業
SDGsを経営に取り込むにあたり、従来と異なった思考方法が必要である
第2章 SDGs経営実践のための「ツール・ボックス」
共発展のキーワードは「トレード・オン」
SDGs戦略の実践に向けての「基本姿勢」とは
基本姿勢、その1:
CSR的とらえ方から脱却する
基本姿勢、その2:
SDGsを「イノベーション・ドライバー」として活用する
基本姿勢、その3:
パートナーシップと協働の重要性を認識する
SDGs経営—理解のフェーズ
SDGs経営の実力測定
SDGs経営実力測定—6つの側面
SDGs経営—行動のフェーズ
SDGs経営—表現のフェーズ
SDGs経営実践のための「ツール・ボックス」ワーク編
第3章 企業が取り組むべきSDGs
企業活動で特に重要な12の目標
目標2 飢餓をゼロに
国連WFP日本事務所
目標3 すべての人に健康と福祉を
公益財団法人 未来工学研究所 22世紀ライフェンスセンター 主任研究員 小野直哉
目標6 安全な水とトイレを世界中に
グローバルウォーター・ジャパン 代表 吉村和就
目標7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに
日本サステイナブルコミュニティ協会 竹林征雄
目標8 働きがいも経済成長も
合同会社 地球村研究室 代表社員、東北大学名誉教授 石田秀輝
目標9 産業と技術革新の基盤をつくろう
長岡技術科学大学 理事・副学長 三上喜貴
目標11 住み続けられるまちづくりを
関西大学社会連携部・名誉教授、大阪大学名誉教授 盛岡通
目標12 つくる責任 つかう責任
アミタ株式会社 代表取締役 佐藤博之
目標13 気候変動に具体的な対策を
国立環境研究所 増井利彦
目標14 海の豊かさを守ろう
公益財団法人世界自然保護基金ジャパン (WWFジャパン) 自然保護室 山内愛子
目標15 陸の豊かさも守ろう
株式会社レスポンスアビリティ 代表取締役 足立直樹
目標17 パートナーシップで目標を達成しよう
一般財団法人CSOネットワーク 事務局長・理事 黒田かをり
第4章 企業のSDGsの取組事例
SDGsの目的と、達成に向けた2種のアプローチ
アミタホールディングス株式会社
資源インフラで持続可能社会の一翼を担う
株式会社エンビプロ・ホールディングス
「再エネ100%」の住宅・建築・街づくり
大和ハウス工業株式会社
再エネが地球と地域を救う
シン・エナジー株式会社
特別寄稿 ビジネスの世界が担う持続的未来とSDGs
東京都市大学・特別教授 涌井史郎 (雅之)
特別対談 「SDGsと地域循環共生圏」
熊野英介 アミタホールディングス株式会社代表取締役
中井徳太郎 環境省総合環境政策統括官
あとがき
巻末付録 SDGs17目標 169ターゲット一覧
執筆者紹介
序章 企業と社会―共存と共発展を模索するその歴史的変遷
ピーター D. ピーダーセン
株式会社の進化を俯瞰する
1600年12月31日、英国王室の許可を得て、世界で最も有名な貿易会社となった英国東インド会社が株式会社として産声をあげた。そのはるか前の1288年6月、スウェーデン生まれの鉱山企業ストゥーラ・コッパルベリ(文字通り「大銅山」)は、羊皮にて世界最古の「株券」を発行したとされている。また、英国とロシア間(当時モスクワ大公国)の貿易を担ったモスクワ会社も、既に1555年に英国の女王メアリー1世の勅許によって、株式会社として活動を始めていた。
日本においても株式会社ではなかったにせよ、聖徳太子の命によって578年に設立され、現代まで操業を続けてきた金剛組という、世界最古とされる企業が存在している。これらの企業たちの歴史自体も栄枯盛衰の道のりであり、随所にドラマに満ちているが、ここでは、1600年の東インド会社設立を節目として、社会と企業の関係性を大きな歴史的観点から俯瞰してみたい。
このような探求はなぜ意味を成すのかと、読者は思うかもしれない。その答えは、読み続けていただくうちに明らかになるはずだが、まずは結論から述べることにしよう。株式会社に代表される近代的な「企業」は、1600年あたりから現代、いや、未来にいたるまでいくつかの大きな歴史的な進化の段階を経て発展、変貌を続けている。それぞれの時代において、企業が担ってきた役割、鍵となる利害関係者、そして企業の操業原理が大きく変容している。
詳細は後述するとして、我々は現在、その進化の歴史における「第三幕」に突入していると言える。この第三幕において、国連のSDGs(持続可能な開発目標)に代表されるように、企業は社会的課題への革新的かつ主体的な役割が社会から強く期待されている。
それは、ただ単に富を増やすことや、豊かな消費社会を実現するといった意味合いでの「社会課題」ではなく、この地球上での生命維持と、人類の将来的な発展を可能にするにあたって避けて通れない「社会課題」なのである。企業の操業と、社会や自然環境のトレード・オフを乗り越え、その双方が健全に発展できる「トレード・オン」の関係性を築くことが必要不可欠となっている。言い換えれば、「トレード・オン」とは、企業と社会の共発展をも意味し、その共発展を可能にする経営が、実は企業という生き物の進化における「ネクスト・ステージ」である。
この挑戦は壮大なものであると同時に、企業側からみるとその組織の規模、形態、営業内容に関わりなく、非常にエキサイティングな新しいイノベーション・フロンティアとみるべきである。まずは、その背景にある、400年の「進化の物語」を簡単に振り返ってみることにしよう。
株式会社の進化における第一幕:重商主義の時代
1600年の英国東インド会社の設立を受け、欧州各国に東インド会社が次々に設立されたことは、有名すぎる話と言えるだろう。1602年、オランダ東インド会社は、現代語でいうIPO(株式公開)を世界で初めて実現し、株式を市場で、一般の人々も参加できる形で取引する最初の会社となった。そして、英国、スペイン、ポルトガルと常に覇権争いを繰り広げていたオランダのアムステルダムでは、1611年に世界初となる株式取引所が完成した。是初の10年は、たった一社—オランダ東インド会社—の株式の取引のを行う場所として賑わっていた。1600年より少し前から、1800年を少し過ぎるあたりまでの欧州の経済社会は「重商主義」の時代と言われているが、それは一体どんな経済発展のエデルだったのだろうか。世界の多くの地域で植民地をつくり、貿易によって安い原料を調達し、自国で加工し、付加価値をつけて、なるべく他国に金や銀を得るために輸出するといった経済のパラダイムだった。一方、輸入をなるべく制限しようと、高い関税を設けるなどといった保護主義的な政策も特徴の1つだった。
この中で、株式会社に操業許可を与えるキーとなるステークホルダーは、最初は君子、その後は資本を有する貴族を中心とした社会の富裕層であった。資本を集めた株式会社に期待された役割は、きれいごとで言えば探検と貿易、言い換えれば搾取と略奪であった。実際、英国東インド会社は、英国そのものを超える規模の軍隊を有し、インドや香港などの植民地化を主導する存在だった。CSR(企業の社会的責任)とはほど遠い、かなり恐ろしい企業像といっても過言ではなかろう。操業原理は、安く原料を調達できるアフリカやアジア諸国などの征服・制圧と、最大限可能な形での人と自然界の搾取だったと言える。そのいかがわしい基礎の上に、産業革命以前の英国など、欧州各国の富と権力が築かれていった。
株式会社の進化における第二幕:産業資本主義の時代
重商主義が経済発展のパラダイムとして徐々に力をなくしていった歴史をひも解くのは、本書の範疇を超えるため割愛するが、18世紀後半の蒸気機関の発明と普及によって、新しい経済社会が姿を現し始めたことは、周知の事実である。1700年代の終盤から、産業革命が(東インド会社と同じく)英国から広まっていくにつれ、経済発展のパラダイムも、次第に産業資本主義へと転換したのである。大英帝国の広大な植民地から得た富がその原動力になったことは否めないが、企業としての主役は「貿易会社」から、産業化の牽引役となった「製造会社」へと次第に移行していった。
農業や職人業から、高度に機械化された産業経済へと社会構造そのものも大きな転換期を迎えた。蒸気機関の機織り機を導入することで、綿紡績(綿の原料を糸として紡いでいく工程)の一人の労働者の生産性は、約500倍になったと言われている。つまり、一人の労働者は、機械の力を借りて、それまで500人が必要だった仕事をこなすことが可能となった。まさに革命的なスケールとスピードの変化だった。
この時代における株式会社のキーとなるステークホルダーは、土地、製造設備、労働力の確保に資金を投じた資本家となった。そして、企業に期待された役割は、一言で言えば、「豊かな消費社会の実現」だったのではないだろうか。操業原理はと言えば、生産の機械化と労働者の最大限可能な搾取によって、生産量の拡大を図るといったところになろう。
21世紀初頭においてもなお、私たちはこの産業資本主義の延長線上に生きていると言える。水力・蒸気機関、電気、ITによるこれまでの3つの革命を経て、現在はAI、ロボティクス、3Dプリンティングなどがもたらす「第4の産業革命」が進行中と言われている。しかし、世界全体を見渡すと、産業化による経済の発展モデルから抜け出しているとは言えない。
産業資本主義が大きな成功をおさめ、農業の工業化をも後押しし、20世紀は莫大な人口増加が起きた。1900年に、人類誕生からの二百数十万年で15億人にまで増えたヒトの頭数は、その後、たった100年でその4倍強の61.3億人にまで急増した(2000年)。そして、現在も一日約210,000人の純増が続いている。皮肉なことに、私たちは種として成功し過ぎたとさえ言えるのかもしれない。20世紀後半、人類は、産業資本主義の目覚ましい発展の予期せぬ副産物に直面することになる。日本の水俣病に代表される公害問題公害問題、1980年代にクローズアップされ始めた地球温暖化、1990年代から特に注目される生態系の劣化、サプライチェーンにおける児童労働など、新たな社会課題と環境問題が多発するようになった。200年続いた産業資本主義の発展パラダイムが、人口密度が急激に上昇した地球社会において通用しなくなっていることは、20世紀後半に進むにつれて鮮明になっていった。そして、その経済の牽引役を務めてきた企業も当然、役割が本質的に問われ始めた。企業の存在意義、これから取り組むべき社会課題、そして、誰が企業にとっての重要なステークホルダーなのか、そのすべてが総点検の時期に差し掛かっている。
株式会社の進化における第三幕:持続可能経済の時代
環境経営、CSR経営、サステナビリティ経営、CSV、ESG、そして本書のテーマであるSDGs(国連の持続可能な開発目標)——これらは特に1980年代以降に台頭した新しい概念であるが、その背景にはこれまでの経済発展モデルの機能不全が潜んでいる。人口密度の高い地球社会において、どのようにして人類の生命を支えられる地球環境と健全な社会とを維持しつつ、必要不可欠である経済力を発揮するか——いまは、その大いなる「問い直しの
時代」に入ったと言ってよいだろう。
筆者は、この一連の動きが企業と社会の関係性における「第三幕の幕開け」に匹敵する出来事であるとみている。小手先では答えが出ない、壮大かつ創造的なトランスフォメーション(変容)の真っただ中に企業が置かれていると考えるべきだろう。株式会社は、ここではその代表格として取り上げているが、地域企業、ベンチャー、中小企業にも、この大転換の一旦を担う責任と可能性があると考える。
第三幕の「何が違うか」を理解するために、一旦、日本における産業社会の代表的な一社、松下電器産業(現パナソニック)に思いを馳せてみよう。1932年、創業者松下幸之助は大阪のある会合で、後に「水道哲学」と称されるようになった自分なりの経営哲学を語った。
「産業人の使命は貧乏の克服である。その為には、物資の生産に次ぐ生産を以って、富を増大しなければならない。水道の水は価有る物であるが、乞食が公園の水道水を飲んでも誰にも咎められない。それは量が「多く、価格が余りにも安いからである。産業人の使命も、水道の水の如く、物資を無尽蔵にたらしめ、無代に等しい価格で提供する事にある。それによって、人生に幸福を齎し、この世に極楽楽土を建設する事が出「来るのである。松下電器の真使命も亦その点に在る。」!
産業資本主義そのものの「使命」を的確に表現していると同時に、当時の社会課題=貧乏の克服と消費社会の実現に焦点を当てた、名演説である。しかし、21世紀半ばに向かおうとしている今日においても、果たして通用するアプローチなのだろうか。廉価な工業製品を地球すべての人々に提供しようとするなら、それはエネルギー、気候変動、資源枯渇などといった制約条件からみると、破綻の道になりかねないのである。この世に極楽楽土を実現「するどころか、将来世代にとっては地獄への入口にすらなるかもしれない。「水道哲学は、1930年代には素晴らしく適していたと言えるし、いまなお、地球社会全体では安全な水(21億人)や電気(10億人)にアクセスできない人々が多数暮らしていることも事実である。しかし、産業資本主義の経済発展モデルやこの時代の企業経営の操業原理では、問題解決ができないだけでなく、むしろ悪化させかねない。言ってみれば、水道哲学には新しい前提条件が必要となっている。それこそが、本書の主たるテーマである「長期にわたる自然環境と社会の持続可能性=サステナビリティ」と言える。
企業の歴史は、社会との新しい関係性と共発展の在り方を模索する「第三幕」に突入している。その台本の新しい展開を「脅威」とみるか、それとも「機会」と捉えるかは、企業人の世界観と力量にかかっているが、一企業が仮にその動きに抵抗しようとしても、それは無駄な努力にしかならない。歴史の新たな波に乗るか、それとも過去の遺物として、いずれ姿を消すかがわれているのだ。未来を選択する時代と言い換えてもよいだろう。
第三幕において問われていることは、「誰が企業の本当に大切な利害関係者なのか、「企業は何の役割を社会において担えばよいか」、そして、地球上で生命維持が可能となるための「企業の新たな操業原理とは、一体どんなものなのか」といった、非常に根本的なものである。現在も続いているその「問い直し」がどのように進んできたかをもう少し具体的に理解し、SDGsとの接点を明らかにするためにも、次に、400年の歴史の俯瞰から、ここ三十数年の変化にズームインしてみることにしよう。
1980年代以降の企業と社会の関係性—3つのステージ
20世紀後半に、特に公害や地球環境問題が次第にクローズアップされるようになるにつれ、社会が企業に求めることも顕著に変わり始めた。個人的には、1980年代以降のその変化を、3つのステージに分けて捉えている。この3つのステージを体系的に理解することで、ここ30年強の環境・CSR・サステナビリティ経営の進化を的確に押さえ、今後にも続く企業経営の潮流を読むことができると考えている。
第一ステージ 1980年代後半まで:【法順守、リスク管理、メセナ活動の時代】
1980年代後半まで、企業は法律を守り、適切なリスク管理を行い、若干のメセナ活動を実施していれば、「よき企業市民」としてステークホルダーに認められる時代が長く続いていた。ビジネスと社会の関係性は比較的わかりやすく、経営側にとっても取るべく対応が明確だったと言える。
興味深いことに、この第一のステージが大きく変わるきっかけとなった年を正確に特定することが可能なのだ。1987年が、その節目の一年となった。3年間の委員会活動を終えた国連の「環境と開発に関する世界委員会」(通称:ブルントラント委員会)は、1987年に報告書「我ら共有の未来』のなかで、初めて国際的に「持続可能な発展」の概念を打ち出した。それ以降の企業経営や国家運営などに、これほど大きな影響を及ぼすコンセプトはなかったのではないかと思うほどのインパクトをもたらしている。
わかりやすく言い換えれば、現代においてもまだまだ貧しい人たちがたくさん存在し、彼らのニーズを満たすための経済や社会の発展は必要だが、その「やり方」を改めないと、将来世代の可能性を奪いかねないということになる。特に、「いま生きている私たちに、世代を超えた責任がある」ということが、この定義の1つの大きな特徴と言える。
持続可能な発展の概念は、1992年6月、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催された「地球サミット」(正式名:「環境と開発に関する国連会議」)へとつながり、この国際会議のバックボーンを成す考え方となった。その少し前から、産業界は既に新たな時代の到来を予感し、自ら経営を次のステージに転換し始めていた。
第二ステージ 1990年代~2005年頃:【積極管理、情報開示、CSR経営の時代】
地球サミットの約3か月前の1992年3月、英国のBSI(英国規格協会)は世界で初めての本格的な環境マネジメント規格を公表した。企業が法を超えて、積極的に環境課題を管理するというそのアプローチは、最終的に1996年から取得が可能となったISO14001へと統合されるに至っているが、この動きのなかに第二ステージの特徴の1つが見え隠れする。企業は、「法律に縛られるより自主的な対応を」という精神に基づき、環境や、後には社会的な課題もプロアクティブに、言い換えれば「積極的に」管理するようになった。
1990年代半ばになると、環境報告書、そのあとCSRやサステナビリティ報告書が世界各国で発行され始める。積極管理が社会から求められたのに加え、法を超えた情報開示や幅広い説明責任もステークホルダーから当然視されるようになっていく時代である。
個人的にも接点を持たせていただいた経営者、今は亡き米国のカーペットメーカー、インターフェース社のレイ・アンダーソン会長の経験が、第一ステージから第二ステージへの移行を分かりやすく表している。アンダーソン会長には、自らが1970年代に創業者したカーペットメーカーが、環境関連法を順守し、納税も適切に行っていたため、優良な企業市民であるとの自負があった。しかし、1994年に、ある大手顧客から「御社の環境ビジョンを教えてください」と問われると、一種のショックを受けたという。自分たちには環境ビジョンに該当するものがなく、それまで必要とも思っていなかったそうだ。しかし、いざ世界の現状を見渡し、さまざまな有識者の本を読み始めると、企業が自ら、積極的に持続可能な未来を築く重要性を深く認識し、同社は、「2020年までに世界初の持続可能なメーカーになる」という長期ビジョンを掲げ、経営を抜本的に変え始めた。目標年度がだいぶ近づいて「きたが、その挑戦はいまも一貫して続けている。
ここまでドラスチックに舵を切った従来型の企業は少ないが、1990年代は間違いなく持続可能な発展の概念を出発点として、企業経営の在り方や、社会との接し方が大きく進化する10年となった。積極管理、情報開示や説明責任を中心とする「CSR経営」のステージである。
第三ステージ:2005年頃から:【課題解決型の革新、ステークホルダーとの共創】
現在もCSR経営を、第二のステージの特徴を中心に、粛々と続けている企業は少なくない。しかし、社会を代弁するステークホルダーから、「それではもはや不十分」だという、発展的な挑戦状を突き付けられている次なるステージは、既に2005年頃始まっている。そして、この第三ステージの集大成の1つが、2015年9月に採択されたSDGsと言っても過言ではなかろう。第二から第三ステージの間に何が変わったのか、そして、いま企業に求められる新たな経営スキルとはどのようなものなのか。
地球社会が直面している環境・社会課題は、国家、国際機関、NGOだけではどうにも解決できない。グローバル資本主義の広まりとともに、強大な力を手に入れた企業の主体的な行動なくして、人類は持続可能な未来を迎えることができない——そんな認識がミレニアム前後に強まり、第三ステージへとつながっている。
いまの時代において「よき企業市民」と認めてもらうためには、第一や第二ステージの経営スキルに加え、一歩進んだかたちで、環境・社会課題を解決するためのイノベーションが求められている。そのイノベーションを、自社の研究開発や事業部門だけで実現できないことも多いため、社会の広い層のステークホルダーとの真剣な共創が必要であるとされている。NGOに寄付するといった社会貢献というよりは(あるいは、それに限定せず)、国際機関、NGO、地域社会、投資機関などと知恵を出し合い、課題への新しい解を協働によって生み出すことが求められている。
なぜ、この第三ステージが2005年頃始まったと言えるか。第一から第二ステージのように、正確に年号を特定することはできないが、2005~2006年あたりは、企業のCSR・サステナビリティ経営に決定的に重要な変化がいくつも起きている。
現在のESG投資(環境=E、社会=S、ガバナンス=G)の流れを生んだ国連の責任投資原則PRIが制定されたのは2006年だが、その前年に、食品世界最大手ネスレは、マイケル・ポーターが提唱するCSV経営(CSV=共通価値の創造)を大々的に掲げ始めた。同年、世界最大手のスーパーマーケット、ウォルマートの経営者は、ハリケーン、カトリーナの破壊力を目の
当りにし、それまで考えらないほど積極的な3つの環境目標を世に打ち出した。同じく2005年秋に、米国を代表するコングロマリット、GEは、エネルギー効率や再生可能エネルギーの商品群を増やす経営戦略「エコマジネーション」を始動させ、一気に環境先進企業へと舵を切り始めた。どれも、自社の事業を通じて、課題解決型のイノベーションを強力に進めるといったメッセージを、産業界全体に送る出来事であった。
第三ステージは、現在も進行中である。持続可能な地球社会を実現することが、史上最大級のビジネスチャンスでもあると、多くの企業が目覚めているかのようにみえる。これは大いに歓迎すべきことだと思うが、この「目覚め」は常に社会とのキャッチボールの中で起きていることを忘れてはならい。そのキャッチボールは、特に2015年頃を境目に、さらに活発に行われるようになっている。社会の変革ドライバーが、企業にさらなる脱皮脱皮とイノベーションの加速を促していると言い換えることもできよう。
2015年以降にさらに鮮明になった「社会の変革ドライバー」
2015年9月の国連総会にて、SDGsが採択された。正確に言えば、採択されたのは「持続可能な開発のための2030アジェンダ」だったが、その「アジェンダ=議題」は、まさに、世界が共通して取り組む17の持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)に集約されている。
SDGSが採択されたわずか3か月後、フランスの首都パリでは、大方の予想を覆して、「パリ協定」が満場一致で採択された。人類活動の脱炭素化に向けた道筋を示すパリ協定の詳細は割愛するが、企業にさらなる課題解決型イノベーションとステークホルダーとの共創を求めている強力な要因であることは、言うまでもなかろう。
ESG投資が2010年代半ばを経て、もはや完全に主流化しつつあるのも見落とせない変革ドライバーだ。ハーバードビジネスレビューが毎年公表している「最もパフォーマンスの高いCEOランキング」(Best Performing CEOs in the World)には、2015年秋、初めてESG的な評価項目も採用され、収益力だけでなく、社会的対応能力で経営者を評価する試みを開始した。その結果、それまで1位の座にあったアマゾンの創業者、ジェフ・ベゾス氏は、一気に87位に転落した。
世界最大の年金基金である日本のGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)も、同じく2015年に上で触れた国連の責任投資原則PRIに署名し、そして、2017年7月には、資産運用において3つのESG指標を採用すると発表した。ESG投資——つまり、環境、社会、ガバナンスの観点から投資銘柄を選定する資産運用——は2019年現在、世界の全運用資産の3割弱に達しており、欧州など一部の市場では既に50%超の割合となっている。
最後に触れるべき変革ドライバーは、顧客の価値観の変化である。B2CとB2Bの世界では異なる形で体現されるが、いずれの市場においても顧客は環境と社会的配慮を以前よりはるかに求めるようになっている。B2Cでは、1981年以降に生まれたミレニアル世代後の生活者がサステナビリティを志向した消費に意欲を示している。B2Bの世界においては、多くの場合は取引条件の中に盛り込まれ、商売を行う上での基礎的な条件にまでなっている。
このように、2010年以降だけをとっても、SDGs、パリ協定、ESG投資、そして顧客の価値観の変化が大きな影響力を及ぼすようになっている。これらの動きは、いずれも「長期ベクトル」に基づいていることが重要なポイントだ。3年や5年で消える変革ドライバーではないのだ。むしろ、2030年や2050年にむけた企業経営そのものの変容が余儀なくされているとみるべき大潮流である。そう簡単にぶれない長期ベクトルが社会によって設定されていることをポジティブに受け止め、自社としての本質的な戦略刷新や事業革新に結び付けて初めて、21世紀半ばの市場にふさわしい企業力や競争力を獲得することが可能となる。
環境・社会イノベーションは「第5の競争軸」
企業は、常に競争にさらされる存在である。そして、時代とともに、競争力を左右する「軸」が変化するのも事実である。戦後、日本が焼け野原から立ち上がり、大きな自己変革力をもとに、最初は価格で勝負し、その後、世界市場に出てマーケットシェアを獲得し、そして、1960年代になると、次第に品質経営で世界における確固たる地位を確立していった。この4つの要因——「ビジネスモデルを進化しつづける自己変革力」、「マーケットシェア」、「値付け」、そして「プロセスと製品の品質」——は、まさに20世紀後半まで、決定的に重要だった「競争軸」と言える。つまり、それらをマスターするか否かが企業の生存可能性に直接影響を与えていた。
これら4つの競争軸は現在も大きな意味をもっているが、昨今は、SDGsを筆頭とする社会の「変革ドライバー」を受け、第5の競争軸が台頭している。その第5の競争軸を一言で表現すれば「サステナビリティ・イノベーション」になろう。つまり、自社の特性や強みを生かしたかたちで、いかにして持続可能な社会や持続可能な未来の実現に貢献するかが、競争力を左右する時代に入ったという見方である。念のために確認したいが、その「貢献」とは「社会貢献」とイコールでもなければ、「社会貢献」を軽視しているものでもない。事業においては事業そのものを通じて、オペレーションにおいてはその特性や課題をふまえ、そして必要な時には社会貢献をも通じて、主体的かつ新たな価値創出につながる行動が求められていることに他ならない。
いまこそ「リフレーミング」が必要
本章では、最初に企業と社会の関係性を400年の大きな歴史的な観点から捉え、その後、ここ30年強を3つのステージに分けてみてきた。企業が、誰によって操業・発展の許可を獲得し、何を社会に提供する存在であるかの非常にエキサイティングかつ創造的な「問い直しの時代」と捉えている。このような時代において、旧態依然のマインドセットや物事の解釈では、当然、求められる新しい解はみえてこない。
米国の言語学者、カリフォルニア大学教授のジョージ・ラコフ氏はかつて、Reframing is social changeという名言を発したが、彼が指摘しているのは、メンタルモデルやマインドセットを抜本的に変えた瞬間に(すなわちリフレーミングが起きたその時から)変化・変革・イノベーションへの扉が開くということである。SDGsをはじめとした社会の変革ドライバーを的確に理解し、イノベーションに結び付けるためには、次ページの図が示すようなリフレーミングが必須となろう。リフレーミングができなければ、第三のステージで求められる「課題解決型イノベーション」を起こすための意思思定や、社内プレイヤーのベクトル合わせは困難を極めるだろう。ここで、いまなお喘いでいる企業も少なくないのではないだろうか。近年、日本において「CSR部」から「サステナビリティ部」への衣替えが続いていることは、リフレーミングの一環とみることができるが、当然、その取組内容のアップグレードもセットで必要になる。
本書の目的は、SDGsと企業の経営・事業戦略の接点を探るところにある。これまでのCSR経営は、ややもすると企業価値の創出に直結していなかった、あるいはその関係性がみえていなかった。SDGsは企業価値創出へのリンクを強める1つの好材料とみることができる。社会と共発展できる企業こそ、ステーホルダーから積極的かつ優先的に選ばれ、長期にわたる発展・成長の許可を手に入れる——そんな時代に、私たちは一歩ずつ、紆余曲折の道を経ながら進んでいるのである。