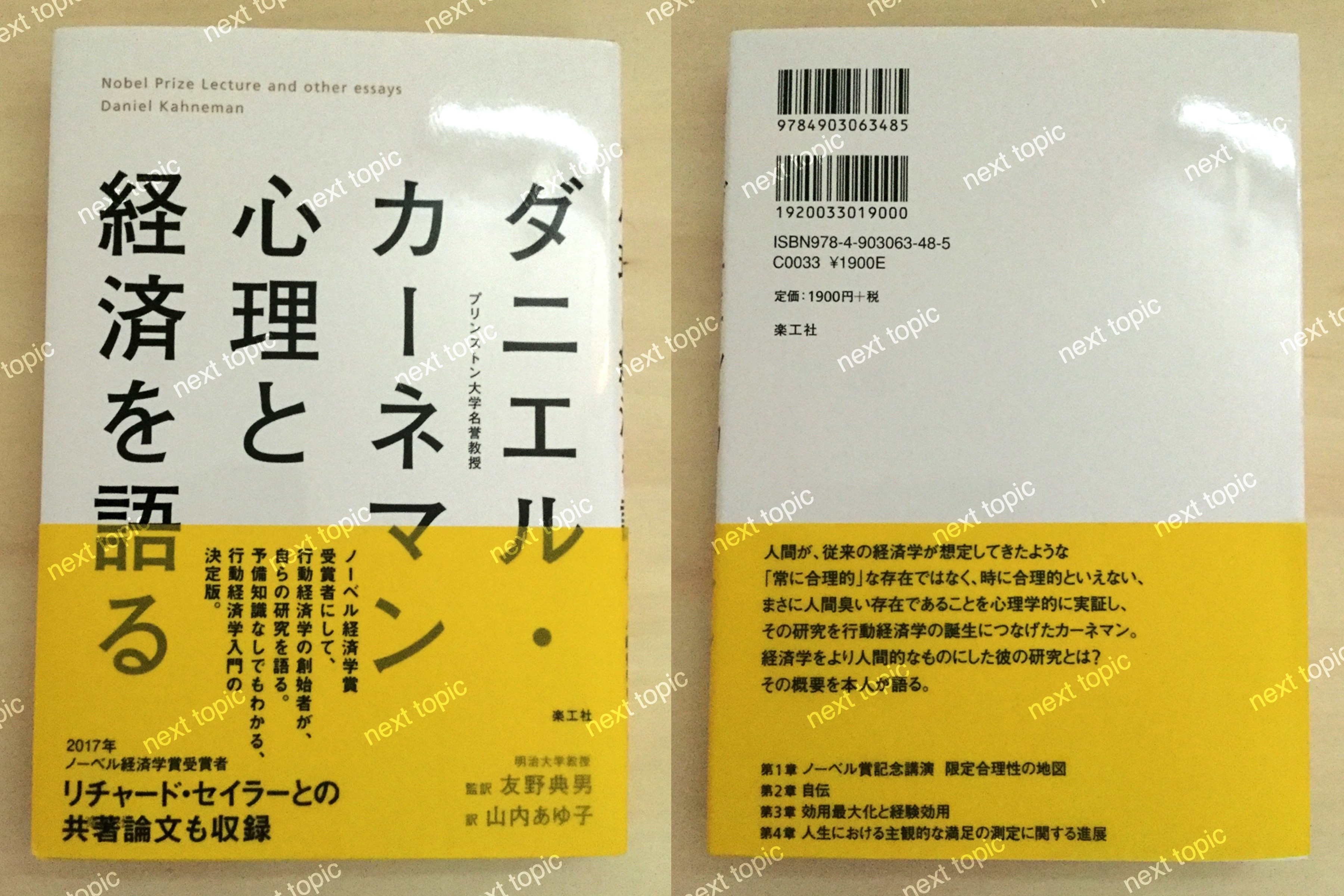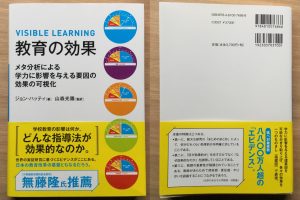ページコンテンツ
カーネマンまるごと1冊
本書は、ダニエル・カーネマンのノーベル賞受賞記念講演、ノーベル賞受賞時に発表された自伝、カーネマンの行動経済学に関する論文のうち、一般読者にも分 かりやすいもの二本を訳出して一冊の本として編集したものになります。心理学者でありノーベル賞経済学をとったカーネマンの考え方が理解できます。

監訳者解説 – 友野典男
本書は、ダニエル・カーネマンの、ノーベル賞受賞記念講演(第1章)、ノーベル賞受賞時に発表された自伝(第2章)、カーネマンの行動経済学に関する論文のうち、一般読者にも分 かりやすいもの二本(第3、4章)を訳出して一冊の本として編集したものである。
なぜ本書を編んだのか。今、行動経済学が流行しつつあり、多くの本が出版されている。しかし行動経済学の創設者の一人であるカーネマンは(彼の共同研究者であり、行動経済学の立 役者の一人でもあるエイモス・トヴェルスキーもそうであるが)、一般向けの書物を著わしておらず、名前が知られている割には、彼の主張や論文の実際の内容について知る機会は少ないと思われるからである。それともう一つ、「行動経済学」=「人間の非合理性」という誤った理解が蔓延しているように見え、専門家を自認する人の本にさえ、そう断定してしまう間違った記述が見られるという状況がある。本書は、カーネマンの著作を通じてそのような誤解を解 き、行動経済学をさらに正しく深く理解してほしいという意図のもとに企画された。
ご存じのようにカーネマンは二〇〇二年に、アルフレッド・ノーベル記念スウェーデン国立銀行経済学賞(ノーベル経済学賞)を受賞した。カーネマンに対する授賞の理由は、「心理学 研究の洞察、特に不確実性下の人間の判断と意思決定に関する研究を、経済学に統合したこと」であり、行動経済学の基礎を固めたという点が評価されたのである。同時受賞したのが、当時ジョージ・メイソン大学(現チャップマン大学)教授のヴァーノン・K・スミスであった。スミスの受賞理由は、「実証経済分析のツールとして実験室実験を確立したこと、特に代替的な市場メカニズムの研究」であった。スミスの受賞理由ともなった経済学の実験的方法は行動経済学にも大きな影響を及ぼしているから、同年のノーベル経済学賞は、行動経済学の研究者 には強力な追い風となったのであり、この後行動経済学の研究はアメリカだけでなく、ヨーロッパや日本においても急速に展開されていくことになる。
余談になるが、カーネマンは、ノーベル「経済学」賞を受賞したが、自伝中で述べているように、経済学の授業を一度も受けたことがない。おそらく正式の経済学教育を受けていない初めてのノーベル経済学賞受賞者ではないだろうか。また彼は、ノーベル経済学賞は毎年二~三人貰うが、全米心理学会賞は年一人だから、そちらの方が貰うのは難しいという感想も述べている。
カーネマンが自伝中で繰り返し述べているように、トヴェルスキーとの偶然の出会い、そして長年に渡る共同研究がなければ、カーネマンの現在のような研究もあり得なかったであろう。トヴェルスキーは一九九六年に病気で死去したが、生きていればノーベル経済学賞を共同受賞したのは間違いない。またそうであれば、カーネマンの受賞の喜びもさらに深くなっていたであろう。
ちなみに、心理学者でノーベル経済学賞受賞者はカーネマンが最初ではなく、三〇年も前の 一九七八年に、当時カーネギー・メロン大学でまさに学際的研究に邁進していた心理学者のハーバート・H・サイモン(二〇〇一年没)が受賞している。現在の行動経済学でしばしば使われる言葉である「限定合理性」という概念を編み出したのが、サイモンである。しかしサイモンの業績は経済学界で言及されることは少なく、長い間忘れられたも同然であった。それを復活させ再び光を当てたのもカーネマンの功績であるということができる。
カーネマンの行動経済学関連の業績をまとめれば、大きく三つになる。一番目は、「ヒューリスティクとバイアス」研究である。本書第1章で詳しく述べられているように、人が判断をするときには、ヒューリスティクスという直感的判断を多用する。ヒューリスティクスは簡便であって素早く結論を出すことができるが、バイアスや間違いを生む原 因にもなることを、カーネマン はさまざまな実験で明らかにした。
二番目は、「プロスペクト理論」に関連するものである。第1章のノーベル賞記念講演で詳しく述べられており、第2章の自伝でも触れられている。人の判断は知覚に似ており、変化に は敏感に反応するが、同じ状態が続くと反応しない。経済学で言えば、効用(満足度)は最終 的な富の状態によって感じられるのではなく、参照点といわれる何らかの基準との違いやそこ からの変化に対して感じられるのである。つまり、基準に比べてより良くなったとかより悪く なったということが効用(満足度)をもたらす。これが行動経済学の意思決定理論であるプロスペクト理論の出発点である。
三番目は、「効用概念の再検討と幸福」である。これらは第3章と第4章で論じられる。幸 福とか人生の満足ということは、哲学や倫理学のテーマになることは多いが、経済学では長い 間忘れられていた話題である。この問題に光を当てることができるのが、幸福と生活上の満足というテーマであり、これは現在カーネマンが最も精力的に取り組んでいるテーマである。
このようにカーネマンの仕事は、行動経済学のほぼ全領域をカバーする幅広いものであるが、行動経済学の主要テーマに含まれる「社会的選好(人は自分自身の利益だけでなく、他者の利 益にも配慮して意思決定を行なうという性質)」と「時間選好(人は、現在を重視して、将来 を軽く見るという性質)」に関してはほとんど著作を発表していない。単なる憶測に留まるが、 たまたまそれらに関する論文を書くことがなかっただけであって、これらを軽視しているというわけではないことは、「自伝」からも窺える。
カーネマンの自伝(本書第2章)には、共同研究者あるいは論文の共著者として行動経済学の錚々たる人物の名前が挙がっている。シカゴ大学教授のリチャード・セイラーはカーネマン やトヴェルスキーと共に行動経済学者の創始者として名前が挙げられる立役者である。セイラーは、自伝中にはやんちゃながら洞察に溢れた若い研究者として描かれており、本書第3章の共著者でもある。セイラーは、イギリスのキャメロン政権の政策策定にも影響を及ぼしている。また、カーネマンの論文の共著者として名前が挙がっているシカゴ大学教授キャス・サンスティーンは、憲法が専門の気鋭の法律学者・法哲学者であり、行動経済学の法律への適用を目指す「法と行動経済学」という分野のパイオニアの一人である。現在はハーバード大学ロースクール教授に転じ、また政府の要職も兼務しており、オバマ政権の政策決定に少なからぬ影響力を持つ人物である。行動経済学の考え方が英米の政策当局から強く支持されていて、活用されつつあるのがわかる。
行動経済学の価値は、政策に応用されて有意義な結果をもたらしたときに初めてわかると言われることがあるが、その意味で、これからが行動経済学の真価が問われるときである。その出発点であるカーネマンの著作の一端を紹介することに本書の意義がある。
各章の内容について簡単に紹介しておこう。
第1章「限定合理性の地図」はノーベル賞受賞講演である。この講演内容をさらに詳細にした論文が、同名で『アメリカン・エコノミック・レビュー』誌に掲載されている。本章の内容 はノーベル賞の受賞理由となったトヴェルスキーとの共同研究、つまり不確実な状況で人がどのようにして判断し決定をするのかについて扱ったものであり、具体的な実験例を交えて、簡 潔に説明している。内容は少し高度に見えるが、図表を多用してわかりやすくなるように工夫されている。
内容は、意思決定を研究するための出発点となったアイディア、つまり視覚を主とする知覚と判断の類似性に着目した研究方法の紹介である。錯視(目の錯覚)という現象については、ご存知の方も多いだろう。パッと見て長さを判断すると、実は同じ長さであるのに、長さが違うように見えるというようなものである。判断も直感的に行なうとこれと同様な「認知的錯 覚」に陥ることが多いのである。人は何かを判断する時に、絶対値ではなく比較あるいは変化 で判断する。経済学の用語で言えば、効用は「富」の絶対量ではなく、参照点からの移動や変化で決定されるというプロスペクト理論の中心的考え方が、知覚の例を交えて語られる。
第2章「自伝」は、ノーベル賞を受賞した際に発表されたもので、カーネマンが自身の生い立ちや学問的関心の展開、そしてトヴェルスキーとの出会いから共同研究の様子などを生き生きと描写している。全体を通じて、カーネマンのトヴェルスキーに対する愛情が溢れ、早世の 友を惜しむ無念の気持ちが滲み出ている。
人間の判断や意思決定の特徴や行動経済学の考え方、さらに自らの学問に対する態度について述べた点も多く、学術論文を読むのでは得られない洞察や思想が語られていて貴重である。
特に、一○六頁の「われわれの研究が人間の非合理を実証するものだと言われたら、今なら即座にはねつけることができます」という部分は感銘深い。前述のように、行動経済学によって 人間の非合理性が示されたとか、人間の意思決定は基本的に非合理的であるという間違った印 象が広まっている感があるが、そのような誤解を一蹴してくれる一文である。
また、カーネマンとトヴェルスキーの主張を誤解ないし曲解した反論にも反批判をしないことにしたという方針も興味深い。「止むに止まれぬ思いで、一つだけ例外を作」ったとあるが、これはドイツの心理学者ゲルト・ギゲレンツァとそのグループに対するものであり、彼らのカーネマンらに対する批判が熾烈でかつ当を得たものとは言い難かったからであろう。
第3章「効用最大化と経験効用」は、行動経済学の創設者の一人であるシカゴ大学のリチャード・セイラーとの共著論文であり、『ジャーナル・オブ・エコノミック・パースペクティブ ズ』の連載コラム「アノマリー」の一本として発表されたものである。同誌はアメリカ経済学会発行の学術誌でありながら、専門に深入りすることなく、経済学に関心を持つ広い読者層を対象にした雑誌であり、この論文も、経済学に関心を抱く一般の人にも十分読んで頂けるものである。
標準的な経済学では、意思決定主体は自分の確固とした選好を持っており、それに基づいて効用を最大化するような選択肢を選択することが前提とされている。カーネマンとセイラーは、このような標準的経済学の前提を覆すさまざまな実験例を用いて、効用概念の再検討と安定的 な選好という考え方に再考を迫っている。
この論文で彼らは、経済学で通常用いられている効用という概念は二つの意味を持っており、それらを区別する必要があるというところから出発する。一つはジェレミー・ベンサムに発し、ジョン・スチュアート・ミルからフランシス・エッジワースへと続く功利主義的効用概念であり、「経験効用」と呼ばれる。もう一つは「決定効用」と呼ばれ、現代の標準的経済学が採用している考え方であり、人々が行なった選択の結果から推論されるものである。
本章の論文でカーネマンとセイラーは、人がいったい経験効用を最大化することができるのかという疑問を呈し、人は自分の好み(選好)を意外なほどわかっていないし、将来自分が何 を好むかの予想にも失敗するという、衝撃的で興味深い結論を、彼ら自身や他の研究者の面白い実証結果を引用しながら示している。
第4章「主観的な満足の測定に関する進展」は、やはり『ジャーナル・オブ・エコノミック・パースペクティブズ』に発表された論文で、プリンストン大学教授アラン・B・クルーガーとの共著である。
幸福とか生活上の満足といった数値をどのように測定するかについての論文であり、著者らはU指数という新しい指標を提案する。これは、一種の「経済的な不快指数」であり、「人が好ましくない状態で過ごす時間の割合を測定する」ものであって、対象者の自己申告によって測定される。この値が小さい方が満足度は高いと見なせるわけである。彼らの調査によってわかったことの一つは、消費ではなく社会的接触、つまり他者との触れ合い時間が長いほどU指 数は小さいということである。このような、人生におけるあるいは生活上の満足や幸福の測定 法が確定すれば、個人所得やGNP、GDPなどに代わる幸福指標として、福祉政策を初めと する経済・社会政策や人生設計においても役立つことになる。
主に第4章に関連する訳語上の問題について一つだけお断りしておく。この論文でもそうだ が、他の経済学や心理学の文献に関しても、”well-being” と “happiness” の訳し分けについて悩むことが多い。happinessについては「幸福」や「幸せ」で問題無いが、困るのは well-being の方である。文字どおり解釈すれば「善く生きること」であるから、「善生」と訳してあるのを見かけたことがあるが、どうもしっくりこない。そこで、本書では単に、「満足」と訳すことにした。妙訳をご存じの方がいらっしゃったら、ぜひご教示をお願いする次第である。
続いて、本書ではほとんど触れられなかったカーネマンの研究テーマについて触れるとともに、本書収録の論文は最も新しいものでも二〇〇六年の出版であるので、その後のカーネマンの研究や考え方について、簡単に紹介しておこう。
まず本書ではほとんど触れられていないが、最近注目を集めている「神経経済学」(ニュー ロエコノミクス)についてカーネマンはどう考えているのであろうか。神経経済学とは、脳科 学と経済学が融合した、まったく新しい学問であり、脳の活動を測定することで、行動の結果だけを見たのではわからない意思決定の側面を脳にアプローチすることで理解しようとする。たとえば、二つの選択肢の一つが選ばれた時、それを選んだのが理性的な判断によるものか、あるいは感情的に選んだのかは、選択の結果だけを外から見たのではまったくわからない。しかし選択の過程において脳のどの部位が活性化するのかを測定すれば、どちらの理由であったのかが判明するのであり、こうしたことから神経経済学は、選択や意思決定に関して新しい知 見が得られる可能性が大きいと期待される学問である。
カーネマンは、二〇〇一年に「金銭的利得と損失の予測と経験に関する神経反応の機能的画像測定」という論文を脳科学者であるハンス・ブライターらと共著で『ニューロン』誌に発表している。この論文はタイトル通り、人が利得と損失を経験した場合と予測する場合に、脳のどの部位が活性化するのかを、fMRI(機能的磁気共鳴画像法)を用いて測定している。その結果、利得と損失では活性化の程度や部位が異なること、実際に報酬が得られた場合だけ でなく、報酬の予測だけでも快が得られることなどがわかった。カーネマンの神経経済学に関する論文はこれ一本だけであるが、多数の脳科学者や行動経済学者の論文が収録された『ニュ loエコノミクス』(アカデミック・プレス)という大著に後書きを寄せ、この分野には以前から関心を持っており、神経経済学の研究成果が人間行動や意思決定の研究に対して持つ意味は大きいと期待を込めて述べている。
最近のカーネマンはというと、ヒューリスティクス概念の彫琢とともに、幸福と人生の満足 度の研究に集中しているようである。二〇一〇年に同僚のアンガス・ディートンと著した最新 の論文「高収入は人生の評価を高めるが、感情的満足は高めない」(『全米科学アカデミー会 報』)では、ギャラップ社と行なった大規模な調査に基づき、日々の感情的満足と人生全体の満足度を測定した。それによると、日々の幸せは年収の増加とともに上昇するが、年収七万五○○○ドルを超えるともう伸びない。一方人生の満足度の方は、年収とともに上昇し、上限は ないことがわかった。つまりより多くのお金で人生の満足は買えるが、日々の幸福は買えない ということになる。味わい深いが、多様な解釈ができる結論である。
あるインタビューで「人生の満足を高めるためにどうしたらよいか」と尋ねられたカーネマンは次のように答えている(The Interview: The Most Important Living Psychologist, The Psychologist, 22(1), 2009)。――それは三つある。一時間の使い方を変えなさい。時間は究 極の稀少資源だから、そうであるように使うべき。二人生を悪くするようなことではなく、人生を豊かにするようなことがらに注意を向けるべき。三.注意を払い続けるような活動に時間を投資すべき。新車を買って運転しても、車にはそれほど注意を払わなくなる。しかし友人と社交しているときには、その活動に注意を払っている。そのような活動に従事すべきだ。
カーネマンの研究成果とこのインタビューによって、私たちが日々の幸せと人生の満足度を高められるようになれば幸いである。
最後に、昨今のような出版不況の折に、本書のような堅い書物を出版するという英断を下された楽工社の日向泰洋氏と、難しい言い回しや専門用語を含む原典を、わかりやすい日本語にして下さった翻訳家の山内あゆ子さんに敬意を表します。
目次
監訳者解説 友野典男
第1章 ノーベル賞記念講演 限定合理性の地図
本講演の三つのテーマ
知覚が、直接利用できる特徴と、直接利用できない特徴がある
直感は高度なことをするが、系統だったバイアスやエラーも犯す
知覚の特性①―「変化」に集中し「状態」を無視する
単なる賭けと、富(財産)を考えに入れた場合の賭けでは、好まれ方に違いが生じる
ベルヌーイの偉大なアイデア
―賭けは期待される貨幣の価値 (金額) ではなく、期待される心理的価値 (効用=満足度)で評価される
ベルヌーイの誤り
―賭けをする者は現在の富と未来の富の状態を「比較」して効用 (満足度)を測る
プロスペクト理論
―効用 (満足度) を決めるのは「変化」であって、「状態」(富の絶対量) ではない
心理学的な誤りが経済学で使われてきたのは、経済主体は合理的とする説に合致するから
無差別曲線の欠点―富の最終的な量は示されるが現在の状況は示されない
知覚の特性②―足し算をすべきときに平均値を求めてしまう
a 1つのグループになった物を評価する場合
b 一連の観察結果の証拠を評価する場合
c ある人が、あるグループもしくはカテゴリーに属すかどうかを判断する場合
d あるエピソードを評価する場合
まとめ
第2章 自伝
ダニエル・カーネマン 年譜
幼少期
青春時代
軍隊経験
大学院時代
プロになるためのトレーニング
エイモス・トヴェルスキーとの共同研究
一九七四年「サイエンス」誌の論文と合理性論争
プロスペクト理論
フレーミングと心の会計
行動経済学
その後
エイモス・トヴェルスキー追悼 (一九九六年六月五日)
第3章 効用最大化と経験効用
序
現在の感情状態の影響
選択状況の影響
過去に学ぶ
適応の予測の誤り
コメント
第4章 主観的な満足の測定に関する進展
主観的経験の測定原理と、実験室での測定
生活上の満足と幸せについての調査
生活上の満足に関するデータが有効な証拠
時間の使い方の評価
適応の謎
社会的な満足の測定 ―U指数
まとめ
参考文献
原注