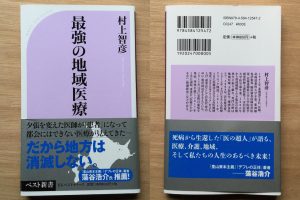ページコンテンツ
【まとめ – タレブ書籍おすすめ本 – まぐれ、ブラックスワン、半脆弱、身銭を切れ 】も確認する
目次
ふたりの勇敢な男性
ギリシア人たちのなかのローマ人
ロン・ポール
ギリシア・フェニキアの聖人
ラルフ・ネーダー
に捧ぐ

身銭を切れ
目次
第1部 「身銭を切る」とは何か
身銭を切ることの意外な側面
プロローグその1 アンタイオス、殺やられる
アンタイオスなきリピア
他人の命で遊ぶ――Ludis De Alieno Corio
人民の庇護者でなければ、貴族たりえない
ロバート・ルービン取引――隠れた非対称性とそのリスク
システムは排除によって学ぶ
その2 対称性の簡単なおさらい
I. ハンムラビからカントへ
なぜかパリにあるハンムラビ法典
白銀は黄金に勝る
普遍主義なんて忘れちゃえ
Ⅱ. カントからデブのトニーへ
ペテン師か、バカ者か、その両方か
因果関係の不透明性と頭示選好
身銭を切る必要のある人ない人
Ⅲ. 近代主義
専門化の痛すぎる弊害
シンプルがいちばん
身銭を切らないと私は愚鈍になる
規制か法制度か
Ⅳ. 魂を捧げる
職人
起業家という言葉に要注意
傲慢も方便
楽しみとしての市民権
英雄に本の虫はいない
魂を捧げる人々と適度な保護主義
身を切った裁判官
その3 「インケルトー』の肋骨
道
研ぎ澄まされた探知器
書評家
本書の構成
第1部の付録 人生や物事における非対称性
第2部 エージェンシー問題入門編
第1章 自分で捕まえた魚は自分で食べよ――不確実性に関する平等
お客は毎日生まれている
ロードス島の穀物の値段
不確実性に関する平等
ラブ・サフラとスイス人
会員と非会員――個から一般へのスケール変換の難しさ
私でもあなたでもなく、私たちのもの――Non Mihi Non Tibi, Sed Nobis
あなたは右でも左でもなく”斜め”寄り?
(文字どおり)同じ船の仲間
自分の持ち株を勧める
診察室に寄り道
次のテーマ
第3部 例のこの上ない非対称性
第2章 もっとも不寛容な者が勝つ――頑固な少数派の支配
あらゆる非対称性の生みの親「少数決原理」
ピーナッツ・アレルギー持ちの犯罪者――ラペリング
オーガニック食品と遺伝子組み換え食品を普及させるための共通の戦略
くりこみ群
“拒否権”効果
共通語
遺伝子と言語の違い
宗教の一方通行性と、ふたつの非対称的な規則
再び、分権化の話
道徳は少数派によって作られる
少数決原理の安定性に関する確率的議論
ポパーとゲーデルのパラドックス
市場と科学は聞く耳を持たない
1頭のみ、されど獅子―Unus Sed Leo
まとめと次のテーマ
第3部の付録 集団にまつわるいくつかの意外な事実
知能ゼロの市場
第4部 犬に紛れたオオカミ
第3章 合法的に他人を支配するには
フリーランス修道士が教えてくれること
パイロットを飼い慣らすには
企業マンから企業人へ
コースの企業理論
複雑な現代世界
奴隷所有の面白い形
自由はタダじゃない
犬に紛れたオオカミ
損失回避の心理
コンスタンティノポリスの復活を待ちわびて
官僚王国を揺るがすな
次のテーマ
第4章 人に身銭を切らせる
住宅ローンと2匹のネコ
隠れた弱みを見つける
自爆テロ犯に身銭を切らせるには
次のテーマ
第5部 生きるとはある種のリスクを冒すこと
第5章 シミュレーション装置のなかの人生
イエスはリスク・テイカー
パスカルの賭け
マトリックスの世界
あのドナルド・トランプが勝ったのは欠点のおかげ
次のテーマ
第6章 知的バカ
ココナッツはどこにある?
科学と科学主義
知的俗物
言語を話す前に文法を学ぶ
結論
追記
第7章 身銭を切ることと格差の関係
2種類の格差
静的な格差と動的な格差
ピケティとマンダリン階級の反乱
靴屋は靴屋を妬む
格差、富、縦の交流
共感と同類性
データ、ああ似非データ
公務員の倫理
次のテーマ
第8章 リンディという名の専門家
反脆弱性とリンディ効果
“真”の専門家は誰?
リンディのリンディ
審判は必要なのか?
女王との紅茶
学術機関の罠
自己の利益に反して
もういちど、魂を捧げる
科学は耐リンディである
経験的か理論的か?
おばあちゃんと研究者の対決
おばあちゃんの知恵のおさらい
第6部 エージェンシー問題 実践編
第9章 外科医は外科医っぽくないほうがいい
人は見た目が大事
グリーン材の誤謬
最高に着飾ったビジネス・プラン
仮装する主教
ゴルディアスの結び目
人生の過剰な知性化
干渉のもうひとつの側面
金と稲
報酬制度が生み出す歪み
贅沢品としての教育
いんちき探知ヒューリスティック
本物のジムはジムっぽくない
次のテーマ
第10章 毒を盛られるのはいつだって金持ち――他者の選好について
金持ちの選好は操られている
毒は金杯で飲まれる
巨大な葬儀場
会話の成立条件
進歩の非線形性
次のテーマ
第11章 不言実行
断りづらい提案
暗殺教団
マーケティングとしての暗殺
民主主義としての暗殺
カメラは身銭を切らせる道具
第12章 事実は正しいが、ニュースはフェイク
自分自身に反論する方法
情報は支配に抗う
反論の倫理学
次のテーマ
第3章 善の商品化
「善」の不正利用者ソンタグ
公と私
善の”売人”
そうなのか、そう見えるのか
聖職売買
善とは他者や集団に対して行うもの
不人気な善
リスクを負え
第14章 血もインクもない平和
平和はトップダウンでは生まれない
火星対土星
ライオンはどこへ消えた?
救急治療室から見た歴史
次のテーマ
第7部 宗教、信仰、そして身銭を切る
第15章 宗教を語るヤツは宗教をわかっていない
宗教の意味は人と時代によって異なりまくる
信念対信念
リバタリアニズムと教会なき宗教
次のテーマ
第16章 身銭を切らずして信仰なし
神々は安上がりなシグナリングがお嫌い
証
第17章 ローマ教皇は無神論者か?
ローマ教皇と無神論者の見分けはつくか
言葉では信心深い人たち
次のテーマ
第8部 リスクと合理性
第8章 合理性について合理的に考える
目の錯覚
エルゴード性が第一
サイモンからギーゲレンツァーへ
顕示選好
宗教は何のためにある?
“おしゃべり”と安っぽい”おしゃべり”
リンディの言い分は?
お飾りはお飾りとはかぎらない
第19章 リスク・テイクのロジック
エルゴード性
繰り返しリスクに身をさらすことが余命を縮める
*あなた”って誰のこと?
勇気と思慮深さは対極ではない
もういちど、合理性の話をしよう
ある程度のリスクを愛そう
浅はかな経験主義
まとめ
エピローグ リンディが教えてくれたこと
謝辞
参考文献
注解
専門的な付録
用語集
第1部 「身銭を切るとは」
本書は、かたや独立した本でありながら、かたや『インケルトー(Incerto)』と呼ばれる私の著作シリーズの一部でもある。『インケルトー』は、不確実性のもとで生き、食べ、眠り、論じ、戦い、睦み、働き、遊び、決断する方法や、ランダム性の問題について、(a)実践的な議論、(b)哲学的な物語、(c)科学的・分析的な解説を組み合わせたものだ。幅広い方々に読んでいただけるよう書いたつもりだが、だまされてはいけない。『インケルトー』は、あくまでもエッセイであって、どこか別の場所で行われた退屈な研究を大衆化したものではない(ただし、『インケルトー』の専門的な補遺は除く)。
本書では、次の4つの話題を同時に論じている。
(a)不確実性と、実践的な知識や科学的な知識の信頼性(両者が違うものだと仮定して)。
もう少しぶしつけな言い方をするなら、たわごとの見分け方。
(b)公平、公正、責任、相互性といった人間的な物事における対称性。
(c)商取引における情報共有。
(d)複雑系や実世界における合理性。
この4つが切り離せないものであるということは、身銭を切っている人間にとっては明々白々な事実だ。
身銭を切ることは、公平性、商業的な効率性、リスク管理にとって必要なだけではない。この世界を理解するうえで欠かせない条件なのだ。
本書の第1のテーマ (a)は、たわごとを見抜き、ふるい分けることだ。要するに、理論と実践、うわべだけの知識と本物の知識、(悪い意味での)学問の世界と実世界との違いを理解するということだ。ヨギ・ベラ流にいえばこうなるだろう。学問の世界では、学問の世界と実世界の違いはないが、実世界ではある。
第2のテーマ(b)は、人生における対称性や相互性の歪みだ。報酬が期待できるなら、それなりのリスクを引き受けるのが道理というものだ。ましてや、自分の失敗の代償をほかの誰かに払わせるなんてとんでもない。ほかの人にリスクを背負わせ、相手が危害をこうむったのなら、あなた自身がその代償の一部を払うのが仁義というものだ。「自分がしてほしいことを他者にもせよ」という原則に従うなら、あなた自身も、起こった出来事に対する責任を公平公正に負担するべきなのだ。
つまり、あなたが何か意見を述べ、誰かがその意見に従ったのなら、あなた自身もその結果に対してリスクを負う道義的な義務がある。経済的な見解を述べるなら、
「あなたの”考え”ではなく、ポートフォリオの中味を教えろ。」
*1 倫理、道徳的義務、能力が実生活で容易に切り離せないということを理解するには、次の例を考えるといい。あなたが責任ある立場の人、たとえば経理担当者に、「信頼しているよ」と伝えたとしよう。その意味は、(1)相手の倫理観を信頼している(パナマに金を流したりはしない、など)、(2)相手の経理の腕を信頼している、(3)その両方、のどれだろう? 実世界では、倫理と知識、倫理と能力をふたつに切り離すのは難しいというのが、本書の全体的な主旨だ。
訳注1 incertoはラテン語で「不確実性」という意味。
第3のテーマ(c)は、他者と共有すべき情報の量についてだ。中古車のセールスマンは、客が大枚をはたいて購入しようとしている車について、どんな情報を伝える(または伝えない)べきなのか?
第4のテーマ(d)は、合理性と時の試練だ。実世界における合理性とは、『ザ・ニューヨーカー』の記者や、軽薄な一次モデルを用いるどこぞの心理学者から見た合理性なんかではなくて、ある人自身の生存と関連するずっと奥深い統計的な合理性である。
ここで定義する(そして本書全体で使われている)「身銭を切る」という言葉の意味を、単なる金銭的なインセンティブの問題と誤解しないでほしい。金融の世界でよくいう利益の分配の話ではなくて、むしろ対称性の問題だ。いわば損害の一部を背負い、何かがうまくいかなかった場合に相応のペナルティを支払うという話だ。
この「身銭を切る」という概念こそが、インセンティブ、中古車の購入、倫理、契約理論、学習(実生活と学問の世界)、カントの定言命法、地方分権、リスクの科学、知識人と現実の接点、官僚の説明責任、確率論的な社会的公正、オプション理論、まっとうな行動、たわごとの押し売り、神学……等々の概念をひとつに結びつけるのだ。
身銭を切ることの意外な側面
本書にもう少し正確なタイトルをつけるとすれば、『身銭を切ることの意外な側面――隠れた非対称性とその影響』くらいになるだろう(かなりぎこちないけれど)。理由は単純。私自身、当たり前のことばかり書いてある本なんて、さらさら読む気にもなれないからだ。驚きがほしい。だから、「自分がしてほしいことを他者にもせよ」という相互性の原則にのっとり、大学の講義のような意外性のないあくび連発の旅ではなく、私自身が体験してみたいと思うような冒険へと、読者のみなさんをご案内したいと思う。
そういうわけで、本書は次のような構成になっている。第2部の終わりあたりまで読めば、身銭を切ること(つまり対称性)の重要性、一般性、普遍性があらかた理解できると思う。しかし、重要な物事が重要たる理由について、必要以上にくどくどと説明するのはよくない。原理原則というものは、正当化しようとすればするほど野暮になっていく。
このワクワクするような旅路では、第2のステップにも目を向ける。つまり、身銭を切るという概念が持つ意外な意味(つまり、パッと見ではわからないような隠れた非対称性)と、その予想外の影響である。そのなかには、私たちにとってかなり不都合な真実もあるが、多くのものは思いがけず役立つ。身銭を切るという概念の仕組みを理解すれば、複雑な現実の根底にある難問が解けるようになる。
たとえば、次のような問題だ。
なぜもっとも不寛容な少数派が世界を支配し、自分たちの選好を私たちに押しつけるのか? なぜ普遍主義は人々を助けるつもりがかえって害を及ぼすのか? なぜ現代には古代ローマ時代よりも奴隷が多いのか? なぜ外科医は外科医っぽく見えないほうがいいのか?なぜキリスト教神学は、神的な側面とは必然的に異なるイエス・キリストの人間的な側面を主張しつづけたのか? なぜ歴史家は平和ではなく戦争ばかりを記し、私たちを惑わせるのか? なぜ(リスクを伴わない)安上がりなシグナリングは、経済でも宗教でも同じように失敗するのか? なぜ一点の曇りもない経歴を持つ官僚よりも、明らかに性格に問題のある政治家候補のほうが、本物らしく見えるのか? なぜ私たちはハンニバルを崇拝するのか? なぜプロ経営者がお節介を焼きはじめたとたん、会社はつぶれるのか? なぜ異教信仰のほうが集団間で対称的なのか? 外交はどう行うべきか? なぜ非常に分権的な方法で運営されていない(現代の用語を使えば、ウーバー化されていない)かぎり、組織的な慈善団体に寄付すべきではないのか?なぜ遺伝子と言語の広まり方は異なるのか? なぜコミュニティの規模が重要なのか?(たとえば、なぜ漁師のコミュニティは、集団の人数、つまり規模が1段階上がったとたん、協力的なものから敵対的なものへと様変わりするのか?) なぜ行動経済学は個人の行動研究といっさい関係がないのか?そして、なぜ市場は市場参加者の個々のバイアスとほとんど関係がないのか? なぜ「生存」こそが合理性の唯一の尺度だといえるのか?リスク分担の基本的なロジックとは何か?
しかし、筆者にとって、身銭を切るという行為の本質は、公正、名誉、犠牲といった、人間の実存にかかわる物事にある。
身銭を切るという原則を取り入れれば、文明化に伴ってどんどん広がっていく次の乖離の影響を抑えられる。それは、行動と口からでまかせ(くっちゃべり)、結果と意図、実践と理論、名誉と名声、専門知識とペテン、具体的と抽象的、倫理的と合法的、中身とうわべ、商人と官僚、起業家と最高経営責任者、強さと強がり、愛と玉の輿、コヴェントリーとブリュッセル、オマハとワシントンDC、人間と経済学者、作家と編集者、学究と学問、民主制と統治、科学と科学主義、政治と政治家、愛と金、精神と字義、大カトーとバラク・オバマ、品質と宣伝、コミットメントとシグナリング、そして何より、集団と個人だ。
まずは、身銭を切るという概念がさまざまなカテゴリーに応用できるものだという事実を理解いただくため、ふたつのエピソードを通じて、先ほど挙げたいくつかの項目どうしを結びつけてみよう。
プロローグその1
アンタイオス、 殺やられる
母ちゃんから離れるな。
武将はいつの世にもいる。
ロバート・ルービンと彼の取引。
システムは自動車事故がお好き。
アンタイオスは、ギリシア神話に登場する巨人(正確には半巨人)であり、地母神ガイアと海神ポセイドンの文字どおりの息子だった。彼には奇妙な日課があり、(古代ギリシア時代の)リビアで通りがかりの者に格闘を挑んでは、地面に押し倒し、殺していた。この薄気味悪い日課は、彼なりの親孝行だったようだ。アンタイオスは殺した人々の頭蓋骨を材料にして、父ポセイドンのために神殿を建てようとしていた。
アンタイオスは無敵とされていたが、そこにはあるカラクリが潜んでいた。彼は母なる大地に足を着けることで、力を得ていたのだ。地から足が離れたとたん、アンタイオスはみるみる力を失っていった。一説によると、ヘラクレスは2の功業の一環として、アンタイオスを倒すよう命じられた。ヘラクレスはアンタイオスを地面から持ち上げると、母なる大地に足が着いていないうちに彼の息の根を止めた。
このひとつ目のエピソードが象徴しているのは、「知識は地に足の着いたものでなければならない」ということだ。いや、それどころか、どんなものも地に足が着いていなければならない。では、どうすれば実世界との接触を保っていられるのか? ずばり、身銭を切ることだ。つまり、実世界に対してリスクを背負い、よい結果と悪い結果のどちらに対しても、その報いを受けるという意味である。あなたが身に負った切り傷は、学習や発見の助けになる。いうなれば、有機的なシグナリングのメカニズムであり、ギリシア語でいうpathemata mathemataだ(「痛みは学びを助く」。幼い子を持つ母親ならよく知っているだろう)。『反脆弱性』で、大学が~発明したと考えられているものの大半は、実際にはいじくり回しによって発見され、そのあとで何らかの形式化を通じて正当化されたのだと説明した。私たちがいじくり回し、試行錯誤、実体験、時の営みによって得る知識、つまり地に足を着けることで得る知識は、純粋な推論を通じて得られる知識よりも、ずっと優れている。ご都合主義の教育機関や研究機関は、この事実を必死に隠しつづけているが。
次に、この考え方を、政策決定、とかいう似非概念に当てはめてみよう。
アンタイオスなきリビア
ふたつ目のエピソード。先ほどの逸話から数千年後、私がこの文章を書いている時点で、アンタイオスが暮らしていたとされる地、リビアには、奴隷市場が存在する。独裁者を排除する」ためのいわゆる トン政権交代、 が失敗に終わった結果だ。実際、2017年時点で、駐車場に設けられた即席の奴隷市場では、捕らえられたサハラ以南のアフリカ人たちが最高入札者へと売り渡されている。
2003年のイラク侵攻や2011年のリビア最高指導者の排除を推し進めた「干渉屋」と呼ぶべき連中(本書の執筆時点で活動しているヤツらの名前を何人か挙げるとすれば、ビル・クリストル、トーマス・フリードマン など)は、シリアなどの別の国々に対しても、似たような強制的な政権交代を支持している。
*1 干渉屋にはひとつ、大きな共通点がある。十中八九、ウェイト・リフターではない。
こうした干渉屋や、アメリカ国務省のお仲間たちは、反体制イスラム教組織の誕生、訓練、支援に手を貸した。当初、彼らは穏健派、だったが、やがてアルカイダの一部へと姿を変えていった。そう、2001年9月1日のテロ事件で、ニューヨーク市のタワーを吹っ飛ばした例のアルカイダだ。アルカイダは、もともとアメリカがソビエト・ロシアと戦うために構築(あるいは育成)した^穏健な反体制派、によって構成されたのだが、干渉屋たちはどういうわけか、そんなことをすっかり忘れているらしい。こういう教養人たちは、これから説明していくとおり、影響の影響、そのまた影響……を考えるようにはできていないからだ。
つまり、私たちはイラクの政権交代という例の手段を試し、大失敗した。こんどはリビアで例の手段を試し、代わりに活発な奴隷市場が生まれた。だが、「独裁者の排除」という当初の目的は達成した。めでたし、めでたし――。もしこんな道理がまかり通るなら、医者は患者のコレステロール値を改善するために、〝穏健、ながん細胞を注入し、患者の死後、検屍でコレステロール値が大きく改善したのを見て、自信満々で勝利を宣言する、なんてことになる。だが、私たちの知る医者は、死につながる `治療”を患者に施したりはしないし、するとしてもこんなに雑な方法は取らない。理由は明白。ふつう、医者はある程度の身銭を切っているし、複雑系について漠然と理解している。そして、数千年間かけて少しずつ築き上げられてきた医者の行動規範なるものを身につけているからだ。
だからといって、論理、知性、教育に愛想を尽かすのは間違っている。2次的、3次的な影響についてちょっと論理的に考えれば、今までの経験的証拠をすべて否定する方法でも見つからないかぎり、政権交代が奴隷制度の復活のような国家の衰退を後押しするということはすぐにわかるからだ(それが今までの典型的な結果だから)。つまり、干渉屋たちは実践感覚に欠けていて、歴史から何も学び取らないばかりか、純粋な推論すらまともにできない。ヤツらは、流行語まみれの巧妙であいまいな議論を用いて、純粋な推論を覆い隠してしまうのだ。
干渉屋の欠陥は3つある。(1)動ではなく静で物事を考える。(2) 高次元ではなく低次元で物事を考える。(3)相互作用ではなく行為という観点で物事を考える。こうした愚の骨頂の教養人(もっというと似非教養人)が頭のなかで行う推論の欠陥については、本書全体を通じてより詳しく見ていく。今の段階では、先ほどの3つの欠陥を具体的に述べるにとどめよう。
干渉屋のひとつ目の欠陥は、ヤツらが2次的な影響という視点で物事を考えられず、しかもその必要性にすら気づいていないという点だ。モンゴルの農民、マドリードのウェイター、サンフランシスコのロードサービス・オペレーターならほとんど誰でも、実生活には2次的、3次的、4次的、n次的な影響があると知っている。
ふたつ目の欠陥は、多次元的な問題と、それを1次元的に表現したものとの区別をつけられないという点だ。たとえるなら、多次元的な健康と、コレステロール値だけを下げることとの区別がつかないのだ。経験的にいって、複雑系には明白な1次元の因果関係のメカニズムはなく、不透明性のもとではそういうシステムにちょっかいを出してはならないということを、干渉屋たちは理解できない。この欠陥の延長線上として、ヤツらは独裁者』の行動を、現地ではなくノルウェーやらスウェーデンの政府の長の行動と比較してしまう。
3つ目の欠陥は、攻撃されることでかえって力を増していく人々の進化や、介入の反動として生じる問題の拡大を予測できないという点だ。
他人の命で遊ぶ――Ludis De Alieno Corio
そうして、いざ目論見が破綻すると、干渉屋たちは(ものすごく)頑固な男が書いた本にちなんで「ブラック・スワン」(影響の大きな想定外の出来事)と呼ばれている現象を持ち出してきて、不確実性がどうのこうのと騒ぎ出す。だが、ヤツらは結果が不確実性に満ちている場合にはシステムに余計なちょっかいを出すべきでないということをまるで理解していないし、もう少し一般的にいうと、結果が予測できない場合にはダウンサイド(潜在的損失)の大きな行動は避けるべきだということも理解していない。
ここで重要なのは、そのダウンサイドが干渉屋自身には何の影響も及ぼさないという点だ。干渉屋は、車2台分のガレージがあり、1匹の犬がいて、平均2・2人いる過保護な子どもたちのために作られた殺虫剤不使用の芝生の遊び場がある、エアコンの効いた郊外の家でくつろぎながら、性懲りもなく干渉を続けるのだ。一方で、非対称性をまるで理解できない愚鈍な人々に、飛行機の操縦を任せたらどうなるだろう。経験から教訓を学び取れず、理解不能なリスクを進んで冒すような無能なパイロットは、多くの人々の命を危険にさらすだろう。ただし、そういう無能なパイロットであれば、たとえばバミューダ・トライアングルのもくずと消えるだろうから、他人や人類を危険にさらすことはない。
ところが、知識階級と呼ばれている連中は、まったく深みのない近代主義的なスローガンを繰り返すくせに(たとえば、一方では首狩り族たちを応援しつつ、一方では「民主主義」という単語を連呼したりする。彼らにとって、民主主義というのは大学院の研究テキストに出てきた概念にすぎない)、自分たちの行動が招いた結果に対する代償はいっさい払わない。したがって、必然的に、文字どおり頭のねじがはずれた妄想人間たちが集団に居座りつづけるはめになる。一般的に、近代主義的な抽象概念を連呼する人間は、一定の教育を受けてはいるが(ただし、十分には受けていないか、受ける分野が間違っている)、説明責任はほとんど負わない。
こういうエアコンの効いた快適なオフィスに座っている干渉屋たちの失敗のツケを払わされたのは、ヤジディ教徒、近東(および中東)の少数派キリスト教徒、マンダ教徒、シリ
ア人、イラク人、リビア人といった罪のない人々だ。この状況は、これから説明するように、聖書が編纂される前、バビロニアの時代から続く正義の概念に反するし、人類が生き長らえてきたよりどころとなる倫理構造にも反する。
医師の場合と同じように、介入の第一原則は、「何よりもまず、害をなすなかれ(primum non nocere)」だ。もっといえば、「リスクを負わぬ者、意思決定にかかわるべからず」と言うこともできるだろう。
さらにいうと、
「人間は昔から愚かだったが、世界を破滅させるほどの力は持っていなかった。今は持っている。」
こうした干渉屋たちの「和平、プロセスが、いかにしてイスラエルとパレスチナのような数々の行き詰まりをもたらしてきたのかについては、またあとで。
人民の庇護者でなければ、貴族たりえない
この「身銭を切る」という概念は、歴史に織りこまれている。歴史的に、武将や戦争屋たちはみな自分自身が戦士であり、いくつかの面白い例外を除けば、社会はリスクを転嫁する連中ではなく、リスクを冒す人々が統治してきた。
過去の偉人たちは、一般市民よりはるかに大きなリスクを冒した。ローマ皇帝の背教者ユリアヌスは、皇帝在位中、ペルシア戦線の果てしなく続く戦いで命を落とした。ユリウス・カエサル、アレクサンドロス大王、ナポレオンについては、伝説作りの好きな歴史家たちのせいで、真相は予測の域を出ないが、ことユリアヌスに関していえば証拠は歴然としている。ペルシア兵の槍を胸に受けたユリアヌスほど、最前線で戦った皇帝の歴史的な証拠としてはっきりしているものはない (ユリアヌスは鎧を着けていなかった)。
ユリアヌス以前のローマ皇帝のひとり、ウァレリアヌスも、ペルシア戦線で捕虜となり、ペルシア王のシャープール1世が馬に乗るときの踏み台にされたといわれている。
また、東ローマ帝国最後の皇帝、コンスタンティノス1世パレオロゴスは、紫色の着衣を脱ぎ去り、イオアニス・ダルマトスといとこのテオフィロス・パレオロゴスに加勢すると、剣を頭上に振りかざし、トルコ軍のなかへと斬りこみ、避けられぬ死に堂々と向きあった。しかし、コンスタンティノス1世は降伏と引き換えに取引を持ちかけられたという説もある。そんな取引は、誇りある王たちにはふさわしくない。
これらは特殊な逸話ではない。私のなかの統計理論家は、こう確信している。ベッドの上で死を迎えたローマ皇帝は、3人にひとりにも満たない。さらに、高齢で亡くなったその数少ない皇帝も、もっと長生きしていれば、クーデターや戦闘で命を落としていただろう。
今日でさえ、君主は肉体的なリスク・テイクを求める一種の社会契約から、自分自身の正当性を得ている。イギリス王室は、1982年のフォークランド紛争の際、王室の成員のひとりであるアンドルー王子に,平民、よりも高いリスクを負わせ、戦線でヘリコプターを操縦させた。なぜか? いわゆる高貴たる者の義務というやつだ。元来、貴族の地位は、名声と引き換えに個人的なリスクを負い、ほかの人々を守ることで得られるものだった。王室は、奇しくもその社会契約をまだ覚えていた。人民の庇護者でなければ、貴族たりえないのだ。
ロバート・ルービン取引――隠れた非対称性とそのリスク
戦士をトップに据えないことが、文明だとか進歩だと思う人もいる。それは違う。
「官僚制度とは、人間が自分自身の行動の責任を取らなくてもいいようにするご都合主義の構造である。」
また、こんな疑問を持つ人もいるかもしれない。中央集権制度には、失敗の代償を直接負わない人々が必ずいる。だとしたら、いったいどうすればいいのか?
システムを分権化(もう少し丁寧にいえば局所化)するよりほかに選択肢はない。失敗の代償を背負わなくてすむ意思決定者をなるべく少なくするしかないのだ。
「分権化は、ミクロなたわごとよりもマクロなたわごとを言うほうが易しいという単純な事実を背景にして起こる。」
「分権化は、構造上の巨大な非対称性を和らげる。」
ただ、心配はいらない。私たちが分権化や責任の分散を行わなくても、分権化はひとりでに起こる。それも、痛みを伴う形で。身銭を切るという機構が備わっていないシステムは、不均衡が累積していくと、やがて吹っ飛び、分権的な形で自己修復する。もし絶滅を免れれば、の話だが。
たとえば、2008年、隠れた非対称のリスクがシステム内に累積した結果、銀行が吹っ飛んだ。リスク転嫁がお得意な銀行家たちは、特定の種類の爆発的リスクを隠して安定した儲けをあげ、教科書のなかでしか成り立たないような学術的なリスク・モデルを使い(学者はリスクについて無知も同然なので)、いざ銀行が吹っ飛ぶと急に不確実性(目に見えない予測不能なブラック・スワンと、例のものすごく頑固な作家)の話を持ち出してきて、過去の収入はちゃっかりそのまま懐に収める。これこそが、私のいうロバート・ルービン取引だ。
ロバート・ルービン取引?元アメリカ合衆国財務長官のロバート・ルービンは、国民がコーヒー代の支払いに使う紙幣に署名の入っている財務長官のひとりだが、2008年の銀行崩壊に先立つ10年間で、シティバンクからなんと1億2000万ドル以上をかき集めた。
訳注1 アメリカで発行されるドル紙幣には、在任中の財務長官の署名が印刷される。
ところが、シティバンクが文字どおりの支払不能に陥り、納税者による救済を受けても、彼は不確実性を言い訳として持ち出し、小切手に署名しなかった。表が出れば大儲け。裏が出れば「ブラック・スワンだ」と大騒ぎ。ルービンは、納税者にリスクを転嫁したことさえ認めなかった。そうして、スペイン語文法の専門家、補助教員、ブリキ缶工場の現場監督、菜食主義の栄養アドバイザー、地方検事補の事務官といった人々が、彼のために”損切り”を行った。要は、彼のリスクを引き受け、彼の損失を穴埋めしたわけだ。
しかし、最大の犠牲者は自由市場だ。もともと資産家を毛嫌いしていた一般大衆が、自由市場と高次の腐敗や縁故主義を混同するようになったからだ。実際には、ふたつはまったく逆のものだ。救 済という仕組みによって腐敗や縁故主義を可能にしているのは、市場ではなく政府なのだ。救済だけでなく、一般的に政府の介入そのものが、身銭を切らなくてすむシステムを生み出している。
一方で、朗報もある。レントシーキングに勤しむ銀行家や銀行業界の保護に加担したオバマ政権の努力とは裏腹に、リスク・テイク業界は「ヘッジ・ファンド」と呼ばれる独立した小さな構造へと移ろいはじめたのだ。
*2 「レントシーキング」とは、保護目的の規制や、利権”を利用して、経済活動になんら貢献することなく、つまりほかの人々の富を増やすことなく、収入を得ようとする行為。数ページ後に登場するデブのトニーがいうように、保護による経済的恩恵をまったく受けることなく、マフィアにみかじめ料を払わされるのと似ている。
こうした動きが起きたのは、主に銀行システムがあまりにも官僚化しすぎたせいだ。官僚たち(仕事といえば書類仕事だと思っている連中)は、銀行を規則でがんじがらめにしたが、どういうわけか、その何千ページという追加の規制のなかで、身銭を切るという概念はみじんも考慮されていなかった。一方、分権化されたヘッジ・ファンドの場合、オーナー経営者が純資産の半分以上を自身のヘッジ・ファンドに投じているので、顧客と比べて高いリスクにさらされている。もし船が沈めば、自分も一緒に沈む運命にあるのだ。
システムは排除によって学ぶ
さて、本書のここぞというセクションをひとつだけピックアップするとすれば、間違いなくこのセクションだろう。干渉屋の事例は、本書の物語の核とでもいうべき部分である)影響の両方を及ぼすことを示しているからだ。これまで見てきたように、干渉屋たちがいつまでたっても学習しないのは、ヤツらが失敗の被害をこうむっていないからだ。「痛みは学びを助く(pathemata mathemata)」のところで示唆したとおり、
「リスク転嫁のメカニズムは、学習も妨げる。」
もう少し実践的な言い方をするなら、
「相手が間違っていることを言葉で完全に納得させることはできない。それを思い知らせることができるのは、現実だけ。」
いや、正確にいえば、現実は議論に勝とうなどとは思っちゃいない。重要なのは、生き残ることだ。
つまり、
「現代性の由々しき側面とは、理解するよりも説明するほうが得意な人間がうじゃうじゃと増殖しているという点だ。」
あるいは、「行動するよりも説明するほうが得意」といってもかまわない。
要するに、「学習」とは、学校という名の厳重警備の刑務所のなかで行われる囚人教育とは似て非なるものだ。生物学でいえば、学習とは、世代間の自然選択というふるいを通じて、細胞レベルに刷りこまれるものだ。身銭を切るという行為は、抑止力というよりもこのふるいに近いと私は考えている。そして進化は、絶滅リスクが存在しないかぎり起こりえないものなのだ。さらにいえば、
「身銭を切らないかぎり、進化は起こりえない。」
この最後のポイントは、明々白々だ。ところが、進化論は擁護するくせに、身銭を切ったりリスクを分担したりしたがらない学者はごまんといる。彼らは全知全能の創造主による設計”という概念は否定するくせに、自分はまるで全知全能であるかのように何かを設計、しようとする。
一般的に、人は神聖なる国家(または大企業でも同じ)を崇拝すればするほど、身銭を切ろうとしなくなる。自分の予測能力を信じれば信じるほど、身銭を切ろうとしなくなる。スーツとネクタイを着ければ着けるほど、身銭を切ろうとしなくなる。
干渉屋の例でも見たとおり、人間は自分自身や他者の失敗からそれほど多くを学ばない。むしろ、学習するのはシステムのほうだ。システムは、特定の種類の失敗を犯しにくい人々を選択し、そうでない人々を排除することで学習していく。
「システムは部分を排除することによって、つまり否定の道によって学ぶ」
*3 「否定の道」とは、何が正しいかよりも何が間違っているかのほうが明瞭であるという原則。言い換えれば、知識は引き算によって膨らんでいくという原則。また、何がおかしいのかを理解するほうがその解決策を見つけるよりも易しいともいえる。何かをつけ加える行動よりも、何かを取り除く行動のほうが頑健である。なぜなら、何かをつけ加えると、目に見えない複雑なフィードバック・ループを生む可能性があるからだ。この点については、『反脆弱性』である程度詳しく論じている。
先ほども触れたとおり、無能なパイロットの多くは、とっくのとうに大西洋の底に沈んでいるし、危険な悪質ドライバーの多くは、美しい並木道に彩られた地元の静かな墓地に埋葬されている。交通システムが少しずつ安全になっていくのは、人間ではなくシステムが失敗から学ぶからだ。システムは人間と異なり、ふるい分けに基づいて経験を積み重ねていく。
これまでの話をまとめると、
「身銭を切るという行為が、人間の傲慢さを抑制する。」
さて、プロローグその2ではもう少し突っこみ、対称性という概念について考えてみよう。