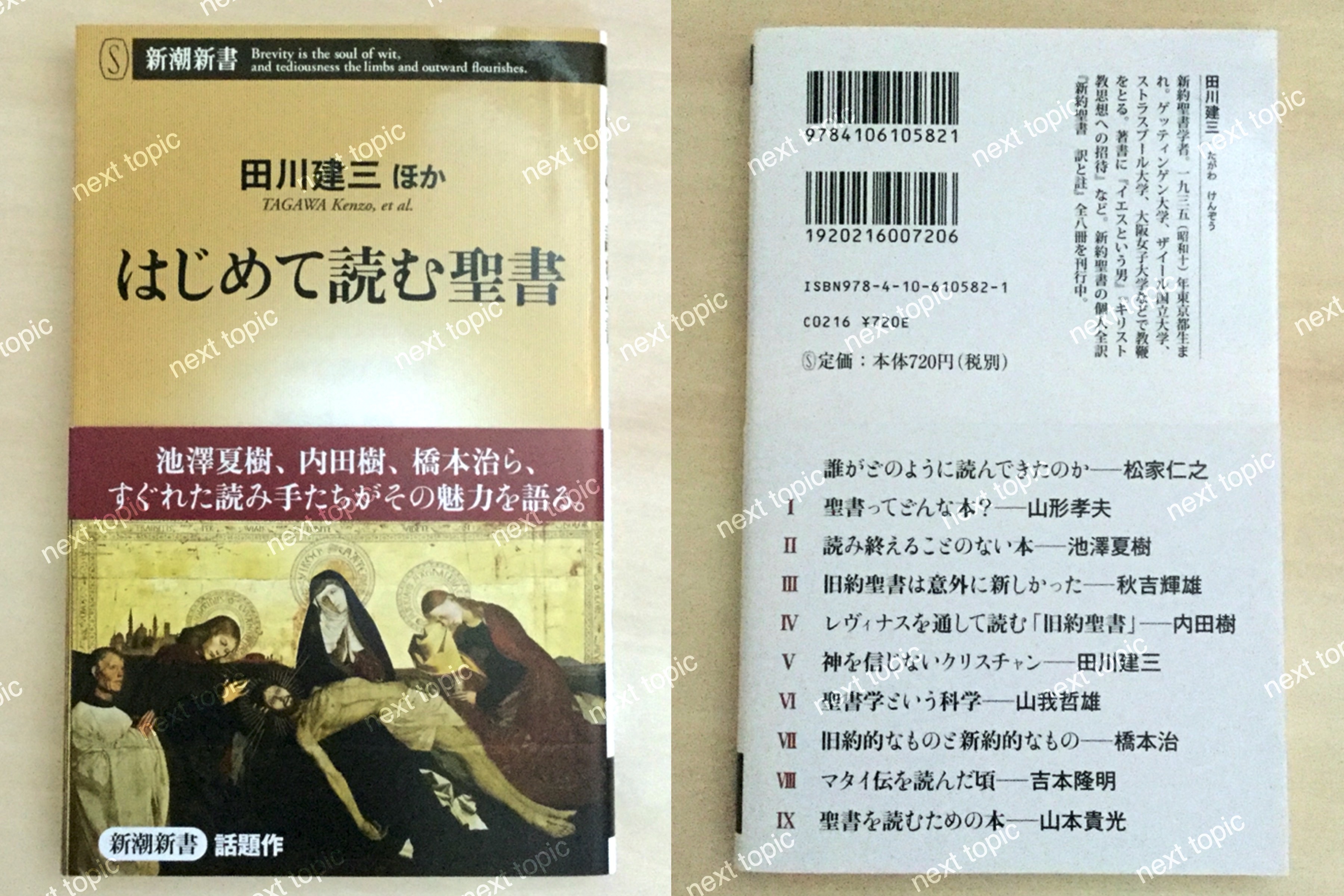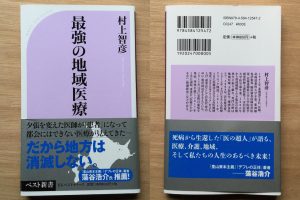【最新 – 聖書を知るおすすめ本 -入門やランキングも】も確認する
苦手意識のある人にこそおすすめの聖書入門
本書は、「聖書を、誰が、どのように、読んできたのか」をテーマに、9人の専門家にインタビューし、まとめたものです。このインタビューが示すのは、聖書にはたくさんの入り口が用意されているということです。聖書はとっつきにくいと感じている方や、聖書に対する専門家の解釈を知りたいと思われている方にもおすすめです。

誰がどのように読んできたのか――松家仁之
本書は、季刊誌「考える人」の特集「はじめて読む聖書」(二〇一〇年春号)をもとに、新潮新書編集部が再編集し、一冊にまとめたものだ。当時、「考える人」編集長として、聖書の特集を組んでみたいと考えたのは、聖書が自分にとって長いあいだ、近づきたいのに近づきがたい、特別な「本」だったからだ。
一度はじっくり読んでみたい――そう思っていても、この二千ページにおよぶ長大な書物は、構成も複雑なら、書かれた年代もさまざま、バックグラウンドを知らずに独力で読み進むのはいかにもこころもとない。史上最大の「ベストセラー」とはいうものの、クリスチャンではない自分が手にとってみても、見知らぬ土地に迷いこんだも同然、めざす入口さえ見いだせないままに撤退、とあいなってしまいそうだ。
わたしと同様、そのように感じている読者が多いのではないか。特集タイトルを「はじめて読む聖書」としたのは、そのような理由によるものだった。
とはいえ、「聖書とは何か」という問いでは、設定のかまえがおおきすぎる。そうではなく、「聖書を、誰が、どのように、読んできたのか」を問うのはどうだろう。答えはそれぞれの経験に即すことになるから、そこに正解はない。同時に、これほど多くの入口が聖書には用意されている、と示すことにもなるだろう。
さまざまな読み手を通して聖書に近づく。これを特集のゆるやかな枠組とし、何人かの方には直接お目にかかって、お話をうかがうことにした。
これを機にぜひ、とまっさきに思ったのは、かねてから畏怖の念を抱いていた新約聖書学者の田川建三氏である。
田川建三氏の著作は、キリスト教の出発点と真正面から向きあう直球勝負のものばかりだ。新約聖書学の研究成果を踏まえつつ、書物としての聖書の成り立ちをつぶさに明らかにし、二千年前の古文書である新約聖書を分析しながら「時代の反逆者」としてのイエス・キリスト像を生々しく描きだす。副読本の域をはるかに超える詳細をきわめた註釈つきの新約聖書の個人全訳全八冊が、二〇一六年夏の完結に向けて進行中である。
田川氏はときおりべらんめえ調までとびだす歯に衣着せぬ文章で、脇の甘い研究や聖書翻訳の不適切な部分を遠慮なく批判する、厳しい人である。しかも、神の存在は信じない(正確にいえば、不可知論者)とおっしゃる。そして同時に、まどうかたなきクリスチャンなのだ。孤軍奮闘、という言葉ほど、田川氏の仕事および仕事の姿勢を評するのにふさわしい言葉はないように思われる。
湯川豊氏によるインタビューは五時間におよんだ。おさないころどのようにしてキリスト教と出会い、やがて新約聖書の奥深くにはいりこむことになったのか、学問としての新約聖書学を選んだ先で出会ったさまざまな困難、あるいは大学教員として赴任したザイールでの希有な体験など、時間が経つのを忘れる話がつづいた。田川氏のもつ厳しさの根源に触れた気のするいっぽうで、節目ごとにあらわれる人びとに導かれるようにしかるべき道へと進んでいくことになったのは、厳しさというよりは素直さ、寛容さのなすところだったのではと感じた。運命を受けいれたうえで、ひとはどのように行動すべきか。田川氏の経験とその言葉はおおくの示唆に富んだものだった。
田川氏がインタビューのなかで触れている,恩師、大畠清氏のお名前を、もうひとりの語り手から耳にしたのも驚きだった。「大畠先生はなぜ人間に宗教があるのかということを歴史的に問うていた」――カトリックとプロテスタントの新共同訳聖書の翻訳・編集委員を務めた秋吉輝雄氏はそう振りかえりながら、「大畠先生に会わなければ、聖書学をやることもなかったでしょう」と断言する。ひとりの人間をその行く先へと導いたものが、「神」でも「神の言葉」でもなく「ひと」であったということにところを動かされる。
秋吉氏は旧約聖書の魅力を語るなかで、「人間にとって最も良いのは、飲み食い、自分の労苦によって魂を満足させること」という「コレヘトの言葉」のくだりをあげてくださった。インタビューのあいだ、ワインを口にし、葉巻をくゆらせ、対話を楽しまれる秋吉氏は、魂のつややかさを感じさせる、まさしくダンディーなかただった。
文学と聖書の深い結びつきも、興味のつきないテーマである。
欧米の文学を読んでいると、しばしば聖書の世界が見え隠れする。秋吉輝雄氏との共著『ぼくたちが聖書について知りたかったこと』で、信仰の外にある作家としてさまざまな疑問をぶつけている池澤夏樹氏は、文学のフィールドから聖書を眺めている。
欧米のさまざまな作家にくわえ、父・福永武彦、そして『バビロンに行きて歌え』など自らの小説のタイトルの由来もふくめて具体的にひもときながら、文学を涵養してきた聖書を「すべてのオリジンである広大な倉庫のようなもの」に喩える。クリスチャンでなくても、文学の隣に聖書を置きながら参照し読むことのよろこび。「イエス・キリストというのはたいへん優れたスピーチライターであり、コピーライターですから、名言がたくさんある」――信仰のない者にとっては、どこからでも「つまみ読み」が許される一冊の書物である、という池澤氏の言葉を聞けば、そびえ立つ高山のように見あげ、登攀をためらっていた気持ちがゆるやかにほどけてゆくではないか。
第二次世界大戦下のホロコーストによって六百万人の同胞を殺されたユダヤ人哲学者エマニュエル・レヴィナスの著作を、内田樹氏は二十代の終わりから読みはじめ、旧約聖書を聖典解釈学のなかに置き、聖典を読むことは師弟関係を結んだ師との一対一の対話によってのみ可能になる、とレヴィナスから学んだ。ユダヤ教ではなぜ儀礼が重んじられるのか、ユダヤ教はじつは無神論に近い、といった核心にも触れながら、いわば身体的に聖典を読むこと、解釈することの本質、について語ってくださっている。
吉本隆明氏の「マチウ書試論」は、思想家としての初期の重要な著作である。吉本氏がマタイ伝を読んだのは、日本が戦争に負け、それまで信じていたものが無効になったときだった。「ペシャンコになった自分に音を立ててぶつかってくるような言葉が、つぎつぎに現れる」ものとして「自分がなぎ倒されるように読んだ」。レヴィナスにせよ、吉本隆明氏にせよ、戦争をくぐりぬけ、生き残った者として、いわば耐え難い現実と向きあうための言葉を探り、思想の足場として踏みだしてゆく拠点となったのが聖書であったことは、聖書が二千年になんなんとする時を生きのびてきた理由の一端を見せてくれている、と言えないだろうか。
しかし、もしマルクスのいうように宗教が民衆の阿片であるならば、橋本治氏へのインタビューで語られるこの言葉は、つよい解毒作用をもつだろう。「聖書はちゃんと読んだことがないんです。読もうとしていつも挫折する(笑)。その理由は、命令されることに疲れるからだと思う。聖書って基本的に命令の言葉で綴られているじゃないですか」。
マルクス、フロイト、アインシュタインという三人のユダヤ人のあり方と聖書の関係、すなわちヨーロッパの物の考え方と聖書の関係を解きながら、日本のやおよろずの神について考える。「ユダヤ教のタルムードもそうだけれど、宗教というのは心だけに対応するものじゃなくて、人の暮らしのあり方全体に対応するものだ」という橋本氏の指摘は、内田氏へのインタビューとも響きあう宗教論として、読むものを立ち止まらせる力を持つ。
たったいまのわたしたちの日常的実感は、宗教的なものからはるかに遠ざかって生きている、というものではないか。しかし、ほんとうにそうだろうか。
近年、つぎつぎと出版され、読者の数を増やしているのは、「このようにすれば、こうできます」という自己啓発本である。八〇年代前半のアメリカで「セルフヘルプ」本、すなわち自己啓発本が大流行となっていることを知った当時、どこまで本気なのかと奇異な印象を持った。しかし気がつけば九〇年代後半あたりから、日本の書店にも自己啓発本の波が押し寄せ、それは増えてゆくばかりに見える。
非宗教的に生きていると思いながら、「基本的に命令の言葉で綴られている」自己啓発本をいわば宗教の代用品として無意識に求めている、ということはないだろうか。だとすれば、宗教に似て非なる、お手軽な「命令」を読み、やがてあとかたもなく忘れてしまうよりは、二千年ものあいだ生きながらえ、くりかえし読まれてきた言葉がならぶ聖書を、時間をかけじっくり読んでみたい。あらためてそう思う。
山形孝夫氏による聖書の概説、山我哲雄氏による聖書学案内、山本貴光氏によるブックガイドは、聖書のなりたちにさかのぼり、長年にわたる人々のとりくみをたどったうえで、そこからはじまるあらたな本の旅への信頼に足る手がかり、羅針盤になってくれることだろう。
秋吉輝雄氏、吉本隆明氏は、本書のインタビューから時をおかずして逝去された。このようなお話をうかがうことができたことに深く感謝する。
松家仁之(まついえ・まさし)
一九五八年東京生まれ。早稲田大学第一文学部卒業後、新潮社入社。二〇〇二年、季刊誌「考える人」創刊。二〇一〇年まで編集長を務める。退職後、二〇一二年、長篇小説『火山のふもとで』を発表。同作により読売文学賞受賞。著書に『沈むフランシス』、編著に『美しい子ども』ほか。最新作は小説『優雅なのかどうか、わからない』。
目次
誰がどのように読んできたのか――松家仁之
Ⅰ 聖書ってどんな本?――山形孝夫
①書には何が書かれているのか
旧約聖書のなりたち/新約聖書のなりたち
②日本語訳聖書のはじまり
日本最古の聖書訳/標準語訳によって失ったもの
Ⅱ 読み終えることのない本――池澤夏樹
聖書とは?/参照する、引用する/文学のなかの聖書/僕の好きな聖書
Ⅲ 旧約聖書は意外に新しかった――秋吉輝雄
耳から知った聖書/天文学から聖書学へ/聖書のテクスト・クリティーク/旧約聖書に流れる時間/旧約聖書の読みどころ
Ⅳ レヴィナスを通して読む「旧約聖書」――内田樹
ホロコーストと哲学/解釈の縛りと自由/ユダヤ教は無神論に近い/旅に出よ
Ⅴ 神を信じないクリスチャンーー田川建三(聞き手・湯川豊)
姉に引かれて/大畠清先生のこと/ストラスブール大学へ/マルコ福音書から始まった/存在しない神に祈る/無神論というより不可知論/ゲッティンゲン大学へ/ザイールでの暮らし/貧しい者は幸いなのか/新約聖書のギリシャ語/世界の「新訳」事情/二千年前の古文書/イエスという男/必死にではなく、のんびりと
Ⅵ 聖書学という科学――山我哲雄
聖書学とは何か/それは「誰の」思想なのか
Ⅶ 旧約的なものと新約的なもの――橋本治
古典現代語訳の悩ましさ/なぜ聖書が読めないか/新約的、旧約的/懺悔の効用と日本人/江戸時代のモラル/神様による構造分析
Ⅷ マタイ伝を読んだ頃―吉本隆明
終戦の日、沖へ泳ぐ/自己嫌悪から、聖書を読む/地獄の子/あなたには関係ない/「マチウ書試論」を書く
Ⅸ 聖書を読むための本――山本貴光源
山形孝夫
やまがた・たかお
宗教人類学者、宮城学院女子大学名誉教授。一九三二年、宮城県仙台生まれ。東北大学文学部卒業。同大学院博士課程満期退学。宮城学院女子大学教授、同大学キリスト教文化研究所所長、同大学学長をつとめた。著書に『聖書物語』『聖書小事典』『聖書の起源』『砂漠の修道院』『死者と生者のラスト・サパー』、近刊に『黒い海の記憶』、訳書に『マグダラのマリアによる福音書』『『ユダ福音書』の謎を解く』など。