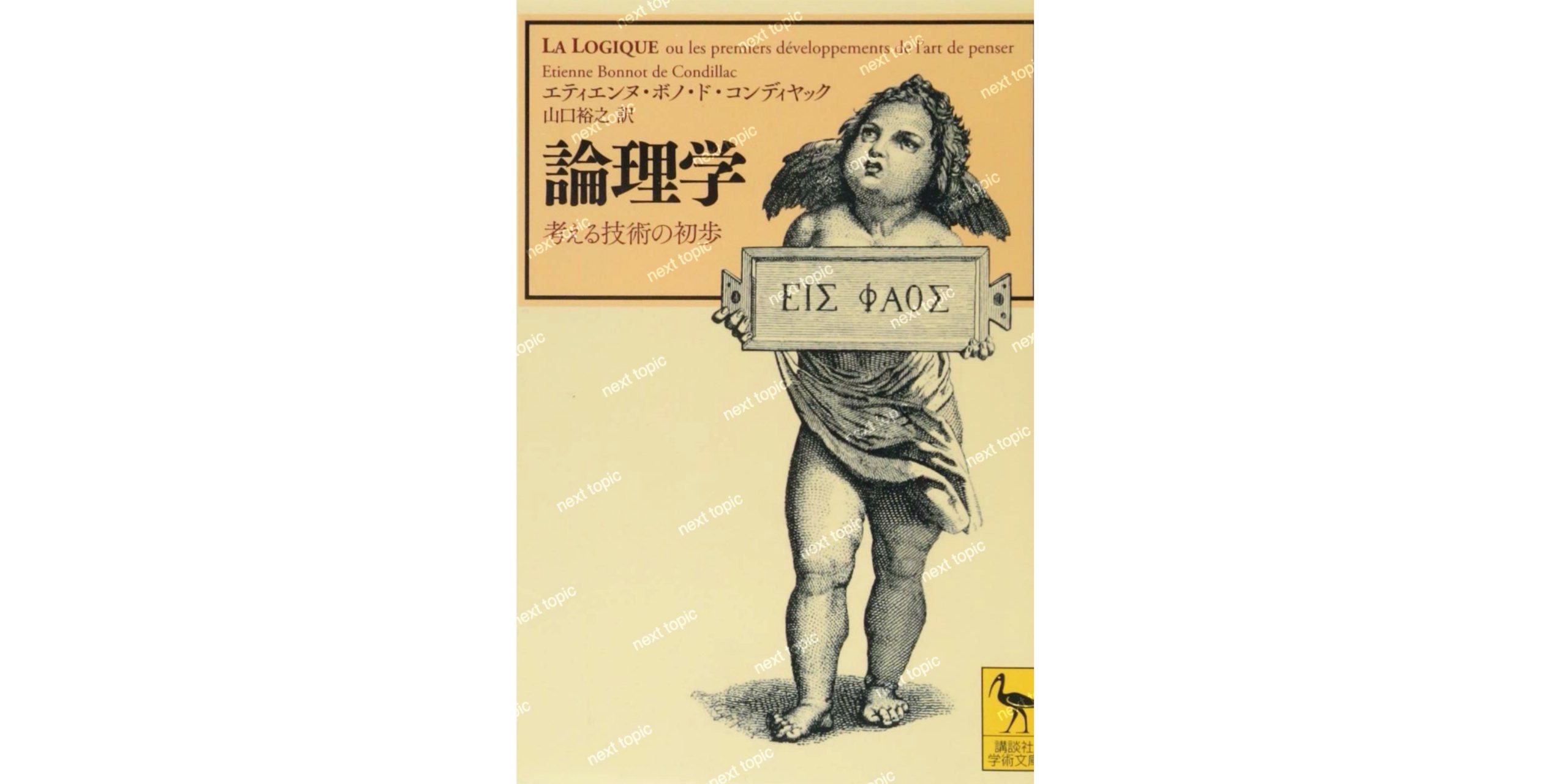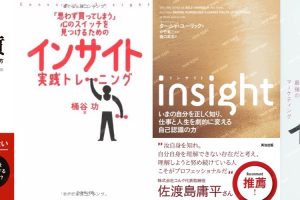ページコンテンツ
【最新 論理学について学ぶためのおすすめ本 – 思考の基本と本質を知る】も確認する
西洋が生んだ知の技法
本書では、分析こそが私たちが生まれついての本性から学んだ方法であることを見ていき、この方法を用いることで、観念と心の諸機能についてそれらの起源と発生を説明します。また、分析の手段と効果について考察し、推論の技術はどのようなものに還元されるかを示していきます。
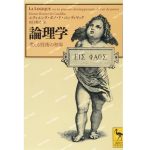
本作品は、縦書き表示での閲艶を推奨いたします。横書き表示にした際には、表示が一部くずれる恐れがあります。
ご利用になるブラウザまたはビューワにより、表示が異なることがあります。
論理学
考える技術の初歩
エティエンヌ・ボノ・ド・コンディヤック
山口裕之訳
目次
この本の目的
第一部 自然はいかにして我々に分析を教えるか。また、この分析という方法に即して観念と心の諸機能の起源と発生を説明すると、どのようになるか
第一章 自然はいかにして考える技術の最初のレッスンを我々に与えるか
感覚する機能が心の諸機能の中の最初のものである/我々は感官を制御するすべを知るとき、感覚する機能を制御するすべを知る/我々が身体器官を制御できるのは、それを何度かうまく使ったあとで、どうやったらうまく使えたのかに気づくときである/我々を最初に教えるのは自然、すなわち欲求によって規定された諸機能である/幼児はいかにしてさまざまな知識を獲得するか/自然はいかにして幼児に判断の誤りを警告するか/なぜ自然は警告するのをやめるのか/知識を獲得するための唯一の手段
第二章 知識を獲得する唯一の方法は分析である。いかにして我々は分析という方法を自然そのものから学ぶか
一目見ただけでは、我々は自分が見ているものの観念を得られない/観念を形成するためには、一つ一つ順番に観察しなくてはならない/対象をあるがままに理解するには、対象を順番に観察する継時的な秩序によって、対象間に同時的に存在している秩序を再構成しなくてはならない/こうした手段によって精神はおびただしい数の観念を全体的に把握できる/このようにして観察することで、人はものごとを分解して再構成するのだから、人は厳密で判明な観念を形成することになる/こうした分解と再構成こそ、人が「分析」と名づけるものである/思考の分析は感覚的な対象の分析と同じやり方でなされる
第三章 分析は精神を正確なものにする
感覚的な対象を表象するものと考えられた感覚印象こそ、人が本来の意味で「観念」と呼ぶものである/厳密な観念、つまり正しい知識を与えてくれるのは分析だけである/この方法は誰もが知っている/正確な精神は分析によって作られた/悪い方法は精神を誤らせる
第四章 いかにして自然は我々に感覚的対象を観察させ、さまざまな種類の観念を獲得させるか
人は、知っていることから知らないことへ進むことによってのみ学ぶことができる/誰であれ、知識を獲得したことのある人は、さらなる知識を獲得できる/観念は次から次へ連続的に生まれていく/我々が最初に獲得する観念は、個別的観念である/人は観念を分類することで類や種を形成する/個別的観念はいきなり一般観念になる/一般観念はさまざまな種に下位区分される/我々の観念は、我々の欲求の体系と一致した体系を形作る/体系はいかなる技巧によって形作られるか/体系はものごとの本性に即して作られるのではない/観念はどこまで区分し、下位区分すべきか/なぜ種は必ず混乱に陥るのか/種が混乱してもとくに不便がない理由/我々は物体の本質を知らない/我々は、観察して確信したことについてのみ、厳密な観念を持つ/観念は厳密であっても、完全なものにはならない/我々が行うすべての研究は同じ方法でなされる。その方法とは分析である
第五章 感官で捉えられないものごとについての観念
結果は原因の観念を与えないにもかかわらず、どうして我々は原因の実在を判断するのか/現代の哲学者たちは、感官で捉えられない原因が実在することをいかにして我々に判断させるか。また、それについての観念をいかにして我々に与えるか
第六章 同じ主題のつづき
行動と習慣/人は、身体の行動をもとに心の作用を判断する/徳と悪徳の観念/行動の道徳性の観念
第七章 心の諸機能の分析
我々に自分の精神について教えてくれるのは分析である/感覚する機能の中に、心の機能がすべて見出される/注意/比較/判断/反省/想像力/推論/知性
第八章 同じ主題のつづき
欲求/不満/不安/欲望/情念/期待/意志/意志という言葉の別の意味/思考第九章感覚能力と記憶力の原因について誤った仮説/動物の内部には、植物的生命の原理としての運動がある/この運動が取りうる規定が感覚能力の原因である/これらの規定は感覚器官から脳へ伝わっていく、我々が感覚するのは、感覚器官がものに触れるか、ものによって触れられたときだけである/我々は、いかにして物体の接触が感覚印象を生じさせるのかを知らない/我々に新たな感覚器官が与えられていたなら、新たな感覚印象が生じていただろう、我々が現に持っている感官は我々にとって十分なものである/動物はいかにして意志に従って動くことを学ぶか/動物の身体はいかにしてある運動の習慣を獲得するか/脳も同様の習慣を身につける。そうした習慣が、記憶力の物理的ないし機会的原因であろ/我々がある観念について考えていないときには、その観念はどこにも存在しない/観念はいかにして再生されるか/記憶力に関わるすべての現象は脳の習慣によって説明される/記憶力の座は脳だけでなく、観念を伝達するすべての器官にある/夢についての説明/記憶力が失われるのは、脳が習慣
を失うからである/結論
第二部 分析の手段と効果についての考察、すなわち、よくできた言語に還元された推論の技術
第一章 我々が自然から学んだ知識はいかにしてすべてが完全に結びついた体系をなすか。自然の教えを忘れたとき、我々はいかにして道に迷うか
自然は、我々の心身の諸機能の使い方を制御することで、いかにして我々に推論することを学ばせるか、我々はいかにして自然の教えを忘れ、悪しき習慣に従って推論するようになるか/悪しき習慣のせいで我々が犯す過ち/考える機能に秩序をもたらす唯一の手段
第二章 いかにして行動の言語が思考を分析するか
我々は言語という手段によってのみ分析することができる/行動の言語の諸要素は生得的である/なぜ行動の言語において当初はすべてが混乱しているのか/それから行動の言語はいかにして分析的方法になるか
第三章 いかにして言語は分析的方法になるか。この方法の不完全性
諸言語はいずれも分析的方法である/言語は、他の人間の発明品と同様に、人がそれをなそうという意図を持つ前に始められた/言語はいかにして厳密な方法になったか/言語はいかにして欠陥のある方法になったか/人々が、諸言語はいずれも分析的方法であることに気づいてさえいたら、推論の技術の諸規則を見出すのは困難でなかったはずである
第四章 言語の影響について
言語が我々の知識や主義主張、先入観を作る/学問上の言語が、もっともよくできた言語というわけではない/最初の通俗言語が最も推論に適した言語であった/言語に無秩序を持ち込んだ張本人は、哲学者である
第五章 抽象的で一般的な観念についての考察。推論の技術はいかにしてよくできた言語に還元されるか
抽象的で一般的な観念とは名称にすぎない/結果として、推論の技術はよくできた言語に還元される/この真理をよく知っておけば、多くの誤りを犯さずにすむ/言語を作り、技術と学問を創造するのは分析である/分析に従って真理を探求すべきであって、想像力に従ってはならない
第六章 言語の乱用を改善する唯一の手段は定義だと考える人がどれほど間違っているか
定義にできるのは、ものごとを提示することだけである。それゆえ、定義を原理として与えられたときには、その意味を知ることができない/定義できるのは稀な場合である/すべてを定義しようとする偏執狂の無駄な努力/観念を規定するのは分析だから、定義は無用である/総合という蒙昧な方法
第七章 言語が単純であれば、推論はどれほど単純になるか分析より総合を好む人の誤り/諸学問は、極めて単純な言語を話すなら、厳密なものになる/そのことを証明する問題/代数学の記号を用いたこの問題の解法/推論の明証性は、ある判断から他の判断へ移行するときに示される同一性にのみ存する/あまり厳密でない学問とは、それを語る言語のできが悪い学問である/代数学
は、本来の意味での言語である
第八章 推論の技巧は何に存するか
問題を解くときにやるべきことは二つある。一つは前提を明示すること、つまり問題の状態の提示であり、もう一つは知らないこと[未知数」を取り出すこと、つまり推論である/問題の状態の提示という言葉によって理解すべきこと/推論の技巧はすべての学問分野において同じである。そのことを証明する例
第九章 確かさのさまざまな段階。明証性、推測、類推について
論理的明証性が欠ける場合、我々は事実の明証性と感覚意識の明証性を持つ/論理的明証性によって物体の実在が証明される/現象・観察・実験という言葉の意味/推測の用法/類推の確かさには、さまざまな段階がある/この『論理学」を学ぼうとする若者への助言
付論 ペリグーの教授ポテ氏から説明を求められた学説について
解説
この本の目的
人間にとって、自分の腕の弱さを補うために、自然*1が与えてくれた手段を使うのは自然なことであった。人間は、あえて技術者になろうとする前にすでに技術者だったのである。同様に、人間は論理学者になろうとする前にすでに論理学者であった。つまり人間は、いかにして考えるかを探求する前にきちんと考えていたのである。人々が「思考はいくつかの法則に従っているのではないか」と思い至るまで、何世紀もの時間が流れる必要があった。今日でも大多数の人が、そんなことにはまったく思い至らないまま、それでもきちんと考えている。
他方、最上の精神を持つ人たちは、知らず知らずのうちに、いわゆる「才能」という恵まれた素質によって、つまり、正確なものの見方や鋭敏な感じ方によって導かれてきた。そうした人たちの著作が他の人々の手本となった。彼ら自身は自分が楽しいものや光るものを生み出したときにどのような技巧を用いたのかを自覚していなかったが、人々は彼らの著作の中にそうした技巧を探したのである。彼らの著作が驚くべきものであればあるほど、人々は、彼らが尋常ならざる手段を持っているのだと考えた。そして、実は単純な手段を探すべきだったのに、尋常ならざる手段を探してしまったのである。そうして人々は早計にも、天才の謎を解いたと信じてしまった。しかし、天才の謎は容易には解けない。天才自身でさえ自分の秘密を明らかにする能力を持っているとは限らないのだから、その秘密はいっそう厳重に守られているのだ。
つまり人々は、考える技術の法則を、それが存在しない場所で探してしまったのである。そして、もし我々が一からこの研究を始めなければならなかったとしたら、おそらく我々自身も同じく間違った場所を探してしまっていたことだろう。しかし、これまでに人々が、それが存在しない場所を探しておいてくれたおかげで、我々にはそれが存在する場所が示されたのだ。もし我々がこれまでの人々よりもきちんとその場所を観察することができさえすれば、我々は考える技術の法則を発見したと誇ることができるだろう。
さて、大きな物体を動かす技術に関する法則は、身体の諸機能と梃子のうちにあり、我々は自分の腕で梃子を利用することを学んできた(1)。それと同様に、考える技術に関する法則は、心の諸機能*?と梃子のうちにあり、我々の精神は梃子の使い方を学んできた「1」。
それゆえ、心の諸機能と精神の梃子を観察しなくてはならない。自分の身体の諸機能を初めて使おうとするときに、まず定義や公理や原理を立てようなどと思う人はいないだろう。実際、そんなことはできない。人は、とりあえず自分の腕を使ってみることから始めざるをえない。腕を使うことは人間にとって自然なことである。同様に、役に立ちそうなものは何でも利用することも人間にとって自然であり、人はすぐに棒を梃子として使うようになる。ものを利用する経験が積み重なると、大きな力になる。経験の中で人は、自分がなぜ失敗したのか、どうすればもっとうまくできるのかに気づき*3、身体の諸機能は徐々に改善されていく。こうして人は自分で学ぶのである。
我々が最初に精神の諸機能を使用するとき、自然はこのようにして我々に始めさせるのである。最初に身体の諸機能を制御していたのは自然だけであった。同様に、最初は自然だけが精神の諸機能を制御する。そのあとで我々は自分で自分を導けるようになるが、それは自然が始めさせてくれたことを継続する場合だけである。我々が進歩できるのは、自然が与えてくれた最初のレッスンのおかげである。そこで我々は、この『論理学』を定義や公理や原理から始めることはしない。自然が我々に与えてくれたレッスンを観察することから始めよう。
第一部では、分析こそが我々が自然から学んだ方法であることを見ていく。それから、この方法を用いることで、観念と心の諸機能について、それらの起源と発生を説明する。第二部では、分析の手段と効果について考察し、推論の技術は「よくできた言語」に還元されることを示す。
この『論理学』は、これまで書かれた「論理学」と称する書物とはまったく似ていない。しかし、単に論理学を新奇なやり方で扱っていることだけが本書の特長だ、などということがあってはならない。特長と言うからには、この本で論理学を扱うやり方が、単に新しいだけでなく、もっとも単純で簡単で光に満ちたものであることが必要である。
原注(1)ベーコンによる比喩である。
ルロワによる注
訳注
*1コンディヤック哲学のキーワードであり、近代の経験論哲学やそこで唱えられたいわゆる社会契約論、自然法思想におけるキーワードでもある(ホッブズ、ロック、ルソーなど)。「自然(nature)」という言葉の語源は、ラテン語で「生まれる、生じる」を意味するnascorの名詞形naturaである。それゆえnatureは、「自然」と訳すよりも「本性」と訳した方が自然な場合がある。実際、コンディヤックはこの言葉を、主に「人間の生まれついての本性」という意味で使っているが、彼の議論はロックの影響を強く受けており、経験論哲学の中に位置づけられるものであるため、本書では従来の哲学研究の訳語に従い、原則として「自然」と訳した。
*2原語はfacultésdel’ame,facultéを「機能」、imeを「心」と訳した。
facultéはラテン語のfacio(行う、作る。フランス語のfaire)の名詞形facultasを語源とし、要するに「何かを行うことができる状態」を指す。日本語としては、「心の機能」より「心の能力」とした方が自然かもしれない。しかし、本書や「人間認識起源論」、「感覚論」などで展開されるコンディヤックの人間論には機械論的と言えるような側面がある。つまり、人間は能動的・意志的に成長進歩するというよりは、感覚印象がいわば自己組織化することで精神的な諸能力が形成される、という論構成になっている。そうしたことからあえて、機械についての表現のニュアンスがある「機能」と訳した。
imeは哲学の文献では「霊魂、魂」などと訳されることがあるが、これらの日本語にはなにやらおどろおどろしいイメージがある。近代哲学で言うimeは要するに「私たちの主観的意識が展開する場」であるから、本書では「心」と訳した。コンディヤックはこの言葉を、「精神(esprit)」と区別せずに使っている。
なお、imeの語源は「微風、息、生命」を意味するラテン語のanimaである。同根の言葉にanimal,animationなどがある。なぜ「息」と「生命」が同じ言葉なのかと思われるかもしれないが、日本語でも「息がある」という表現で「生きている」ことを意味するのと同様の発想であろう。そもそも日本語の「生きる」という言葉の語源は「息」であるという説が有力なようである(前田宮祇監修「日本語源大辞典」小学館、二〇〇五年による)。
*3原語はremarquer,コンディヤック認識論のキーワードの一つである。訳語としては「気づく、注目する」が考えられるが、本書では原則として「気づく」と訳した。日本語の語感として「気づく」のほうが偶然任せ、「注目する」のほうが能動的だが、訳注*2で書いたようなコンディヤックの議論の「機械論的性格」に鑑みて「気づく」とした。コンディヤックの認識論では、最初に人間がものごとを知るのは「自然に従って」である。つまり、意識的・意志的に研究する以前に、自然な欲求に従ってこの世界を探索することで、知らず知らずのうちに知識を獲得するのである。そのあと、自分がすでに暗黙のうちに知っていることに「気づく」ことで、その知識を意識的ないし意志的な行動に活かせるようになる。ジャック・デリダは『たわいなさの考古学」(飯野和夫訳、人文書院、二〇〇六年)のなかでコンディヤック認識論のこうした「事後的性格」を指摘している。
re-marquerとは「再び-印をつける」ということだが、そのほかにもretracer(想起する、改めて描き出す)、rappeler(呼び戻す)などのようにreという接頭辞がつく言葉がコンディヤックの議論には頻出する。これはコンディヤック認識論の「事後的性格」を反映していると言えよう。
第一部 自然はいかにして我々に分析を教えるか。また、この分析という方法に即して観念と心の諸機能の起源と発生を説明すると、どのようになるか