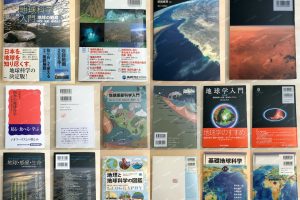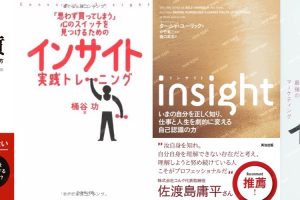あなたはこの時代に生きたいか?全ての日本人が読むべき本。
多くの人が知る幕末・維新、人名や出来事。その前提が覆されるかもしれない新情報が数多く提示されています。
「欧米列強」と言われていた時代、果たして本当に日本の文明は劣っていたのでしょうか。当時、政府をコントロールしていたのは極少数の権力者でした。しかし、歴史を動かしてきたのは紛れもなく名前無き我々の先祖なのです。学校ではまず出てこない、誰も教えてはくれない視点で切り込んだ容赦ない1冊。

はじめに―喜望峰から江戸へ
ペリーとマンデラ
和暦で嘉永五年、陽暦の一八五二年一一月、日本を開国させる使命をあたえられたペリーは、アメリカ東部の海軍基地を出港し、大西洋を横断、アフリカ大陸西岸を南下し、ちょうど二カ月後、年が改まった五三年一月下旬に大陸南端の、イギリス植民地だったケープタウンに入る。
本書の最初の主題である江戸湾の浦賀へ投錨するのは、さらにその五カ月半後である。
『ペリー提督日本遠征記』の、この大西洋からインド洋へと航海するあたりは、欧米の植民地にされたアフリカやアジアの諸民族の様子がじつに興味深く描かれている。南アフリカの部分を紹介しつつ、本書の序言にかえよう。
一八五三年の南アフリカは、五〇年から始まっていたイギリスと南アフリカ諸部族とのムランジェニ戦争がイギリス軍の勝利に帰していた。ペリーは、牢獄に捕らえられたコーサ族(諸部族の総称)の首長夫妻を訪問し、会見する。武運つたなく、妻や属僚とともに捕虜となった首長は、10代半ばの立派な容貌の青年であった。画家ブラウンが描いた首長夫妻の肖像のうち、夫人の肖像を上に掲げた。「ペリー提督日本遠征記』の図版のなかで格別に印象に残るものである。気品があり、深い憂愁が伝わってくる。このコーサ族の子孫の一 人が、南アフリカ共和国の反アパルトヘイトの不屈の運動家、後に大統領となったマンデラである。

「彼は、弾圧裁判(リヴォニア裁判、一九六三年)での、 世界中の関心が集まった反対陳述や自伝で述べているように、悲痛な境遇に堕ちた部族の長老たちから、七〇年以上前の、一九世紀前期から中期におよんだ戦争(血の河の戦い、斧戦争、そしてムランジェニ戦争)で、イギリスに敗北した諸部族の首長たちの数々の物語を聞いて育った。長老によって語られるのは、敗北した英雄たちのイギリス軍に対する「勇猛さ」であり、そして「心の広さ」、「慎み深き」である(遠征記は、諸部族を「カフィール族」と総称しているが、当時の蔑称である)。
少数を尊重する黒人伝統文化
養父の首長や側近たちが、部族の会議で示す政治を、僕は見てよく学んだ。
会議は満場一致までつづけられる、首長に向かって厳しく遠意のない批判が飛び交う、首長は聞き役に徹して終わりが近づくまでいっさい口を開かない。
反対があれば、会議は持ち越された。少数意見が多数意見に押しつぶされることはけっしてなかった。マンデラは、西欧の知識も十分に身につけた弁護士であったのだが、リーダーシップというものについては、南アフリカの部族会議から深く学び、それを後年まで育んだ、と述べている。
一九世紀半ばの当時、「未開」とされた黒人伝統文化には、欧米とちがって、少数を真に尊重するような独自の包容力があった。それが、マンデラたち、アフリカ民族会議(ANC)の、白人にも門戸を開いた汎アフリカ人主義の普遍的な考え方と運動を育てた一因である。一九九○年代には、マンデラとアフリカ民族会議は政権について、ついに白人支配をうち負かした。
黒人伝統文化は、滅ぼされることはなく生き続けた。部族会議を見聞し、敗北した英雄たちの話を聞いて彼が育ったのは一九二〇、三〇年代だが、当時南アフリカは、黒人を数パーセントの土地に押し込める政策が実施された最悪の時代であり、その時代を生きのび、反アパルトヘイト運動を支えた伝統文化の根強さは、まさに敬服に値する。それは、未開どころではない力量をもっていたのであり、欧米の文明を逆転したのである。
一九六〇年代になると、ベトナム戦争などにも影響されて、すでにアジアの伝熟した民衆
蝶統社会が再評価され始めていた。このような伝統文化・社会の世界的な再評価界の再評価の動向を承けて、一九八〇年代頃から、日本でも江戸時代後期の見方が新しく変わってきた。かつて日本は、欧米の文明に対して、半未開と位置づけられ、日本の側でも、維新政府以後は、そうした評価をすすんで受け容れてきたのであったが、それから、ようやく解き放されたのである。
とくに民衆史の研究で、伝統社会が新しく解明されている。本書でも紹介するように、江戸期の民衆の訴訟を願いでる活動は、私たちの想像よりはるかに活発だった。百姓一揆への一般百姓の参加も、事実上、公認されており、幕府や藩は、こうした農民の活発な訴えを受け容れることが多かった。江戸時代、幕府や藩の支配には、成熟した柔軟な仕組みがあった。
欧米列強の到来に対して、日本より事態がはるかに深刻だった南アフリカ(内的な発展は、高かったといわれている)でも伝統社会が解体しなかったのと通底しているのだが、幕府外交も、本文で述べるように、成熟した伝統社会を背景にその力量を発揮するのである。「極東」の東端という、地勢上、有利な位置にある日本においては、発展した伝統社会のもとで、開国が受け容れられ、ゆっくりと定着し、そうして日本の自立が守られた、というのが本書の一貫した立場である。
伝統社会の力は、幕府の外交能力に限らない。地域経済の発展に支えられた商人(売り込み 商人)たちが開港場にこぞって殺到したのもそのことをよく表している。日本では、貿易を、外からの圧力によってではなく、内から定着させてしまったという事実も、近年の経済史研究によって明らかにされている。
維新史を見なおす
日本の開国は、比較的早く定着した。そうであれば、幕末・維新期の対外的危機の大きさを強調するこれまでの評価を大はばに見なおす必要がある。
切迫した対外的危機を前提にしてしまうと、専制的な近代国家の急造すら「必至の国家的課題」だったということになる。しかし、一八七一年から政府要人たちが長期に米欧の回覧のために日本を「留守」にできたのはどういうふうに説明できるだろうか。欧米列強の圧力のあったのは事実だが、それに対抗してではなく、逆にそれを追い風として、明治政府の外交政策が東アジアの隣国に対する侵略へと向かう道筋、そして、日本民衆が伝統社会に依拠して、新政府に対して激しい戦いを展開した事実を中心として、江華島事件の新史料などの近年の成果を紹介しつつ、維新史をあらたに描きなおしたいと思う。
一八七二(明治五)年一二月二日までは、とくにことわらないかぎり、陰暦である。
なお、一八七三年一月一日以降は、陽暦に替わる。
引用史料は、スペースの関係と、分かりやすさを重んじて、原文の味わいを生かしつつ、部分的に、口語訳にしたところがある。また、かたかな文をひらがなに、漢字をひらがなに直したところもある。なお、引用文中カッコ内の説明は、筆者のものである。
目次
はじめに――喜望峰から江戸湾へ
第1章 江戸湾の外交
1 黒船来航
2 開国への道
3 二つの開国論
第2章 尊攘・討幕の時代
l 浮上する孝明天皇
2 薩長の改革運動
3 尊王攘夷と京都
第3章 開港と日本社会
1 開港と民衆世界
2 国際社会の中へ
3 攘夷と開国
第4章 近代国家の誕生
1 王政復古と「有司」専制
2 戊辰戦争
3 幕末維新期の民衆
4 近代国家の創出
5 版籍奉還と廃藩置県
第5章 「脱アジア」への道
1 急進的な改革
2 東北アジアの中で
3 東アジア侵略の第一段階
4 地租改正と西南戦争
おわりに
あとがき
参考文献
略年表
索引