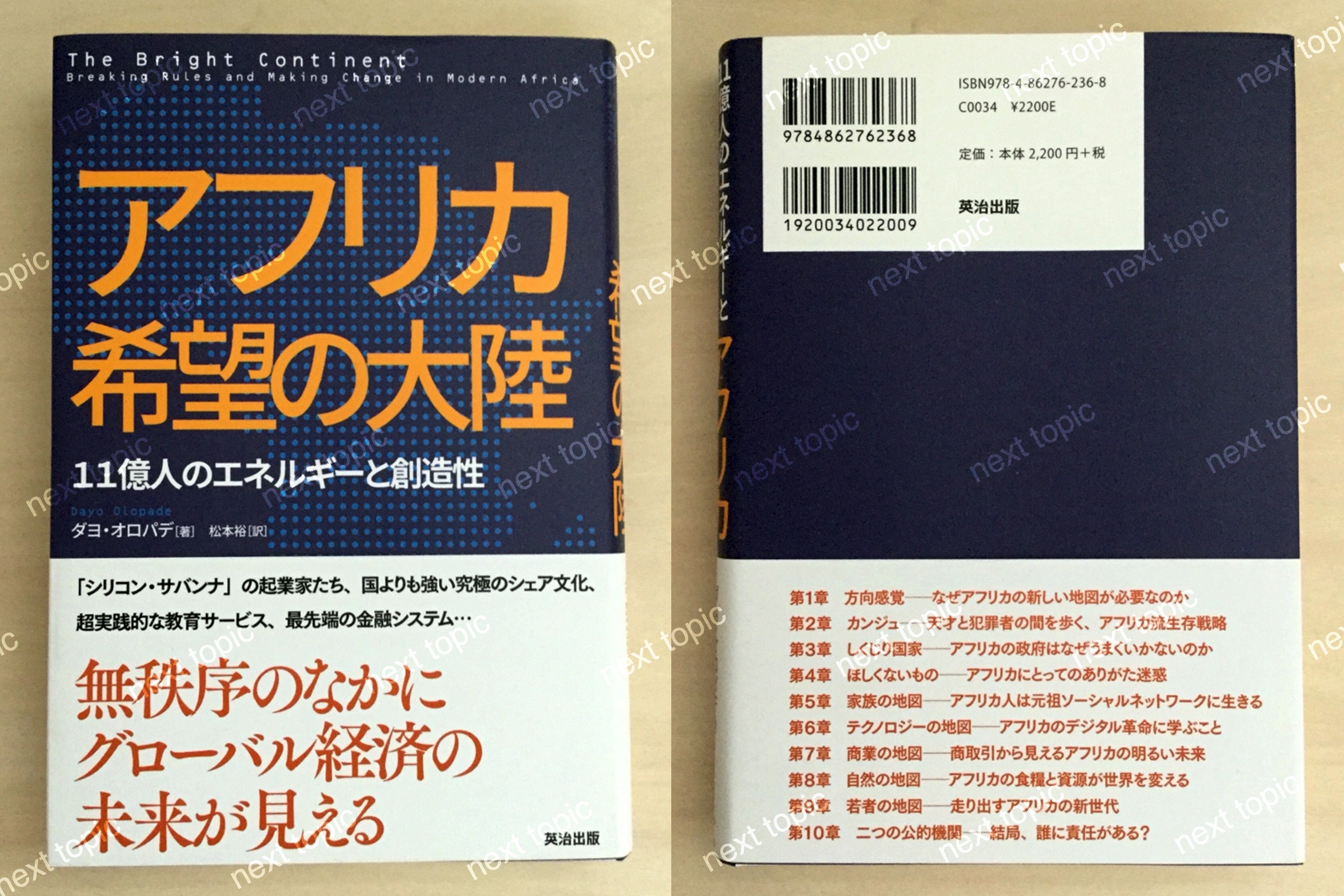ページコンテンツ
【最新 – アフリカの今を学べるおすすめ本(経済、政治、文化を知る)】も確認する
アフリカだけでなく、グローバル経済についてもわかる
この書籍が提供してくれる情報は経済と成長で、タイトルが示すようにアフリカ大陸にある希望です。アフリカの現在を生き生き描写しています。自分自身の見方を少しでも上書きするために、素直に受け入れながら読んでみてください。

目次
1方向感覚
なぜアフリカの新しい地図が必要なのか
「誰かに聞けばわかる」
秘密の庭園
世界は太っている
アフリカはひとつの国である
2 カンジュ
天才と犯罪者の間を歩く、アフリカ流生存戦略
ナイジェリアのメール詐欺に隠された真実
リサイクルとレジリエンス
灰色の経済
不正を暴く
3 しくじり国家
アフリカの政府はなぜうまくいかないのか
分離する国家
国家に巣食うハゲタカたち
悪い境界線は悪い隣人を生む
4ほしくないもの
アフリカにとってのありがた迷惑
Tシャツは自分で取っておいて!
部外者が立てた計画
行動する村
5家族の地図
アフリカ人は元祖ソーシャルネットワークに生きる
一緒にボウリング
口コミネットワーク
助け合う医療
頭脳流入
6 テクノロジーの地図
アフリカのデジタル革命に学ぶこと
急上昇する携帯電話普及率
電子マネー
クラスター経済
「とにかくアプリを立ち上げろ」
誰かの肉は誰かの毒
7商業の地図
商取引から見えるアフリカの明るい未来
取引をしよう
私立学校
売れよ、さらば来たらん
カンジュ的資本主義
8自然の地図
アフリカの食糧と資源が世界を変える
電力問題
食べるのは私たちの番
特区都市
電力を育てる。
9若者の地図
走り出すアフリカの新世代
「待ち期」
次世代の起業家を育てる
適切な進路を
放課後改革
10 二つの公的機関
結局、誰に責任がある?
脱出、声、忠誠心
最強の国家
市場試験
中心が中心でいられなくなる
謝辞
原注
架空の地図を本物だと信じて使う者 [1] は、地図をまったく持たない者よりも道に迷う可能性が高い。
経済学者エルンスト・フリードリッヒ・シューマッハ
エクス・アフリカ・センペル・アリクイド・ノヴィ (アフリカでは日々新しきものが見出される)
古代ローマの博物学者 プリニウス
第1章 方向感覚
なぜアフリカの新しい地図が必要なのか
「誰かに聞けばわかる」
ナイル川が発見されるまでには、二〇〇〇年もの歳月が必要だった。もっとも、それを発見と考えるのはおかしな話 だ。ウガンダ東部からエジプトの広大なデルタ地帯まで伸びるその穏やかな流れは、人類が存在する前からずっとそこに あったのだから。にもかかわらず、アフリカに最初に足を踏み入れた海外特派員たち(つまりヨーロッパから来た白人) は、この川の水源から河口までの地図を描こうという、驚くべき競争に夢中になった。アフリカの水路をたどって密林へ と分け入る彼らの旅の物語は、一八五〇年代のロンドンやブリュッセル、ニューヨークの新聞社へと送られた。エチオピ アで未知の部族に遭遇したことやアフリカ中部の奥地の湖へ無事たどり着いたことを報告しながら、彼らはアフリカについて仰々しい文章を書くという伝統の基礎を築いていったのだ。「暗黒大陸」という言葉を生み出したのは、コンゴの旅 について一八七八年に記したヘンリー・モートン・スタンリーだ。
アフリカが「暗黒」だという誤解は、西暦紀元前にすでに始まっていた。ヘロドトスが西暦紀元前五世紀に描いたアフ リカの地図は、この文明のゆりかごをほんの付け足しのようにしか描写していない(のちのメルカトル図法でも、アフリカ を文字通り過小評価して小さく描いている)。ヘロドトスはこう書いた。「人類がアフリカとアジアとヨーロッパを現在の ように分けたこと自体に唖然としている [1]。その分け方が非常に不公平だからである。ヨーロッパは他の二大陸の長さ全体を上回るほどで、その奥行きにいたっては(私の見解では)比較にすらならないほど深い」
その後一〇〇〇年にわたって、北へ向かって流れる川の謎はヨーロッパの地図製作者たちを悩ませ続けた。ディオゲネ スというギリシャの商人が、ナイルの水源は「ヌビア」の奥地、いわゆる「月の山脈」の合間にあるという噂を広めたり もしている。アフリカ大陸の西岸で交易が盛んになると、すでに知られていた部族や目印となる建造物などは、一八世紀 ヨーロッパの商業学校で教えられる精巧な筆致で地図に描きこまれた。だが、世界最長の川が伝説の「月の山脈」ではなくビクトリア湖から始まっていることをジョン・ハニング・スピークという探検家が「発見」するのは、それからしばらく経った一八五八年のことだった。
白ナイルの水源が発見されたという知らせがヨーロッパ中をさざなみのように伝わっていく中、エチオピア駐在のイギ リス領事R・E・チーズマン少佐がこのように述べている。「これほど有名な川が……これほど長い間無視されてきたと いう事実は、信じがたい」。ヘロドトスと同様、チーズマンもヨーロッパ人の文化的偏見を露呈してしまった。なにし ろ、ナイルはサハラの北と南を結んで言語や気候の橋渡しをし、モーゼの時代から何百万もの人々を養い、運んできたの だ。スピークがナイルを探検したころ[2]、ナイルの水源近くで生活し、交易をおこなっていた人の数は三〇〇万近か った。探検家たちも血眼になって探すより先に、地元の住民に水源がどこにあるか聞けばよかったのかもしれない。きっ と教えてくれただろう。「ここだよ」と。
このナイルの源流を探す旅は、非効率だっただけではない。現代アフリカの歴史を動かしてきた力学を象徴している。 何世紀にもわたる接触(主に奴隷貿易による)にもかかわらず、ヨーロッパ人は、その無知と尊大さで、アフリカを底知れ ぬ未知の大陸―小説家ジョゼフ・コンラッドが呼ぶところの「闇の奥」 と捉えてきたのだ。
ポルトガルとフランス、イギリス、ドイツを中心としたヨーロッパ勢力が自分たちの解釈で描いた地図を使い、勝手に 国境線を引いてアフリカを切り分けようと決めたのも、この尊大さの産物であったわけだ。一八八四年のベルリン会議 で、彼らは大陸にそれまで一切存在しなかった国境線を引き、タバコからピーナッツから黄金(その後まもなくして石油 も)まで、さまざまな天然資源を奪い合った。以来この国境線は、外国からの認識とアフリカの現実との間に横たわる埋めがたい構であり続けている。
その後一世紀以上経って、グーグルが誕生する。二〇〇七年以降、このアメリカの巨大IT企業はガーナやケニア、ナ イジェリア、セネガル、南アフリカ、ウガンダに支店を開設し、世界一使われているこのアメリカ製アプリにアフリカの 情報を取りこみ始めた。中でも、地図は最優先事項だった。グーグルのデジタル地図製作チームが大陸中に散り、アフリ カの街や通りをワールド・ワイド・ウェブという織物の中に織りこんでいった。アメリカ人たちは金に糸目をつけず、カ メラを搭載した真っ赤なプリウスで南アフリカ中の都市を駆けめぐり、グーグルのストリートビュー用の画像を撮影しまくって、どうにか二〇一〇年のFIFAワールドカップ南アフリカ大会に間に合わせた。
ナイルの水源を探したかつての地理学者たちと同様、現代のグーグルマップ作成者たちも方向感覚に関しては欧米の考え方を持ちこんだ。だがアフリカで道を聞いたことのある人ならわかるだろうが、この大陸では欧米とは異なる種類の方 向感覚が使われている。先進国では、かわいらしい女性の合成音声がわかりやすい指示で指定の番地まで案内してくれる かもしれない。だがアフリカでは、こんな感じになる。
タスキスの交差点のほうから来てるんだったら、ずっとランガタ通りのまま、ランガタ通りの「カーニヴォア」に 入る道を通り過ぎるまで走っていくんだ。そのあと、最初に出てくる右に曲がる道でランガタ通りを離れる。ランガ タ通りを〇・五秒くらい行ったら、「ラフィキズ」の隣にあるガソリンスタンドのすぐ手前で左に曲がる。その道を 三〇秒行って、右手に「サイズ・ランガタ」が見えたら、その左に入るんだ。
混乱しただろうか? これは私が本書の執筆中に暮らしていたケニアの首都ナイロビで実際に聞いた、典型的な道案内 だ。もちろん、ナイロビをはじめとしてアフリカの多くの都市では通りや地区には正式な名前があるし、建物にも番地が ついている。だがナイロビのようにもっとも国際的な都市であっても、住所はたいてい無視される。
地元の住民は道案内の強力な手段として会社や看板、バス停、美容院を活用している。時間や相対的な距離、自分を中 心に見た方向(右や左)、共通の知識に依存した方法をとるのだ。北スーダンの首都ハルツームでは、特に目立つ目印の ひとつが、かつて中国料理店の入っていたビルだった。そのビルが修繕中だった半年間、私は当時住んでいた家への道案 内を、道に開いた特に大きな穴ぼこを基準に伝えていた。だが最終的には「誰かに聞いて」と言うこともしょっちゅうだ った。
人類学者なら、ナイロビの通りを「ハイコンテクスト(訳注 : 実際に言葉として表現した内容よりも、言葉で表現していな いのに相手に理解される内容のほうが多い表現方法)」と呼ぶだろう。そのような道案内は、中央集権型のシステムが存在 しなかった時代の遺物だ(そして今もそのシステムが存在しない場合が多い)。そして、ここでもっと重要なのは、A地点 からB地点への道案内がハイコンテクストだったからと言って、B地点が存在しないというわけではない。ただ、普通と は別の地図が必要だというだけだ。
同じことが、現代のアフリカにも言える。道案内を標準化しようと苦労しているアメリカの大手IT企業でも、ビジネ スチャンスを探しているブラジル人起業家でも、冒険を探し求めるフランス人観光客でも、人々の暮らしをよくしようと している非営利組織でも、好奇心旺盛な世界の傍観者でも、サハラ砂漠の南側で営まれる暮らしを正しく記した地図はたぶん持っていないだろう。
実際、世界がほとんどアフリカのことを考えていないという事実が、私には不思議でならない。これは、時間と評価の 両方の意味でだ。ナイジェリア系アメリカ人二世である私自身には、アフリカに注意を向けるべき個人的理由がある。だ が、そういった事情がなくてもアフリカについて考えたときにその内容から学べることは非常に多いのだ。二〇一〇年 に、HIV感染対策から世界中の教育の質の改善まで、国際社会共通の八つの壮大な目標を掲げたミレニアム開発目標 (MDGs) 採択一〇周年を祝ったとき、国際連合はその記念として、ポスターのデザインコンペを企画した。優勝した デザインは、権力(主要八カ国の首脳たちの上半身)と貧困(難民キャンプで列に並ぶ若いアフリカ人たちの下半身)を合体さ せたものだった。このポスターはグラフィックデザインとしては気が利いているかもしれないが、そこにつけられたコピーには心が痛む。「世界中の指導者たちへ―私たちはまだ待っています」。貧しく、受け身なアフリカ人は欧米の行動 に恩恵を受ける形でしか存在しない、という近代史で一番の大嘘を、国連の審査員たちは受け入れたことになる。
「開発」関係の本を読んだことがあるなら、そのような印象を受けたことはあるだろう。世間一般で対アフリカ援助の論理が議論されるようになってもなお、議論は「欧米」がどうすればもっと成果を上げられるかという点に集中している。 開発業界でおなじみの論者たちは、G8の首脳から世界銀行の一般職員、果ては中央アフリカ共和国のような内陸国の首 脳にいたるまで、いわゆる万人向けの対処法を提示するだけだ。経済成長を妨げる固定観念や問題について多くの人々が 何十年もかけて検証しているが、ごく普通のアフリカ人たちが自ら前に進むためにすでにやっていることについては、めったに耳にしない。
本書は、その状況を変えるための本だ。一ジャーナリストとして、私は哲学者ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインの 助言、「考えるな、見ろ!」に従っている。アフリカ大陸に必要なのは、想像だけでお決まりの対応をすることではなく、目と耳を向けることだ。店主や日雇い労働者、経営者、教育者など、アフリカに暮らす現実の人々の声を聞き、彼ら の物語を伝えることに専心すれば、一度は隠れてしまった彼らの力強さに再び光が当たるのだ。
その物語はたとえば、歩いて仕事に行くという単純なものであったりする。あるとき、私は母と一緒にケニアからウガ ンダ行きの早朝便に乗ることになった。太陽が昇るよりも早く目をさまし、空港へ車で向かう途中、列をなして歩く人影 が道の両側に見えてきた。「みんなどこへ行くのかしら?」と母が不思議がる。都心へ向かって流れていく人影は、行進 する子ども兵でもなければ蚊帳の配給を求める母親の列でもない。何千人というごく普通の人々が、仕事に向かっている のだった。アフリカでは何億もの人々が毎日夜明け前に目をさまし、家族を養うためにこうして歩いて通勤しているのだ。
秘密の庭園
本書を執筆していた間ほぼ毎日、私は自分が住むケニアの首都ナイロビの共同住宅の窓から、隣にある空き地で土を耕す女性、グラディス・ムウェンデの姿を目にしていた。厳密には、彼女にそのようなことをする権利はない。マチャコスという小さな町からナイロビに移り住んできたグラディスと夫のベンソン・ムサメ、そして六人の子どもたちは、私の家 の窓から見える植民地時代から残る空き家に住みついた。石とタイルづくりで、上は一三歳から下は一〇カ月までの六人 の子ども全員に行き渡るだけの部屋数がある二階建てのきれいな家だ。その家の全盛期がはるか昔に過ぎ去ったことを教 えてくれるのは、穴の開いた窓と朽ちかけた木の装飾だけだった。
ケニア最大の都市のにぎやかな交差点に建つこの家で、この家族がアフリカの田舎暮らし焚き火で料理をし、水を 運び、ニワトリを育てる生活を再現しているのは奇妙な光景だった。だが、問題は空き地のほうだ。勝手に土地の管 理人を自任した一家は、大都会の畑をまるで、世界のコーヒーと紅茶と花を育てるアフリカ大地溝帯の大農園のように扱 っていた。
春になると、一家はヤシとミモザの木が影を作るところは慎重に避けながら、トウモロコシを畑に植えた。夫のベンソンが警備員として働く間、歩ける子どもたちはグラディスを手伝ってトウモロコシやマメの種をまき、草をむしり、なん とサトウキビまで育てていた。雨期の間、私は取材メモをタイプし、国の開発政策について調べるかたわら、若芽が育つ のを眺めた。夏の盛りには、トウモロコシは人の背丈を超える高さまで成長していた。一家は最初に収穫したトウモロコ シの一部を焼いて、夕暮れどきに家路を急ぐ労働者に売った。私が夕食を作る時間帯には、売店代わりのバス停のあたり から、排気ガスにまじって焚き火の煙のにおいがしてきたものだ。だが基本的には自分たちが食べるために植え、生きる ために食べるのさ、とグラディスは言った。
ミシェル・オバマ米大統領夫人も誇らしく思うことだろう。私は、一家のずぶとさに感服した。彼らは正式にはなんの 権利もなく、支援も受けず、農業技術も持たないが、アフリカ中の何百万という自給自足農家と同じように、一エーカー (約四000平米)の土地から価値を引き出す方法を見つけたのだ。彼らの静かな努力こそ、国連のポスターに直接反論 する行動であり、アフリカの発展の道筋を大きく、楽しみな方向へと変えていく大胆な日和見主義のいい例だ。
彼らの行動は、我々がアフリカに対する判断をいかに誤りがちかを思い知らせてもくれる。満員のバスから転がり出た り、バイクタクシーを呼び止めたりする何千人もの通勤客たちは、この秘密の庭園に気づいていない。近所の住民にすれ ば、廃屋は目障りなだけだ。政府の政策立案者にしてみれば、一家は不法侵入者だ。私は窓から俯瞰で毎日目にしていた からこそ、その土地は実質的に一家の資産であると捉えることができたのだろう。
このような目につきにくい成功について人々に伝えることが、首脳たちが口にするような、アフリカの発展をかえって 妨げてしまう重苦しい話に対抗する、私なりの最善の手段だ。そのために私は、ほかの多くの先達ナイジェリア人と同 様、物書きという道を選んだ。物語は、欧米の新聞でほんの小さなコラムを埋めたり、ケーブルテレビのニュース番組で 画面の下を横切るテロップで伝えられたりする、悲観的なニュースに対抗する力になってくれる。本書に記した物語の 数々は、私が「形式的バイアス」と名づけたもの――廃屋は廃屋でしかなく、A地点からB地点にたどり着く方法は地図 に描かれた正式な道路を通る以外にないという思いこみーに対抗するものだ。
国連などの国際機関、経済学者、人道活動家、私のようなジャーナリストなどは往々にして、歩いて通勤する人々や都 会の空き地で育つ野菜、目印になる穴ぼこや雑貨店から目を背けがちだ。では何に目を向けているのかというと、アフリ カの公式な組織と公式な解決策にばかり注目している。いくつ学校を作ったか? 去年何人の母親が死んだか? 選挙は 公明正大におこなわれたか?
つまるところ、私たちはからっぽの会場でパーティーを開いていただけだったのだ。世界がアフリカに対して長年抱いてきた印象には、大きな問題がいくつもある。そのうち最大の問題のひとつが、もっとも活発で本質的かつ経済的に重要 な交流が、個人やばらばらの集団の間でおこなわれているにもかかわらず、世界は政府間または公式な組織間の交流のほうばかり重視してきたということだ。グラディスとベンソン夫婦のような非公式なやり方のほうが実は日々の暮らしを構 成しているのだということに、私は気づいた。「開発」に関しても、こうした非公式なやり方のほうがもっと早く、もっ と多くの、あるいはもっといい成果を上げられる場合もあるのだ。
例として、騒乱にまで発展した二〇〇七年のケニアの大統領選挙後に立ち上げられた非営利のソフト開発組織、「ウシ ャヒディ」を見てみよう。民族という境界線で引き裂かれた現職のムワイ・キバキと対立候補のライラ・オディンガのそれぞれの支持者たちが、何週間にもわたって地方都市や主要都市でもみあった。約一二〇〇人の死者が出て、暴動によって家を失った人は三五万人を超えた。その間ずっと、テレビ局とラジオ局はその責務を果たしていなかった。通りで血が 流れている間、退屈なバックグラウンドミュージックをひたすら流し続けていたのだ。身のすくむようなこの期間、アフリカでもっとも安定している民主主義国家のひとつが、混沌の淵を転げ落ちるかに見えた。
最初はブログで、次はメールで各地の情報が集まり始め、それからケニアの技術屋たちのチームが実際に集結し、市民 が携帯電話を使って暴力行為を報告できるマッピングソフトを開発し始めた。スワヒリ語で「目撃者」を意味するこのソ フト、「ウシャヒディ」を使って何千という地点から情報が共有され、リアルタイムで地域に特化した情報を取り込んだ 地図が作り上げられたことで、秩序を回復して救援の手を差し伸べようという努力が加速していったのだ。
以来、ウシャヒディはさまざまな形を取って世界中に広がっていった。パレスチナのガザ地区での混乱を監視し、スー ダンや南米での選挙を監視し、二〇〇九年には豚インフルエンザの蔓延を追跡し、アメリカではメキシコ湾原油流出事故 で流れ出た石油を監視し、二〇一〇年にハイチを襲ったマグニチュード七・。の地震では生存者の支援に役立った。ビ ル・クリントンとヒラリー・クリントン夫妻もこのウシャヒディの活動を称賛している。ケニアが二〇一三年に新大統領 を選んだときは、ウシャヒディから派生した「ウチャグジ(「選挙」の意味)」が政府の対応と市民の行動に目を光らせた。
ナイジェリアで二〇一一年四月に選挙がおこなわれたときにも、ウシャヒディは活躍した。その一カ月間、私はナイジ リア最大の都市ラゴスで過ごしていた―不安いっぱいで。ケニアの二〇〇七年の選挙と同様、ナイジェリアの前回の 選挙も詐欺と不正行為、票の数え間違い、開票の遅れなどで台無しになっていたからだ。次の投票日が近づくと、「リク レイム・ナイジャ (ナイジェリアを取り戻せ)」と呼ばれる市民社会団体が大陸の反対側にあるケニアに助けを求めた。その開発者たちが一貫して主張しているように、ウシャヒディのモデルは市民がリアルタイムで問題を報告しなければ機能 しない。そのためには、正確に電話番号を伝える必要があるのだ。
この共同プロジェクトを率いた直情型の活動家、ンゴジ・イウェレは、ナイジェリアで長年にわたってHIVの予防な どの医療関連のコミュニケーション戦略に取り組んできた人物だ。広報活動なら、どこから手をつければいいか彼女は確 実にわかっている。テレビや新聞を使った大々的なキャンペーンを打ち出す代わりに、リクレイム・ナイジャは仕立屋や 肉屋、車のバッテリー交換屋、家具職人、石工、整備士、美容師、露店商人、バイクタクシー運転手たちに協力を求め た。実は、多くの同業組合が定期的に集まっては支払いなどをすませるついでに、政治についておしゃべりしていたの だ。こうした組合に対して、イウェレたちは一般大衆向けのスローガンを伝えた。英語と現地語をないまぜにしたピジン 英語で、そのスローガンはこう訴えた。「登録や投票のときにはっきりしない、あやしげな動きを見たら、リクレイム・ ナイジャに報告しよう!」 「あれは、私が見た中でもっとも見事なマーケティング戦略でした」と語るのは、ケニアからはるばるナイジェリアまで ウシャヒディの展開を支援しにやってきた開発者の一人、リンダ・カマウだ。ナイジェリアで「オカダ」と呼ばれるバイ クタクシーは、毎日何十人もの客を乗せて走る。投票箱が盗まれるような事件が起きたときに、ショートメールで報告するための電話番号を伝えるのに最適な場所だ(美容師たちは、さらにじっくりと客に情報を伝えた)。
オカダのドライバーはシンボルとしてはちょっと風変わりだが、内側から外に向かって働きかけるという、発展の新しい一面を代表している。これまでの海外からの介入は演繹的、つまり外から中に働きかける形だった。時間と予算を投資 して「業界」の「利害関係者」たちの「ネットワーク」を構築し、所定のメッセージを宣伝したり二元論的計画を実行し たりしてきたのだ。多くの人々がヨーロッパ中心の地図作製者と同じように、もっと適応能力が高いだけでなく、無料で 活用できる既存のプラットフォームを見落としていた。
本書では、サハラ以南アフリカのそのようなプラットフォームあるいは地図―を五つ見ていく。特に注目するの は植民地としての過去と比較的開発が遅れている現状が共通している、四五の地続きの国だ(北アフリカの国々はこの条件 にあてはまらないので除く)。奴隷制度と帝国主義に、政府の弱い統治能力が組み合わさって、これらの国は同じような不満と似たようなチャンスに沸き立ってきた。東南アジアや中南米、東欧と比べても、アフリカはひどく過小評価されている地域でもある。私が紹介する「家族」、「テクノロジー」、「商業」、「自然」、そして「若さ」という五つの地図 は、ブラック・アフリカを団結させて明るい未来を形作っていく個性的な仕組みを見せてくれる。 「家族」の地図は、必要不可欠な構成要素だ。私が旅した先はどこでも、社会的な人間関係が暮らしを定義し、向上させ ていた。この拡張された「家族」という現象は、政府によるセーフティネットが欠如している場合には特に有用となる。 本書で紹介するように、アフリカの中に構築された横のつながりは命を救い、ビジネスを立ち上げ、暗闇を照らすことが できるのだ。アフリカの家族には、階大な数の海外移住組も含まれる。彼らも財政、イノベーション、そして影響力の面 で重要な資産だ。
「テクノロジー」の地図はサハラ以南のアフリカで一番の隠し玉で、ニーズと才能が出合う刺激的な領域だ。インターネットと携帯電話の爆発的な普及は、サービスの提供、情報の拡散、経済成長のまったく新しい基礎を築き上げている。数 えきれないほどの地方ベンチャーがこのグローバル化の波に乗って、合理的かつ驚異的な成果を上げているのだ。 「商業」の地図は、大小問わず市場についてのものだ。ここでは何百万人というアフリカ人消費者が生きていく基盤を見 出し、発展のためのいままでにない策を編み出している。市場の力と人のニーズとを引き合わせるベンチャーは、まったく新しい形の資本主義そのものを作り出しているとまではいかないにしても、新しい形の発展手段を作り出していると言 える。
「自然」の地図は、アフリカの圧倒的な地理的メリットである土と太陽、水、そして世界の東、西、北との歴史的なつながりに関するものだ。アフリカの資源という富が、石油や鉱物だけにとどまらないことはますます明白になってきてい る。実際、食糧生産とエネルギー消費、都市化の未来は、アフリカで形作られるのだから。アフリカには、地域の繁栄と地球環境のバランスを両立する、独自の態勢が整っている。
同様に、サハラ以南のアフリカは、驚くべき規模の「人口ボーナス(訳注 : 就労人口の増加によって経済発展にプラスの影 響が得られること)」を誇る。ここは世界でもっとも年若い地域で、人口の七〇%が三〇歳未満なのだ。無垢な状態から 力を得ていく何億という若者の存在は、いい方向にも悪い方向にも可能性を秘めている。「若者」の地図の基盤となるの は、私たち全員にとって未来を左右する、独創的な教育方法だ。
これから見ていくことだが、アフリカは資源と公的機関が豊富な土地だ――公平な目で見さえすれば。これらアフリカ の非公式な地図は、同時に使うにしても、それぞれ使うにしても、政府や慈善活動、既存のNGO等の正式な仕組みより も、強い生産力と影響力を生み出す。その力を発揮すれば、巧妙かつ効果的な方法で従来の開発活動に爆発的なエネルギーを与えられるはずだ。ただし、地図を読む際の基本原則通り、自分が今どこにいて、何を持っているかがちゃんとわかっていないと、これからどこに行こうとしていて、何が必要なのかはわからない。
世界は太っている
ここで、用語について一言。「開発」という表現が大嫌いな人間が、「開発」についての本を書くのはけっこう大変な ものだ――私自身がそうなのだが。「開発」という言葉は、特定の国が何かに向かって「開発」を進めていて、そこに到 達する道はひとつしかないということを示唆している。文中で「開発」という言葉を使いはするが、世界を「太っている (裕福である)」と「痩せている(貧しい)」という言葉で説明するのもわかりやすいのではないかと思う(*)。 「太っている」と「痩せている」という枠組みは、古くさい「第一世界」「第二世界」「第三世界」という言い方や、より新しい「グローバル・サウス」「グローバル・ノース」という言い方からは一歩離れた見方だ。昔は基本方位も好まれ てきた(開発に関する本の多くが、貧しい国と「西側」を対置している)が、そのような方向感覚は今ではもう意味がない。 ヨーロッパ中心の地図でさえ示していることだが、今世紀の経済エネルギーの大半は東方向にあるアジア亜大陸や、中南 米の嗜大な数の取引相手との間で発生しているのだ。「開発」と同様、「南北」という用語は、私たちを取り巻くこの世 界をちゃんと理解する手助けにはなってくれない。
では、「太っている」経済とはどんなものなのか? 私が生まれた国、アメリカがそのひとつだ。経済協力開発機構 (OECD)に加盟している富裕国では、豊かさはあたりまえのことだ。物が大量にある状態が普通[3] で、国民総所得 (GNI)は年間一人当たり約四万一一〇〇ドル。問題を解決すると言っても、衛生環境や予防接種、電化といった基本 的問題とはかけ離れたものになる。当事者にとってはあまり慰めにならないかもしれないが、「太っている」経済では一 番貧しい人でも、歴史的に見れば過去のどの時代の人類よりも快適な暮らしをしているはずだ。
もちろん、マイナス面もある。アメリカの肥満率は世界最悪だし、ほかにももっと比喩的な意味での「肥満」問題にも 苦しんでいる。サブプライムローン問題、見返りを求める献金が蔓延する政治、甘すぎるがゆえに多くの問題を生む石油 の蜜の味。ヨーロッパ、オーストラリア、韓国などの太った国も、やはり富の報酬を管理するのに苦労している。消費に よって加速し、さざ波のように広がっていったここ一〇年の経済危機は、OECD全体の慢心を暴く結果となった。これ を受けた「緊縮」制作は、一部の太った国を今後何十年も続くであろう危機にさらしている。
一方、アフリカは「痩せて」いる。東・中央アジアの新興経済国とサハラ以南アフリカのほぼすべての国(国連はこれ らの国を「後発開発途上国」と定義している)では、GNIの平均は年間一人当たりたったの一二〇〇ドルだ。このような 痩せた国、特にアフリカでは、病気という重荷の負担がかなり違う。マラリア、HIV/エイズ、そして出産は、アフリ カ大陸では死因の上位を占めるのだ。私の両親の生まれ故郷であるナイジェリアも、衝撃的なほどの乳幼児死亡率、とど まるところを知らない失業率、毎月二六日間もの停電に悩まされている。
こうした問題の陰には、希望の兆しが多く隠れている。アフリカ人一人ひとりを個別に見てみると、食べ物は無駄にし ないし、借金は少ないし、地域全体の二酸化炭素排出量は世界でも最低水準だ。そして無謀な世界市場からおおむね排除 されてきたこともあって、アフリカは最悪の金融危機も回避することができた。これから見ていくように、アフリカのビ ジネスの多くはより効率的な運営を目指して、「痩せている」モデルを実務と財務の両方に適用している。世界が財政の スリム化に向けて着実にベルトを締めていくのであれば、目指すべきは「アフリカ」という印のついたベルト穴だ。 「痩せた」国と「太った」国の区別を分かりやすく説明するため、私はよくトイレの「音姫」を開発した日本の企業、T OTOの話を引き合いに出す。いまや日本で数多くのトイレに取りつけられている「音姫」は、水洗の音をリアルに再現 する機械だ。「音姫」が解決したのは比較的裕福な国だからこそ生じる問題で、つまりは日本人女性が用を足す際の音を 恥ずかしがって公衆トイレでずっと水を流し続けるのをやめさせるためだった。TOTOの発明で、水の無駄遣いという 問題は解決された。お財布にやさしい携帯タイプが、今はベストセラー商品となっている。(訳注 : 現在は販売終了)
痩せた国では、トイレ関連の発明はだいぶ様子が違っている。アフリカでもっとも人口が密集した地域で一時期もてはやされた排泄物処理方法が「空飛ぶトイレ」―排泄物をビニール袋に詰めて、できるだけ遠くに投げ捨てるというもの だった。無理もない。日本の滅菌された全自動の公衆トイレとはまったく違い、アフリカの非公式居住区に暮らす人たちのほぼ半数が、近代的な衛生設備という基本的な尊厳を欠いているのだ。汚物まみれの水は、病気を蔓延させる。そのう え、大都市特有の犯罪を恐れて、夜中に公衆トイレを使うことを避ける住民が多い。「空飛ぶトイレ」はそうした背景で 生まれたその場しのぎの発明で、明らかに問題のある方法だ。 ケニアのコミュニティ組織「ウマンデ・トラスト」[4]は、もっといい方法を思いついた。非公式居住区のひとつ、ガトウェケラの住民グループと協力し、彼らは巨大な円筒形の堆肥装置を作り、そこに作りつけたいくつもの個室トイレから出た排泄物で堆肥を作れるようにしたのだ。ウマンデはトイレの使用料としてほんのわずかな額を徴収し、毎月四〇 0ドル程度の収入を得ている。さらにいいことに、このシステムなら従来の水洗トイレのように水資源を浪費せずにすむ うえ、排泄物からバイオガスを生成することでコミュニティの集会所で使う電気を作ったり、毎日シャワーを浴びに来る四〇〇人の住民が使えるだけのお湯を温めたりすることもできるのだ。
このように、人の尊厳を守るという目的は一緒でもまったく異なる発明が生まれるのが、「太った」国と「痩せた」国 の違いだ。「音姫」は、経済のピラミッドの上層部向けに作られた発明品の数々の一つだ。この階層の発明品はほかにも 駐車場で空きスポットを見つけてくれるソフト、本物ではないデジタル作物を育てる「農場」アプリ、iPhoneを振るとムチの音が出るアプリなどがある。いずれも、トイレのような基本的な問題が解決したあとで生じる問題に対処する発明だ。
だが、空飛ぶトイレがまかりとおる現状では、なんでもありだ。痩せている経済は、どれほど大きな課題を抱えていよ うとも、発明を生む土壌となる。必要が発明の母だと言うなら、アフリカの逆境は必要の母と言えるだろう。
植民地主義と独裁政権、貧困の歴史という酸っぱすぎるレモンが、アフリカになかなかいいレモネードのレシピを与えてくれたわけだ。ここからの何章かでレシピについて説明して、それからレモネードの話をしよう。指導者たちによる一 番まずいやり方ではなく、現地の人々による一番うまいやり方を検証するとどうなるか、何世紀も前から存在していた非 公式経済や非国家ネットワークに正式に耳を傾けるとどうなるかを見ていく。
本書では、アフリカに問題がまったくないと言いたいわけではない。すべての政府、すべての援助、すべての近代化がアフリカにとって悪いと言いたいわけでもない。当然、投資のアドバイスをするものでも、きめ細かい経済分析をするも のでもない。だが、進歩を妨げる「形式的バイアス」を暴き出し、アフリカに生きるすべての人々の未来を後押ししていける名案に光を当てたいと思う。
アフリカに関わる上で、何よりも重要なのが異なる点から学ぶことだ。太った国は痩せた国が自分たちから学ぶべきだ と思いこんでいるかもしれないが、太った国が痩せた国から学ぶべきことがあるのもまた事実だ。太った国で金融経済崩 壊後に広まった節約精神――少しの時間、少しのエネルギー、少しのお金でもっと多くのことを成し遂げようという精神は、サハラ以南アフリカでは必要不可欠な生活手段であると同時に、世界にとっての新たな責務なのだ。
アフリカはひとつの国である
最後に、方法論についてもう一言。本書で紹介するすべての事例は、外部の出典が明記されている場合を除き、私の直 接の取材によって得られたものだ。そして文中では「アフリカ」について語っているが、これは一〇億近くの、私がほとんど会ったことのない人々を指す。「アフリカについての書き方」という、ケニア人作家ビニャヴァンガ・ワイナイナが 書いたエッセイがある。これは、私のような人間が「してはいけないこと」を記した、広く出回っているリストだ。ワイ ナイナの風刺に富んだ助言は、このように述べている。
正確な描写にこだわって、身動きが取れなくなってしまってはいけない[5]。アフリカは広い。五四の国に暮らす九億という人口は、移住したり戦争したり命を落としたりするのに忙しすぎて、あなたの本を読む暇などないの だ。この大陸は砂漠とジャングル、高原、サバンナ等々だらけだが、あなたの本の読者はそんなことは少しも気にかけていない。だから説明はロマンティックかつ刺激的にして、そして細かくし過ぎないことだ。
私は、アフリカをひとつの国としては扱わない。三年をかけて一七カ国を取材した私は、到底ひとくくりになどできないほどの多様性を目撃してきた。それでも、本書は汎アフリカ的だと胸を張って言える。私たちは似たような困難からしっかりと学ぶことができるし、多種多様な成功からはさらに学べると信じている。大陸を横断して事実を比較しようというのも、ひとつの必要な熱意だ。ただその点については、私はその表面をほんの少し引っかいただけに過ぎない。
まずは一九世紀の、アフリカの地図を作ろうとする物語から始めた。この物語は、二〇世紀の開発へ向けた屈辱的な努 力を映し出す鏡だからだ。MDGsが終了し、二一世紀における人類の進歩が展開していく今、私たちは一九世紀のとき よりももっとうまくやっていかなければならない。ナイル川に沿って旅していた探検家たちは、歴史的に無知だったという言い訳ができる。なんといっても、空からの視点で川や道路を地図に描いていくという考え自体を人間が受け入れるまで、何世紀もかかったのだから。ジャングルの中を歩き回り、山を登り、草原を横断している間は、俯瞰したときに自分 の歩みがどんなふうになっているかなど想像もできないし、物の見方を変えることがどうして役に立つのかもわからない ものだ。
これまでに目にしてきた戦争、あって当然のものとみなしている貧困、愛想を尽かしたくなるような政府などの側面か らアフリカについて考えると、核心を見失ってしまう。画期的な技術と情報がすぐに手に入るこの時代、無知は言い訳に ならない。本書で紹介する物語は、新たな羅針盤を提供してくれるだろう。アフリカ大陸のためだけでなく、世界経済の すべての分野のための羅針盤だ。
* 資本の社会的利益を重視する投資会社アキュメン・ファンドのネイト・ローレルが、最初にこの区別を定義した。